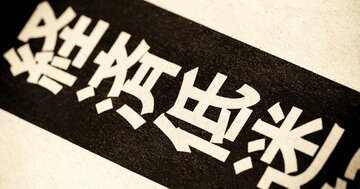日本人、そして日本企業はクオリティが本来持つ意味に立ち返るべきである。
デフレマインドの払拭といってもよく、足元のインフレ基調がそのきっかけになるかもしれない。純粋に価値が高いものをそれなりの高価格で販売しているのがスイスだ。
高価格帯の商品で溢れても
スイス市民の生活は破綻しない
しかしこういうと、市民の日常生活はどうなるのかと思われるかもしれない。クオリティ戦略とは、国内外の富裕層だけを相手にしていて、大多数の市民を置き去りにするのかという話だ。
これに対しては2つ述べておきたい。
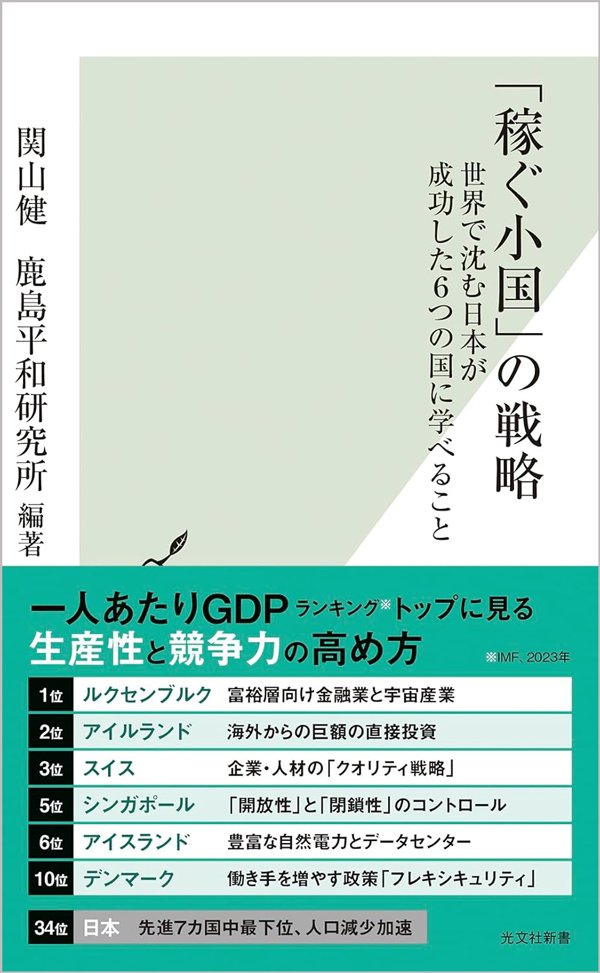 『「稼ぐ小国」の戦略 世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること』(関山 健、鹿島平和研究所、光文社)
『「稼ぐ小国」の戦略 世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること』(関山 健、鹿島平和研究所、光文社)
1つ目は、スイスの賃金水準の高さである。日本人がスイスに旅行すると、物価が日本の3倍くらい高いと感じるはずだ。しかしスイスの賃金水準も同じく高く、スイスの月額平均賃金は6500スイスフラン(約110万円/月)といわれている(My swiss company、2024)。つまり物価の高さに見合った賃金水準になっているということだ。
2つ目はスイスにおける価格帯の幅の広さである。スイスでは同じ商品(例:ペットボトルの水)でも購入する場所でずいぶんと価格や商品ラインナップに幅がある。市民は安価なところで購入するが、外国人観光客はそのような場所を知らず、高いところで購入しがちである。
つまり、販売チャネルや商品の多様化によって価格の幅を広げておくことで、市民の生活を圧迫しないような工夫もされているということだ。