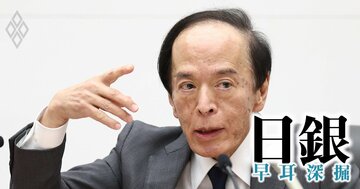重要なのは実質金利の判断
マイナスなら利上げが必要
その点で、特に重要なのは、現在の実質金利がマイナスの領域にあるか否かの判断だ。実質金利がマイナスと判断されれば、利上げの必要がある。
実質金利がどの程度の水準なのかの判断にあたっては、期待インフレ率を推計する必要がある。ここで「期待インフレ率」とは、将来のインフレ率の予想値のことだ。将来のインフレ予想を決める重要な要素は、現在のインフレ率だ。
この問題を考える際のインフレ率、消費者物価上昇率としては、次のようにいくつかのものが考えられる(カッコ内の数字は25年7月における対前年同月比)。
▼コアCPI:生鮮食品を除く消費者物価指数(3.1%)
▼コアコアCPI:生鮮食品及びエネルギーを除く総合(3.4%)
▼食品(酒類除く)及びエネルギーを除く総合(1.6%)
日銀は、消費者物価としてコアCPIを取っているが、前回7月の決定会合時に公表された「経済・物価情勢の展望」(25年7月)では、「消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、25年度に2%台後半となった後、26年度は1%台後半、27年度は2%程度となると予想される」としていた。
これは、次のような考えによると推測される。
消費者物価としては「コアCPI」を考えるが、ここに含まれる「食品」(特にコメ)は、短期的な条件で上昇している面がある。したがって、将来を見る場合には、コアCPIの上昇率は7月のような高い値(3.1%)にはならず、「食品(酒類除く)及びエネルギーを除く総合」の上昇率(1.6%)に近い2%程度になる。
9月19日に発表された直近8月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は、対前年同月比2.7%増となり、昨年11月以来9カ月ぶりに3%を下回った。
これは、上記の日銀の展望レポートの見通し通りの結果のように見える。しかし、これは政府が電気・ガス料金の補助を7月に再開したことの影響が大きい。つまり、本来の消費者物価の動きから外れている可能性がある。
現在の実質金利マイナス0.5%程度!?
懸念される投機的行動や資産価格の高騰
仮に現状での期待インフレ率を2%程度としても、現在の10年国債の名目利回りは1.5%前後なので、実質金利はマイナス0.5%程度ということになる。
金融政策が経済活動に中立的になるには、実質金利を経済の実質潜在成長率に等しくすることが必要であると、経済理論で明らかにされている。
日本経済の実質潜在成長率は、低下はしているものの、プラスだと考えられるため、マイナスの実質金利は、景気活動に過度の刺激を与え、健全な資源配分をゆがめる要因となり得ると考えられる。