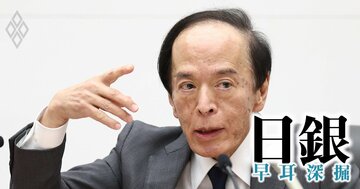また、仮にコアCPIの伸び率が将来、鈍化せず、7月のように3%を超える水準にとどまるとすれば、実質金利はマイナス1.5%ということになるだろう。その場合には、日本経済の資源配分は大きくゆがむだろう。
具体的には、以下のような副作用が考えられる。
▼過剰な投資や借り入れ
▼不動産や株式など資産価格の高騰
▼その他、生産性向上を伴わない投機的活動の増加
円安過ぎる現在の市場為替レート
過剰な外需依存、内需回復を遅らせる
過度な低金利政策は、為替市場にも大きなゆがみをもたらす。これは「実質実効為替レート指数」によって表されている。
これは通貨の購買力を測る総合的な指標だ。基準時点(2010年)を100とする指数で表されている。ある通貨の実質実効為替レート指数の下落は、その通貨の購買力の低下を意味する。
この値を見ると、最近時点で72.2程度だ。つまり、円の購買力は、10年に比べて約3割低下したことになる。10年に円の市場為替レートが1ドル80円台に迫る水準だったことと比べると、現在の1ドル140円後半の市場為替レートは、円安すぎるということになる。
実質実効為替レート指数のデータを過去にさかのぼってみると、いまは1970年ごろの値とほぼ同水準だ。
70年代の初め、私は留学生としてアメリカにいた。当時の私の日本での月給は2万3000円程度。しかし、大学周辺のアパートは、独身用一部屋でも100ドルを超えていた。日本円に換算すれば、3万6000円だ。日米の豊かさの差を思い知らされた。日本円の実力は、その当時とほぼ変わらぬ状態にまで低下してしまったのだ。
為替のゆがみによって生じる外需への過剰な依存構造は、内需回復を遅らせる一因となっている。日本経済の持続可能な成長のためには、為替レートを適正な水準にすることが必要だ。現在の日本経済は、低金利、円安という構造的ゆがみに直面している。これらが相互に作用し、経済活動の効率性を損なっている。
日銀は、金融政策正常化の戦略を明確に描き、その基本は経済の構造的安定性を回復することに置くべきだ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)