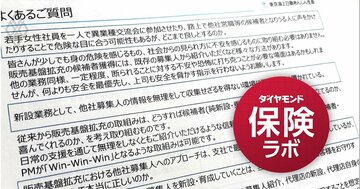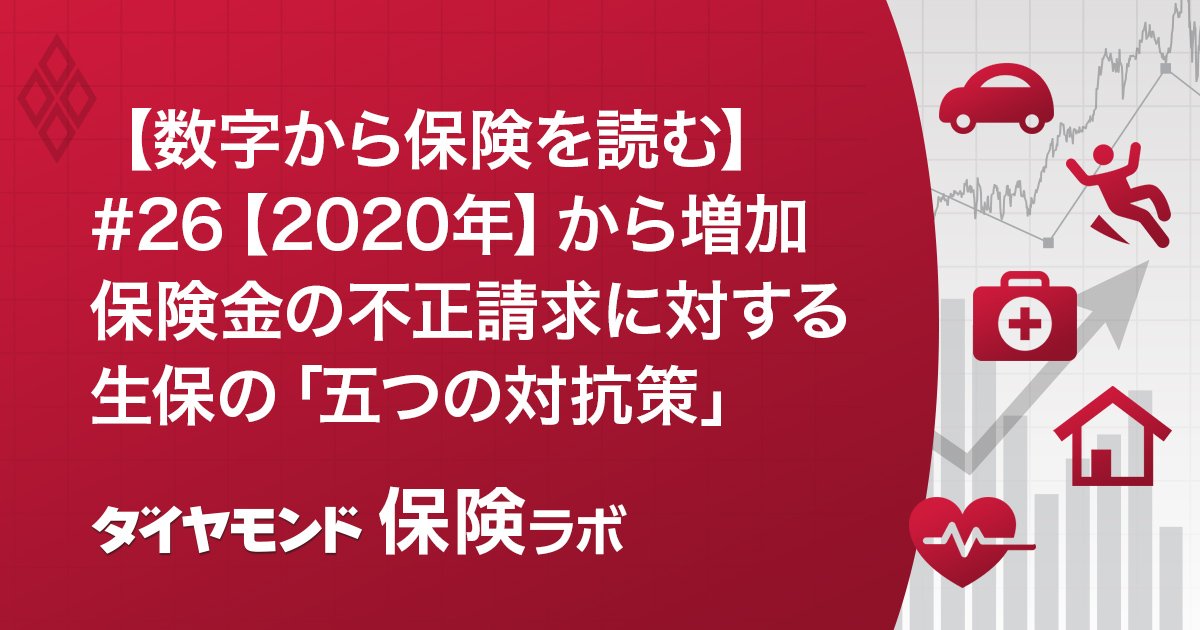
新型コロナウイルス感染症のまん延以降、保険金・給付金の不正請求が急増し、保険における公平性を損なう事態となっている。その理由は何なのか。そこで連載『ダイヤモンド保険ラボ』の本稿では、生保会社が取り得る五つの対策をお届けする。(野口俊哉)
コロナ禍以降に急増した
保険金・給付金の不正請求
「最近給付金の請求がやけに多いな。あれ、また同じ病気で入院一時金が20万円か。えっ!? このお客さま、他にも10社に請求しているの?」
生命保険会社の保険金・給付金の支払い部門は、毎日がこのような給付金請求との戦いだ。
特に新型コロナウイルス感染症のまん延以後の状況はひどいもので、明らかに保険金・給付金の不正請求と疑われる事案が大量に発生しており、生命保険会社も対応に苦慮しているのが実情だ。
逆選択リスクとモラルリスク
保険においては公平性の原則が存在する。つまり、保険料はお客さまのリスクに応じて設定され、加入したお客さま間で不公平が生じないようにする。そのため、保険加入時は、お客さまから年齢・性別に加えて、現在の健康状態の告知をしてもらうことや、場合によっては医師の診査を受けてもらうこともある。
しかし、それらのハードルを越えて加入したお客さまの間でも、多少なりとも健康状態の差があることは避けられない。リスクの高いお客さまばかりが集中して保険に加入するケースもある。明らかにリスクの高い人たちばかりが保険に加入するならば、実績支払率は当初想定した支払率よりも悪化することになる。
一般的に保険金や給付金の請求可能性が高い人たちが集中して保険加入することは、「逆選択リスク」と呼ばれている。ただし、逆選択リスクはお客さまに悪意があるとはいえず、健康に不安のある人ほど保険へ加入しやすいというお客さま心理に根差した問題である。
一方、似たような用語で「モラルリスク」と呼ばれるものがある。これは、保険金や給付金を不正に請求するなど、保険制度を悪用しようとする試みである。例えば、既に病気に罹患(りかん)しているにもかかわらず、その事実を隠して保険に加入し、すぐに保険金や給付金を請求することなどを指す。
保険は万が一の事故が起こった際に、支払った保険料に比して、多額の保険金や給付金を受け取ることが可能な類いの金融商品であるため、昔から保険金詐欺などのモラルリスクが生じやすい傾向にある。
例えば、多くのがん保険で、加入時に待ち期間が90日あるのは、これを防ぐための仕組みだ。モラルリスクは保険事業の根幹である保険の公平性を根幹から覆すものであるため、保険会社は保険加入時や保険金請求時に、慎重な確認や調査を行って不正を防止する必要がある。
実は、このモラルリスクが、近年急激に高まっている。いったい、その理由は何なのか。次ページで徹底解説していこう。