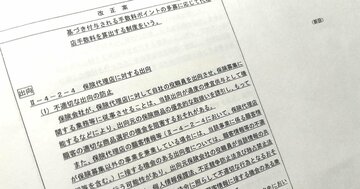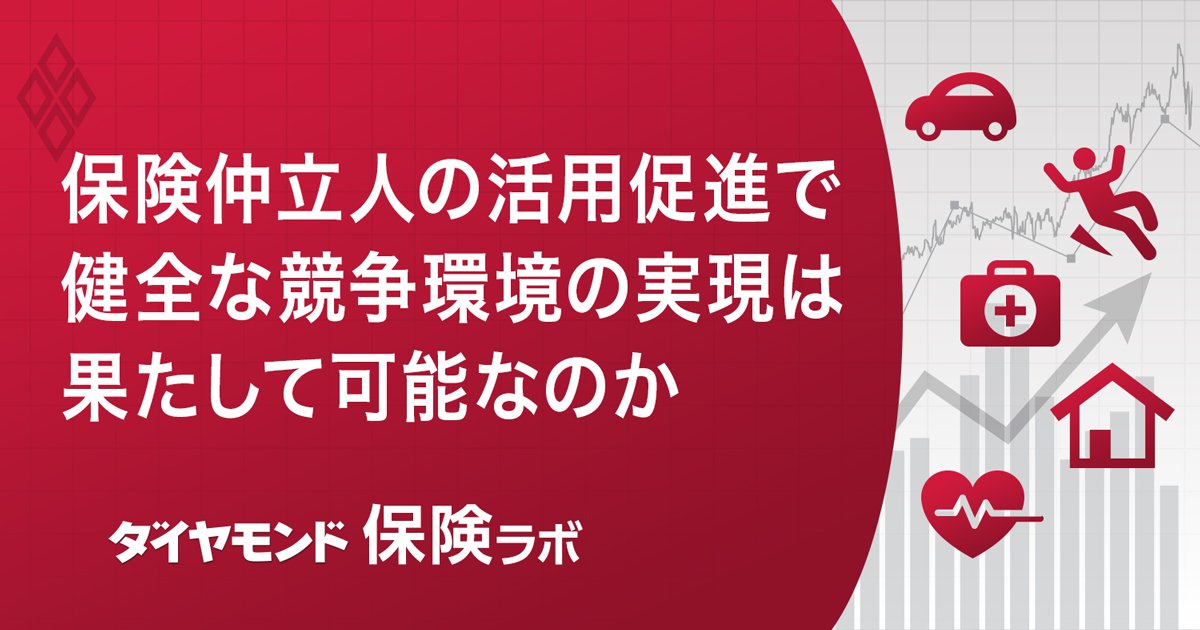
損害保険業界で起こった一連の不祥事を契機として、企業保険分野において保険仲立人(保険ブローカー)の活用促進に向けた対応を行うべきだと金融審議会で提唱された。だが、果たして保険仲立人の実態はどうなのか。そこで連載『ダイヤモンド保険ラボ』の本稿では、五つの観点から検証する。(元金融庁監督局特別検査官 成島康宏)
金融審議会の報告書で提唱された
保険仲立人の活用促進
2024(令和6)年12月25日に公開された金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書(以下、「報告書」)では、保険仲立人(保険ブローカー)の活用促進に向けた対応を行うべきだとされた。
損保業界では、企業向けの保険契約において、大手損保4社が事前に保険料を調整するというカルテル問題が発覚したが、保険会社から独立した立場で顧客の代理人として最適な保険商品を提案する保険仲立人が活躍すれば、健全な競争環境が実現すると期待されるためだ。
その点について報告書では、以下のように述べられている。
『保険仲立人は、保険契約の締結の媒介業務だけでなく、総合的なリスクマネジメント業務も併せて提供しており、企業向け保険市場を主な活動領域としているものの、保険仲立人の活用が進んでいないと考えられる。
保険仲立人の活用は、販売チャネルをより多様化させ、販売面での競争をより促し、わが国の保険市場の健全な競争環境の実現につながるものと考えられることから、その活用促進に向けた対応を行うべきである。併せて、保険仲立人の認知が企業の中で広がること、さらには保険仲立人を十分活用できるよう企業側がリスクマネジメント体制及び能力を向上させていくことも重要となる』
また、保険仲立人を活用するための方策としては、以下のようなポイントが示されている。
■企業向け保険について、保険仲立人が顧客からも手数料を受領できるよう見直す。
■保険仲立人に義務付けられる供託金の最低金額を引き下げる(2000万円→1000万円)。
■保険契約者の誤認防止措置を前提として、保険仲立人と保険代理店等の協業を認める。
■当局による個別審査の上で許可を受けて、企業等が外国保険業者と保険契約を締結する場合、保険仲立人による当該契約締結の媒介を可能とする。
■保険仲立人が不祥事件を起こした場合、当局にその旨を届け出る義務を課す。
このように報告書では保険仲立人を活用することで、健全な競争環境が実現するとされているが、果たしてそうなのか。次ページでは、五つの観点から保険仲立人の実態を考察する。