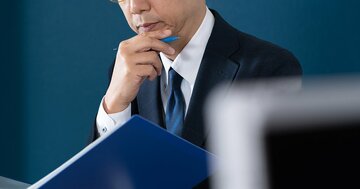「それでは例題を解いていきましょう。養老保険の『新フリープラン』を、62歳の男性に販売しました。保険金額は1000万円、満期は10年、医療特約が付きます。かんぽ未契約の純新規のお客さまで、支払い保険料は毎月10万8000円です」
われわれは「計算式」が書かれたペーパーを見ながら、教官の出す例題の数字を手元の電卓で叩いていく。なんだかそろばん教室にでも通っている気分だ。支払い保険料がやけに高額な設定なのは、研修生のやる気を喚起するためか。
「はい、それじゃあ、半沢さん、この場合のボテはいくらですか?」
「5万4915円です」
「はい、正解! ところで、今、半沢さんに答えてもらったのは契約の翌月に付く歩合給です。そのほかに、6月と12月のボーナス月にもこの契約から歩合が支給されます。この計算は少々面倒なので私が答えを言ってしまいますが、今のケースだとボテは1万9613円になります。よって、5万4915+1万9613=7万4528円がこの契約によってみなさんが受け取ることができるボテになります」
教官は最後の「7万4528円」をひと際強調してそう解説した。
最初は手間取っていたが、何度も繰り返し問題を解いていくうちにスピーディーに計算できるようになっていった。人間、何事も慣れが大切なのだ。
研修で具体的な商品内容について
教えられる機会はほとんどなかった
このようにボテ計算については、何度も懇切丁寧な授業が行なわれたのに対し、研修で具体的な商品内容について教えられる機会はほとんどなかった。
たとえば、かんぽ生命を代表する「終身保険」という商品がある。生涯にわたる保障を特徴とする生命保険で、死亡または重度の障害を負った際などに受取人に対して保険金が給付される。また、掛け捨てではないため、途中で解約すれば解約返戻金がある。
これはメジャーな内容で、かんぽ生命以外のほとんどの保険会社でも同種の商品が販売されている。競合する商品が多いわけで、営業マンであれば、自社商品と他社商品を比較し、どの点が優れているか(逆にどの点が劣っているか)を把握したうえでお客にアプローチする。会社によっては、デザイン性に富んだ「各社との比較一覧表」などを作成し、営業マンがそのポイントを熟知したうえで、お客に自社商品の素晴らしさを説明する。これが金融商品セールスの王道だろう。