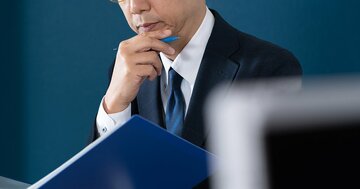写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
かんぽ生命の不適切営業問題が表面化したことで、それまで多くの人が抱いてきた「身近で親切、信頼できる」というイメージは地に落ちた。2017年春、私は郵便局に入社し、かんぽ生命の苛烈なノルマに追われながら仕事に勤しんでいた。私はかんぽ営業の現場で何を見て、何を考え、なぜ退職を決断したのか。これから記すのは、すべて実体験したありのままの事実である。私は東海地方のY郵便局に配属されると、すぐに東京の中央郵政研修センターに向かった。4週間にわたる研修で目の当たりにした光景は衝撃の連続だった。
※この記事は、半沢直助『かんぽ生命びくびく日記』(三五館シンシャ)の一部を抜粋・編集したものです。登場する人物・団体名は仮名です。
某月某日 ボテ計算
研修で教わらなかったこと
研修は「いかに稼ぐか」に主眼が置かれていた。そのひとつが「ボテ計算」の授業である。この授業で初めて、Y郵便局で局長から言われた「ボテ」の意味を知った。「ボテ」とは「募集手当」の略なのだ。
郵便局、とくに金融渉外部の給与は「基本給」+「各種手当」+「ボテ」で構成される。基本給は低く、大学卒40代の私でも20万円を切る水準だ。そこに、扶養手当、住居手当、超過勤務手当(残業代*)、祝日給(休日出勤手当)、通勤手当(さらに北海道などでは「寒冷地手当」などがある)がつくことで、20万円台半ばから後半の水準となる。さらに歩合給である「ボテ」が乗って、それなりに見栄えのよい額になるわけだ。
郵便局の扱う商品は多様だ。
(1)一生涯の死亡リスクに備える「終身保険*」
(2)一定期間の死亡リスクに備える「養老保険*」(満期返戻金あり)
(3)一定期間の死亡リスクに備える「定期保険」(掛け捨てで満期返戻金なし)
(4)子どもの教育資金を計画的に積み立てる「学資保険」
(5)アフラックの「がん保険」
(6)東京海上の「自動車保険」
ほかにも、「投資信託」や「通常貯金から定額貯金への切り替え」「年金口座の獲得」「カタログギフトの販売」などもあり、それらすべてにボテがつく。
ボテの計算方法は非常に複雑で、生命保険であれば、被保険者の年齢、死亡保険金額、保険料の払い込み期間や金額、特約の有無、さらに取扱者(局員)の役職などに応じて変わってくる。まったく同じ内容の商品を成約できても、課長とヒラではもらえるボテが異なるのだ(上位役職者のほうが、ボテが大きい)。
研修生のモチベーションを上げるべく、授業ではさまざまな状況におけるボテ計算を実演*させられる。がんばればこれくらいもらえますよ、というわけだ。教官が出題する。