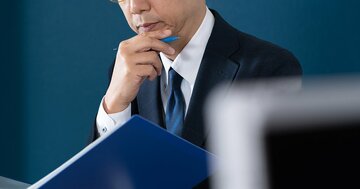写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
かんぽ生命の不適切営業問題が表面化したことで、それまで多くの人が抱いてきた「身近で親切、信頼できる」というイメージは地に落ちた。2017年春、私は郵便局に入社し、かんぽ生命の苛烈なノルマに追われながら仕事に勤しんでいた。私はかんぽ営業の現場で何を見て、何を考え、なぜ退職を決断したのか。
※この記事は、半沢直助『かんぽ生命びくびく日記』(三五館シンシャ)の一部を抜粋・編集したものです。登場する人物・団体名は仮名です。
某月某日 金融のプロとは?
私が考えるプロフェッショナル
私はかんぽ生命の営業マンは“金融のプロ”であってほしいと考えている。また、郵便局でならそんな仕事ができるかもという期待とともに入社した。
私が思い描くかんぽ生命の営業マンとは、お客のライフプランアドバイザーとして最適な金融商品を提案するプロフェッショナルだ。
巷にはファイナンシャルプランナーがあふれている。前職の乗合保険代理店時代に実感したことだが、彼らは真のプロフェッショナルとは言えない。
というのは、彼らはたいてい特定の保険会社の商品を契約させると大きなキックバックが入るというシステムの中で動いているからだ。どうしても顧客よりも手数料収入を優先するようになる。
これに対し、私が考える真のプロフェッショナルは、お客の状況によってはあえて何も売らない提案をすることができる人だ。銀行時代、尊敬する上司から言われた言葉をいまも鮮明に覚えている。
「半沢君、俺たちは懸命に融資を伸ばしていかねばならんけれど、あえて貸さないという決断をすることも仕事のうちだぞ」
融資額を伸ばすことだけに一心不乱になっていた私にとって目からうろこだった。その上司は、自らのノルマを果たすためだけに融資することで最終的にその企業がさらに苦しんだり、たとえば連帯保証人の社長が自殺*するようなことになるくらいなら、あるところで融資を打ち切る判断をするのも銀行員の務めだと言ったのだ。
保険営業にも同じことが言える。この業界には「保険貧乏」という言葉がある。営業マンに言われるがまま保険に加入し、契約を抱えすぎて生活が苦しくなることだ。支払う保険料も月々は少額でも永続的に払い続けるとなると生活に影響を与える。生活を切り詰めて保険料を支払うようなことになれば、本末転倒なのだ。そんなとき、「保険に入らない」という選択肢を勧められる、それが金融のプロなのではないだろうか。
また、私は前職まで金融商品を扱っていたこともあり、郵便局の商品内容についても把握していた。言い換えれば、その「弱さ」を知っていたのだ。