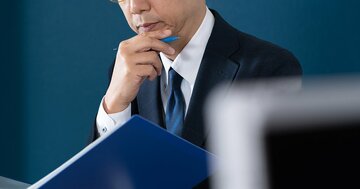郵便局が売っていた
2つの“ダメ商品”とは
たとえば、郵便局の「学資保険」に「はじめのかんぽ」という商品がある。
これは子どもの教育資金準備と、契約者(親)が万一のときの保障を兼ねた内容で、被保険者(子ども)の「17歳・18歳満期型」や、「21歳満期型」など、複数のプランから選べ、大学進学などのタイミングで学資金が受け取れる、というのが売りだ。
ところが、この学資保険の返戻率(最終的に戻ってくるお金)はどんなによくても100%を下回る“ダメ商品”に成り下がっていた(なお、他社の商品の中にはまだ110%近くまで伸びるものも存在した)。これならふつうに貯金していたほうがいい。
ほかにも、完全な掛け捨ての死亡保障である「定期保険」は、他社の商品にくらべて、保障内容が同じでも、保険料は大幅に高いという“ダメ商品・その2”であった。
つまり、私にとって郵便局の金融商品は決して売りやすいものではなかった。
だから、研修ではこうした問題をクリアするアプローチ法などを教えてくれるのではないかという期待を抱いていた。あるいは顧客に寄り添う郵便局ならではの仕事のやり方があるのではないか。しかし、そんなものはどこにも存在しなかった。
研修で重視されたのは、ボテを正確に計算する方法であり、「郵便局の看板」で信頼感を得ながら高齢者を中心とする郵便局ファンに商品を売る方法だった。そこに「お客のためを考えて、あえて売らない」という選択肢など存在しない。
同部屋の3人*も真面目に授業を受けていた。しかし、いくらきちんと研修を受けたところで、これから自分たちが売る各商品のメリット・デメリットを理解できる人*はおそらく1割もいないだろう。まして金融のプロなど養成できるはずもない。
同部屋の仲間たちと郵便局の営業方法やかんぽの商品性について話をしたことはない。彼らにそんなことを伝えれば、これからの活動に不安を与えるだけだ。何より、私自身もその事実を直視することが怖かったのだ。