しかし、何度か働きかけをしても改善されず、さらに予想外のトラブルが重なると、上司としても対応に悩みを深めるようになります。
Mさんが短期間で何度も異動している背景には、もしかすると、現場が対応に苦慮し、状況の打開策として業務内容などの環境を変更するために異動という方法をとってきたということも考えられます。
ただ、本来であれば、「異動」という一時的な対応にとどまらず、Mさんの特性を理解したうえで、どのようにマネジメントしていくかを考えることが重要です。
仕事がやりやすくなる方法を
話し合いで模索しよう
では、上司が「もしかしたら発達特性があるのかもしれない」と気づいた場合、その後どのような対応が求められるのでしょうか。
管理職向けの研修などでよく寄せられる質問には、「どうすれば本人に自覚してもらえるか」「どうしたら受診してもらえるか」といったものがあります。
こうした問いの背景には、「本人が自分の特性に気づけば、行動の調整ができるのではないか」といった期待があるのかもしれません。そして、「行動を変えてほしい」「そのために診断を受けてほしい」と考えるのでしょう。
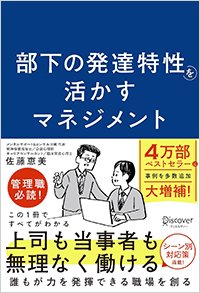 『部下の発達特性を活かすマネジメント』(佐藤恵美、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『部下の発達特性を活かすマネジメント』(佐藤恵美、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
しかし、発達特性のある人に対する適切なマネジメントとは、周囲に合わせて行動を無理に変えさせることではありません。それは、たとえば絶対音感のない人が「自分には絶対音感がない」と気づいたとしても、それによって絶対音感が身につくわけではないのと同じです。
しかし、絶対音感がなくても演奏の仕方や練習方法を工夫することによって音楽を楽しむことができるように、特性に合った方法を工夫することで力を発揮できるようにすることは可能です。
したがって重要なのは、「自覚しているかどうか」よりも、上司と本人が共にその特性を理解し、「どのようにすれば仕事がしやすくなるか」「どう工夫すれば成果に近づけるか」といった視点で、業務の進め方や支援の方法を話し合うことです。







