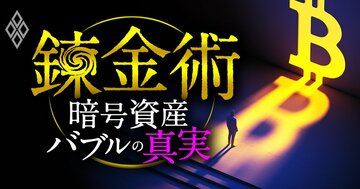外国人労働者というと最近の日本が直面している問題だと誤解している人も多いが、実は100年以上前から続けられている日本の「悪癖」である。歴史を振り返ると、日本人にとって外国人労働者というのは、前澤氏の指摘通り「奴隷的」なもので、なおかつ「自分たちの努力や工夫」の足を引っ張ってきたことがわかる。
1917年(大正6年)、北海道や九州の炭鉱で深刻な人手不足が発生した。若者が都市部でのホワイトカラー的な仕事を望むのは今も昔も変わらない。命の危険や怪我のリスクの高い炭鉱内の肉体労働者は敬遠されていたのだ。
こうなると「だったら、日本人以外の労働者を呼び寄せてやらせりゃいいじゃん」という発想になるのは、大日本帝国の政治家も令和日本の政治家も変わらない。なぜかというと「安い給料で文句言わずに働く労働力が確保できないと会社が潰れてしまう」と訴える産業界から献金を頂戴して、選挙応援をしてもらうのが政治家だからだ。
かくして2018年の安倍政権と同じくサクッと「外国人労働者の受け入れ拡大」が決まる。政府は「試験的」という名目で、三菱、三井などの炭鉱に朝鮮人労働者約700名の受け入れを決定すると、これをきっかけに外国人労働者をどんどん日本に入れていくのだ。
もちろん、100年前の日本人はわりとまともな人が多かったので、前澤氏のような「日本人だけで効率よく豊かな国を目指せ」という意見も少なくなかった。「読売新聞」(1917年9月14日)の「労力の輸入 最後の計算を誤る勿れ」という記事が以下のように警鐘を鳴らしている。
「鮮人労働者の輸入は生産費の軽減を意味し随(したが)って生産品の低廉を意味するが如きも事質に於ては只内地労働者のエキスペンスに於て資本家の懐中を肥やすに過ぎざるなり」
「要するに鮮人労働者を内地に輸入するは我内地の生活を朝鮮の生活と同一の水準に低下せしむるとなしとせず」
産業が安価な外国人労働者に依存するようになると、そこで儲かるのは経営者だけで、多くの日本人は外国人労働者と同じくらいの低賃金に据え置かれてしまうというワケだ。