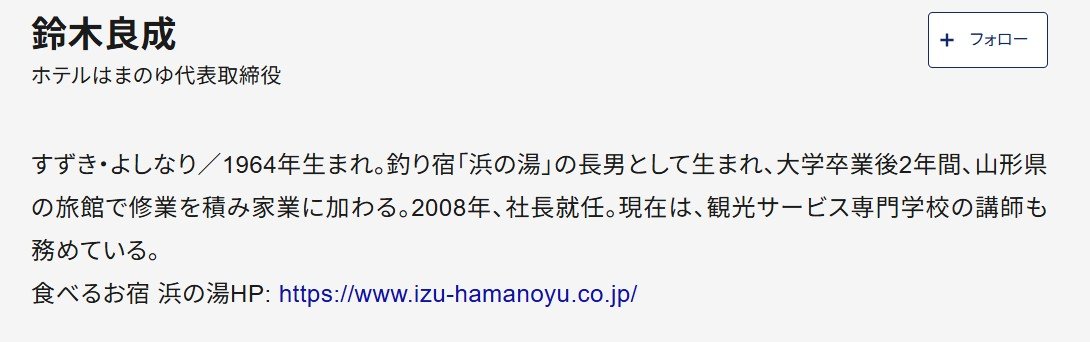リスクを見誤る「インバウンド偏重」
箱根など有名観光地では、インバウンド客が9割を超える宿もあるそうです。売り上げは増えるかもしれませんが、世界情勢次第で一気にゼロになるリスクもあります。コロナ禍でそれを痛感したはずです。日本人リピーターをないがしろにした旅館経営は、決して安定しません。
当館では、最後のお見送りの際にお客さまが仲居に駆け寄り、涙を流しながらお礼を言ってくださることがあります。料理、施設、接客――どれかひとつでも欠ければ、このような感動は生まれません。お客さまが「ありがとう」と心から伝えたくなる宿こそ、本物の旅館です。
こうした光景をもう一度、全国の温泉地で取り戻したい。実際、当館に宿泊された旅館オーナーが、のちにご自身の宿で仲居の担当制と料理の部屋出しを復活させ、大繁盛している例もあります。つまり、経営者の覚悟次第で旅館文化は再生できるのです。
若い人に旅館文化を継承しよう
お客さまの中には、「仲居にチップを渡さなければいけないのでは」と心配される方もいます。しかし、そんな決まりはありません。当館でも、渡す方もいれば渡さない方もいます。渡さない方も、定宿にしてくださる例はたくさんあります。
泊食分離が進めば、日本の若い人たちが旅館文化を体験することのないまま、この文化が廃れていくでしょう。令和の今こそ、日本の伝統を守り、次世代につなげるべきではないでしょうか。
旅館に宿まる際は、主人や女将に「どんな思いでこの宿を続けているのか」と尋ねてみてください。サービスを受けるだけではなく、コミュニケーションを取ることで、その旅館の真価を知ることができるでしょう。
表面的な贅沢ではない、心を豊かにする宿泊体験を提供する――これが、日本の旅館の存在意義だと私は思います。