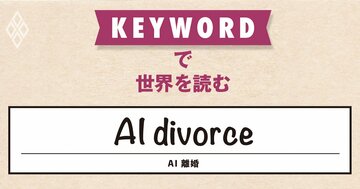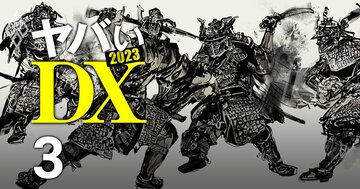Photo by Masato Kato
Photo by Masato Kato
米OpenAIの初期からの出資社である米マイクロソフト。オラクル、エヌビディア、AWS(アマゾン ウェブ サービス)などがその後次々と同社への出資や計算リソース契約を行う中、AIエージェント市場でどのように競合他社と差別化戦略をとるのか。特集『DX2025 エージェントAIが来る』(全22回)の#18では、日本マイクロソフトでのAI事業のトップである岡嵜禎執行役員 常務 クラウド&AIソリューション事業本部長に戦略を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 鈴木洋子)
企業にデファクトで普及しているマイクロソフトの
アプリケーションやサービスがAIと連携する圧倒的な強み
――マイクロソフトのAIエージェント事業の特徴や強みは何ですか。
Teams、Office、SharePointなど、ビジネスユーザーに広く普及し使われているアプリケーションや、開発者向けのプラットフォームとしては同様にデファクトスタンダードのGitHub CopilotにAI機能を搭載しているところです。
また、お客さまが自分たちの業務に合ったAIエージェントを作りたい、自社開発のアプリケーションにAI機能を組み込みたいというニーズに対して、自社クラウドサービスのマイクロソフトAzure上でAIモデル、データベース、検索サービスなど、一連のサービスとして必要なコンポーネントをそろえて提供しています。
大きな特徴は、お客さまがニーズに応じて自由に選択可能なAIモデルを1万1000種類以上用意していることですね。提携しているOpenAIと、Meta、Grokなどの主要なモデルに加え、マイクロソフト独自のAIモデルであるPhiも提供しています。
また、AIエージェントを利用する際には、人と同様に、権限に応じてどの情報とシステムにアクセスできるかをコントロールする必要があります。Microsoft 365(M365)などでも使われ企業に広く普及している認証基盤「Entra ID」では、ログイン管理とセキュリティーを一体化し、異常検知からアクセス制御まで自動で連携する仕組みをAIエージェントのセキュリティー管理でも使うことができます。
――OpenAIに対して出資を行ったビッグテック企業はマイクロソフトが最初でしたが、その後OpenAIにはエヌビディアが出資を行うほか、クラウドサービスに関してもオラクルやAWS(アマゾン ウェブ サービス)ともクラウドリソース供給契約を結んでいます。現時点でのマイクロソフトとの関係はどうなっているのでしょうか。