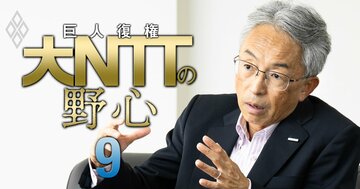Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
全国1700以上の市区町村で約3万4000のシステムが動き、予算約7000億円を投じて進む自治体ITシステム標準化プロジェクト。ここへきて昨年の富士通に続き自治体システムでシェアの高いベンダーの1社が2026年3月末までの納期に間に合わないと発表。特集『DX2025 エージェントAIが来る』(全22回)の#21では、日本のITシステムの歴史の中でも最大規模の移行プロジェクトの最新状況を追った。稼働まで半年を切る今、現状はどうなっているのか。そして26年3月何が起こるのか。(ダイヤモンド編集部 鈴木洋子)
都内自治体にも顧客が多いRKKCSが「ギブアップ」
26年3月末の移行断念を顧客に通達
「稼働に向けテストをしたものの、計算ボタンを押しても何も動かない。ベンダーに確認すると『実はまだ一部機能を作っている最中』などの回答が来た」(自治体IT職員)
全国1741の市区町村と47都道府県が、役所の中核機能をつかさどる住民記録や税など20の基幹ITシステムを2026年3月までに一斉に「標準化」する、総予算7000億円超の壮大な計画。それが自治体システム標準化プロジェクトだ。3万4000を超えるシステムを対象とし、さらにその後これらのシステムをクラウドに移行する。日本のITの歴史の中でも最大の基幹系移行プロジェクトである。
その移行現場では大混乱が起きている。前出の自治体は、大手自治体ITベンダーRKKCSの顧客。同社は10月1日、現在標準化作業を受注している全123団体のうち約半数に対し、政府が目標とする25年度末までの完了が間に合わない、と発表したのだ。
RKKCSの顧客には東京23区を含む全国の多くの自治体が並ぶ。24年には富士通と富士通Japanが約300の顧客向けに同様の通達を行っている。稼働まであと半年というタイミングでまたもや大手ベンダーの「ギブアップ」発表に、全国の自治体IT関係者は大騒ぎになった。
国はなんらかの理由で期限までに稼働できないシステムを自治体からの申請で「特定移行支援システム」として救済する制度を設けた。特定移行支援システムとなると移行の予算措置が最大5年間延長されるのだ。
25年7月の時点で特定移行支援システムの対象は全システム数の10.9%。全政令指定都市と、墨田区と千代田区を除いた21の東京特別区を含む、全都道府県・市区町村のうち36.0%がなんらかの特定移行支援システムを抱えている。
稼働まであと半年、標準化プロジェクトはどうなっているのか。ダイヤモンド編集部では、総務省が公開している各自治体のシステム移行進捗ツールであるPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)を分析した。最新のデータである9月末の数字を分析すると、上記の数字はまだまだ「底」が抜けそうな状況も見えてきた。
そもそも、どうしてこうした大混乱が起こっているのか。各自治体ごとのデータ分析と自治体の移行現場の声、そして専門家の分析と共にこの世紀の炎上プロジェクトについてじっくりと分析していこう。