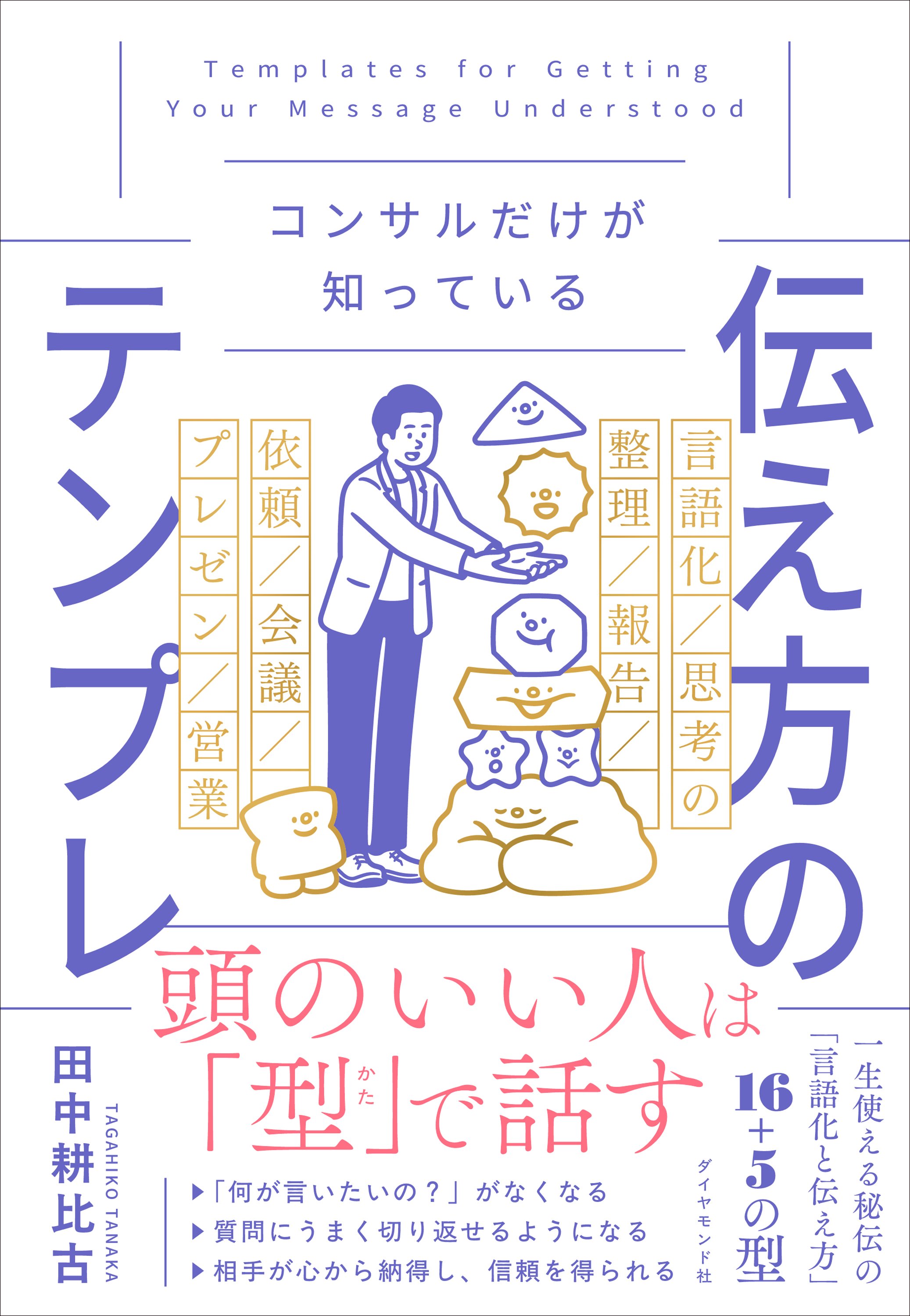仮説を提示して
相手から引き出す
こうしたアドバイスの中でも、特に大事なのが「相手の状況を把握する」という点です。
いきなり「どんな感じですか?」「どういうところにニーズがありますか?」「お困りごとはなんですか?」などのオープンクエスチョンを投げられても、多くの人は困惑してしまいます。
話を前に進めるためには、こちらから「こういうことではないか」という仮の答え、つまり、仮説を提示していくことが重要です。
既に利用中のサービスであれば、利用ログを確認した上で「最近、○○領域のご利用が増えているように見えますが、何か業務面での変更がございましたか?」のように、質問の範囲を狭めるようなアプローチも考えられます。
あるいは、完全に新規のお取引で、相手の情報が不足しているという場合には、「御社の業界のお客様のお声を聞く限りでは、○○や××などが過大だというお話がよく出てきます。御社では、そうしたことでお困りではないですか?」のように、他社事例などを引き合いに出して、相手の状況を聞いていくのが良いでしょう。
相手が話しやすいように、すなわち相手が脳内で話のとっかかりを見つけやすいように、うまく誘導していくことがポイントです。
仮説自体が当たっているかどうかは、それほど大きな問題ではありません。
仮に間違っていて、「うちは、そういう感じじゃないな」と言われたとしても、「なるほど。そのあたりは、すでに解消されているわけですね。ちなみに、どういう工夫をされてそのあたりの問題を解決されているのですか」と切り返せば、相手の業務内容を教えてもらうことにつながります。
こうして、相手の状況をうまく聞き出していくと、相手の「困りごと」「ニーズ」が少しずつ見えてきます。そうなるとしめたものです。
その課題への対処法や、ニーズに合致した解決策などを “一緒に” 考えていくことができるようになります。
若手社員にこの流れを意識させるだけで、商談は「押しつけ」から「対話」に、「セールス(販売)」から「共創」に変わっていきます。
「信頼を積む商談」ができる
若手を育てよう
商談は、勝ち負けを競う場ではなく、“お互いの信頼づくりの場”です。
マネジャーが若手に教えるべきは、トークの型ではなく、共感のつくり方です。
たとえ契約に至らなくても、相手が「また話したい」「今後も相談したい」と思ってくれれば、その商談は成功なのです。