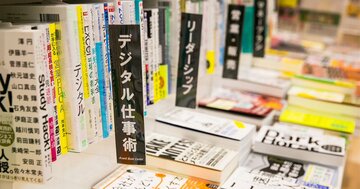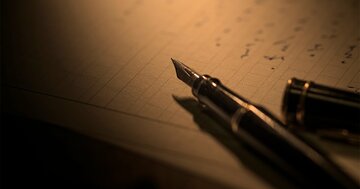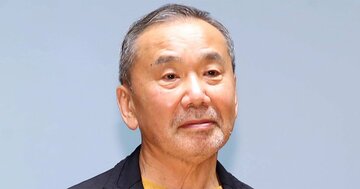「装丁は僕がやる」と
漱石みずから手を挙げた
ただし漱石はひとつ条件をつけます。
「装丁デザインは僕がします」
もちろんこんな言葉遣いではなかったでしょうが、漱石はいわゆる著者装、自装を希望します。
装丁をどうするか。
これも「制作」のなかの重要な仕事のひとつです。簡単にいえば、その本にふさわしい「装い」を決める。
皆さんも、着る服次第で、印象が大きく変わるのを経験したことがあるでしょう。デザイン、素材、形、それぞれのちょっとした違いの積み重ねで、その日のその人にピッタリな装いを身につける。同じように、その著者と、その内容にピッタリな装丁がある。
それを、デザイナーとともに見つけ、導くのも編集者の大きな役割です。
私が出版にかかわり出したときはすでに、装丁、つまりカバー、表紙などのデザインは、ブックデザイナー、装丁家に編集者が依頼することが当たり前でした。
岩波茂雄が出版業を始めたころは、分業体制がいまほど確立しておらず、画家や版画家、編集者、あるいは著者自らが装丁を手がけることもありました。漱石の作品は橋口五葉によるものが多いですね。
本に合う装いを見つける
ブックデザインという仕事
ちなみに、著者装でぱっと思いつくのは、村上春樹さんの『ノルウェイの森』でしょうか。「暮しの手帖」創刊編集長の花森安治さんは、企画、取材、校正のみならず、挿画や装丁を手がけたことでも有名です。個人的には昔の装丁のなかでは、版画家・棟方志功の河井寛次郎作品の装丁デザインがとても好きです。
いずれにせよ、岩波茂雄は、天下の漱石の本を出せるとあって、有頂天の思いで本づくりに勤しみます。最高の本をつくるのだ。この思いは茂雄のなかで疑いもなく、最高の素材でつくることに昇華します。
素材と書きましたが、書籍づくりの前提をここで説明しておきます。
書籍はひとつのモノです。モノである以上、さまざまな素材をくみあわせてつくることになります。
表紙、見返し、扉、本文用紙、スピン、花布。日本では、カバー、帯を巻くことが多いため、それらも装丁まわりといわれる素材に含まれます。
こうした用紙や素材を「仕様」と言います。
ブックデザイナーの仕事のひとつに、仕様の指定がある。その指定を受け、編集者は、印刷所や紙の業者へ用紙の見積もりをとり、その書籍にあった仕様を最終決定します。
これは、電子書籍にはない、紙の本ならではの行為ですよね。
くりかえしますが、1冊の本にはその本にふさわしい装いというものがある。それを、ピタリと見つけ、着せる。デザイナーとともにそれを実現するのも編集者の重要な仕事のひとつです。