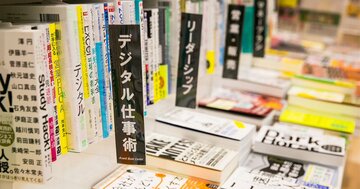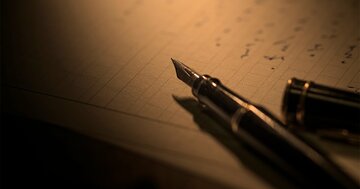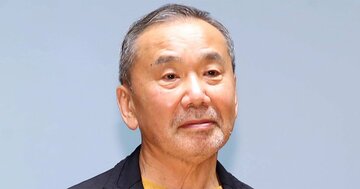高価な素材を探す茂雄に
「編集のいろは」を教えた漱石
『こころ』の場合、漱石がブックデザイナーさながらに、仕様を指定していきます。それをもとに茂雄が素材を探すわけですが、最高の本に仕上げると意気込むあまり、高価な仕様に走ります。それを見た漱石は手紙を送り、こう茂雄を諭します。
「表紙がよければ紙を落すとか、用紙がよければ箱張りをもう少し険約するとか、何とかそんな風に工面して、いい具合に本というものは作るのだ」
(中島岳志『岩波茂雄――リベラル・ナショナリストの肖像』岩波書店)
このやりとり、なかなか感慨深いものがありますよね。
のちに日本を代表する出版社となる岩波書店の創業者にたいし、編集のいろはを教えたのが、大作家・夏目漱石だった。
きっと、この2人に限らず、近代出版の礎を築くやりとりが、作家・編集者のあいだでこの時期、無数にあったにちがいありません。
編集素人だった岩波茂雄から出版社として岩波書店は始まったというのも、今からは想像しにくいですが、ひとつの出版という仕事の本質を物語っている気もします。
コストを気にすることも
商業出版の核である
ともあれ、漱石・茂雄のやりとりは、出版という仕事のある核心をついているのは間違いありません。
ひとつは、漱石がコストを気にしなさい、と言っている点。ここに、商業出版の核が宿っているといっていいでしょう。
出版社の大きな役割のひとつは本の刊行です。本を出すということ。出しつづけること。それを可能にするには、1冊の刊行を通じて、しっかりと利益を出さないといけません。むろん、利益を出すには、「原価」を抑えることが必須です。
 『出版という仕事』(三島邦弘 ちくまプリマー新書、筑摩書房)
『出版という仕事』(三島邦弘 ちくまプリマー新書、筑摩書房)
原価というのは、1冊の制作にかかるコストを指します。具体的には、印税(原稿料)、校正費、印刷・製本代、用紙代などです。これらにかかるコストを計算して、継続して出版活動をおこなうための利益を確保するのです。
出版社の利益=(卸値)─(原価)
卸値は、書店(あるいは取次)に卸すときの価格で、卸率は基本的には固定です。そのため、原価を抑えないことには、利幅は上がらない。
原価を抑える。これは、制作のひとつの肝と言って過言ではありません。
いい作品をつくること(茂雄が最高の本にしようとしたように)と、商業出版として成立させること。制作という業務は、この両立をめざしながらおこなう。
偉大な先人たちは、このことを私たちに教えてくれます。