生い立ちを聞くと、彼の父親は会計士で、母親は大学で物理学を教える教師だという。母親が幼いころから勉強を教え、3つ年の離れた姉の存在も大きかったようだ。両親は「彼が感じる『なぜ?』や好奇心を大事にしてきた。家庭では数学パズルを楽しみ、小学校の高学年になるまでに、20の段のかけ算は覚えていたね」と振り返る。
暗算の能力よりも
論理的に考える力の方が大事
ただ、電卓やコンピューターの普及で、計算自体の速さはそこまで重視されなくなった。
私が、「どれくらいの段まで暗算できるの?」と尋ねると、アルジュンさんは「暗算ができれば良いという訳ではない。論理的に考える力の方が大事です」と冷静に返された。
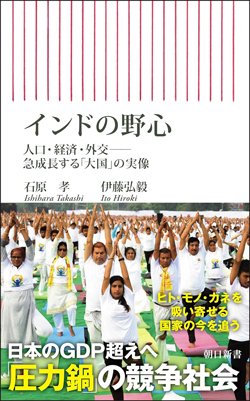 『インドの野心 人口・経済・外交――急成長する「大国」の実像』(石原 孝・伊藤弘毅、朝日新聞出版)
『インドの野心 人口・経済・外交――急成長する「大国」の実像』(石原 孝・伊藤弘毅、朝日新聞出版)
数学の魅力にのめり込んだのは、家庭環境だけが理由ではない。小学生の時にはまったのが、日本でもおなじみの数独。学校で地元の新聞を見つけると、中面に掲載された数独コーナーを解くのが好きで、友人からは「数独少年」と呼ばれた。数字に親しみを持ち、論理的な思考をするうえで役に立った。
盤上の駒をお互いに動かして争うチェス(古代インド発祥の「チャトランガ」が欧州で変化したとも言われるボードゲーム)も好きだという。
インド国内のチェス大会にも出場するほどの実力を持つ。「数学オリンピックに出場する他のインド人の多くもチェスをやっている。ひょっとしたら、数学と何か関係しているのかもしれませんね」と笑った。
勉強の合間にバドミントンをして体を動かし、インドで人気のヨガをする時間も設けている。当然のように流暢な英語も話す。
将来の進路は決めかねていると言うが、「病気の治療や人工知能(AI)、情報工学など、数学が実社会でどのように利用できるかについて興味があるんです。そういった分野を研究していきたい」と前を向いた。







