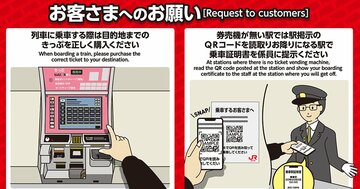なぜ長期債務残高の上限は
7.1兆円へと拡大したのか
2010年にJR東海が交通政策審議会に提出した資料「超電導リニアによる中央新幹線の実現について」は、物件費を2006年度から2010年度の5年間の実績を基本とし、20年間で累計5%上昇する前提だったが、ここ数年の上昇は想定を上回っている。
この資料で同社は、国内インフラ事業者の長期債務残高/営業キャッシュフロー(CF)比率は、一般的に10倍以下、比率が高い企業でも13~14倍が限度としている。そのため、当時の営業CF(約3800億円)の13~14倍にあたる5兆円と長期債務残高(約3.1兆円)の差額である約2兆円を限度として資金調達すると説明していた。
また、長期債務残高については、1991年度末の約5.4兆円から5000億円縮減するのに7年、1998年度末の約4.9兆円から5000億円縮減するのに3年を要した経験から、「長期債務残高が大きいと利払い負担が重いことから、元本の縮減は進まない」と指摘。残高が5兆円を超えると債務の圧縮ペースが鈍化するとした。
当時の調達金利実績は、期間10年で1.6%程度、20年で2.2%程度だったが、調達金利は固めにみて3%と想定していた。長期債務残高が5兆円に達すると金利1%の上昇で年500億円の負担増となるため、金利上昇リスクを抑えるためにも長期債務の管理が肝要と結論付けていた。
にもかかわらず、2021年の総工事費見直しで長期債務残高のピーク(開業翌年度)を6兆円、今回の見直しで7.1兆円に引き上げた。工事費は東海道新幹線などから得られる営業CFを基本として、不足分は借入金や社債で調達するとしている。
事業の前提が揺らいだようにも見えるが、一方で前提条件の変化もある。前述のように2010年の試算は営業CF約3800億円をベースとした計算だったが、これはリーマン・ショックの影響を強く受けていた時代の数字だ。
東海道新幹線の利用者数は2010年代に急増し、2018年度の営業CFは6095億円、コロナ禍の大幅な落ち込みを経て、2024年度は6245億円を記録しており、改めて「営業CF の13~14倍」を適用すると7.1兆円は同条件を満たすとも言える。また、同社は営業CFの増加により、5兆円を超えても債務削減ペースは落ちないと主張する。