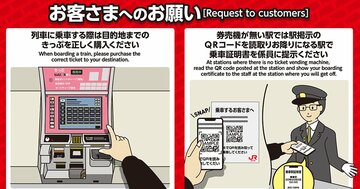リニアの工期が延びるほど
強まるJR東海の財務体質
JR東海は名古屋~大阪間について、「環境影響評価法の手続きも始まっておらず、駅位置やルートも確定していないことから、お示しすることはできない」としつつ、「名古屋までの工事の知見を活かし、健全経営と安定配当を堅持しながら早期開業に向けて全力で取り組んでいく」と語る。
だが、語幣を恐れずに言えば、JR東海は名古屋開業が遅れても困らない。工期が延びて年あたりの投資額が減れば、補って余りある営業CFで財務体質は改善する。そもそも、リニア計画とは営業利益率約40%という莫大な利益に対し、株主や利用者の増配、値下げ圧力に応えるか、東名阪のネットワーク強化に投資するかの選択である。キャッシュが回り、現状レベルの配当を継続できるのであれば、十分なのだ。
11兆円の投資をリニア単独の営業収入で回収できるわけがない。山田佳臣社長(当時)の「リニアは絶対ペイしない」発言はリニア懐疑論でたびたび持ち出されるが、同社にとって東海道新幹線とリニアは、建前や詭弁ではなく、一体的なネットワークであり単独の収支など見ていない。これは今も変わらぬ本音だろう。
今回の発表をめぐっては、丹羽俊介社長が運賃・料金値上げの可能性について言及したことから、リニアの工事費増額分を賄うための値上げという解釈を見かけた。
だが、現状の総括原価方式では、鉄道事業の利益を食いつぶし、「赤字」にならない限り運賃改定は認められない。それでは必要な投資が継続できないため、インフレに機動的に対応できる制度の導入を求めるもので、リニアの工事費増額とは関係なく、従前からJR各社と歩調を合わせて要望していた事項だ。
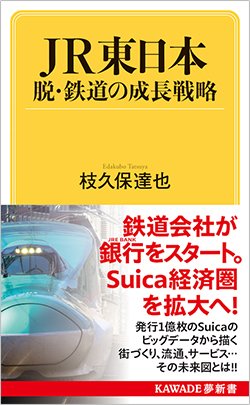 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
現行制度で運賃改定が認可されたJR東日本はともかく、6000億円以上の経常利益を計上するJR東海の主張がどこまで認められるべきかについては、議論が分かれるだろう。ただ、インフレの影響はリニアの総工事費だけでなく、運賃・料金にも反映すべきとの意味では、リニアと全く無関係ではないだろう。
やはり本質は大阪延伸の実現性である。前述の北陸新幹線新大阪延伸では、大深度に設置予定の新大阪駅の工期を概ね25年程度と試算している。リニアも同様に新大阪駅を設置するならば、今すぐ着工しても開業は2050年だ。
名古屋開業で品川~名古屋間は90分から40分に短縮され、名古屋~新大阪の約50分と合わせれば、乗り換え時間10分と仮定して、品川~新大阪間は1時間40分程度に短縮される。確かに効果は小さくないが、品川~新大阪間を乗り換えなく67分で結ばれなければ存在意義は半減する。
南アルプストンネル問題では、リニア開業後の「ひかり」増発をメリットとして提示しているが、これは大阪開業後の話である。「東名阪の直行輸送需要が本格的にシフトするのは大阪開業後である」とJR東海も国土交通省も認めているのだ。
地方の鉄道需要は急速に縮小しているが、東名阪の需要は当面の間、増えないまでも大きく減少することもないだろう。だが、2050年ともなれば日本の人口は1億人を切る可能性が高く、旅客需要の前提も大きく変わってくる。財政投融資を受けた以上、JR東海は早期に展望を示す必要がある。