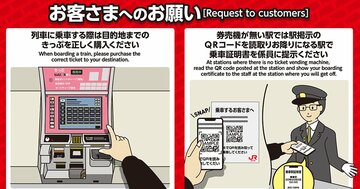全線開業の前倒しのために
踏み切った財投の活用
もうひとつの変化は財政投融資からの借り入れだ。リニア計画は国の援助を受けず「自己負担でプロジェクトを完遂」するとしていたが、全線開業を最大8年前倒しするため、財政投融資を活用した3兆円の長期借入を2016年から2017年にかけて、6回に分けていった。
調達金利は0.6~1%で全期間固定、返済は30年間(2046年まで)の元本据え置きで、以降は10年間の元金均等返済としている。これは2027年に品川~名古屋が開業し、2037年頃に全線開業を果たした後、経営安定後に返済を開始する前提だった。
リニア関連投資は現在、財投資金(中央新幹線建設資金管理信託)から充当しており、2024年度までの累計額は約2兆円で、3兆円を超えた段階で新規借り入れを開始する。同社は2010年試算では想定していなかった長期・固定・低利の融資が実現したことで、経営リスクは大幅に軽減されたと説明する。
日銀は2024年3月にマイナス金利を解除し、17年ぶりに政策金利を引き上げると決定した。2021年までマイナスまたは0%台だった10年国債の年利回りは、2023年5月に1%、今年3月に1.5%を超えた。直近では1.68%程度の水準で推移しており、JR東海にとっては絶妙なタイミングで融資を引き出した形だ。
膨大な資金と長期の建設期間を必要とする鉄道事業には、これまでも長期・固定・低利の財政投融資が充てられてきたが、一事業者に3兆円もの融資がなされるのは前例がない。JR東海は財投も有利子の負債であり、自己負担の方針は変わらないと主張するが、結果的に故・葛西敬之名誉会長と安倍晋三首相(当時)の蜜月が実現した「国策融資」なくして事業が成り立たなかったのは事実だろう。
問題は財投の目的だった「全線開業の最大8年前倒し」が果たされるかである。当初、全線の総工事費は約9兆円程度と見込んでおり、つまり、名古屋~大阪間は差し引き3.5兆円だった。北陸新幹線敦賀~新大阪間約140キロの総工事費は2024年に最大5.3兆円と試算されており、同距離で大部分がトンネルになるとみられる名古屋~大阪間がこれを上回るのは確実だ。
物価や金利が今後さらに上昇した場合、7兆円の債務を抱えた同社がこれを負担するのは難しいだろう。だが、再びの財投は期待できない。回避するはずの「経営体力回復期間」が必要になると、全線開業は見通せない。