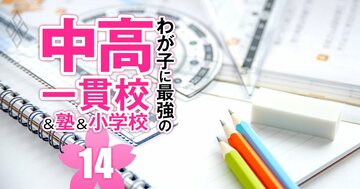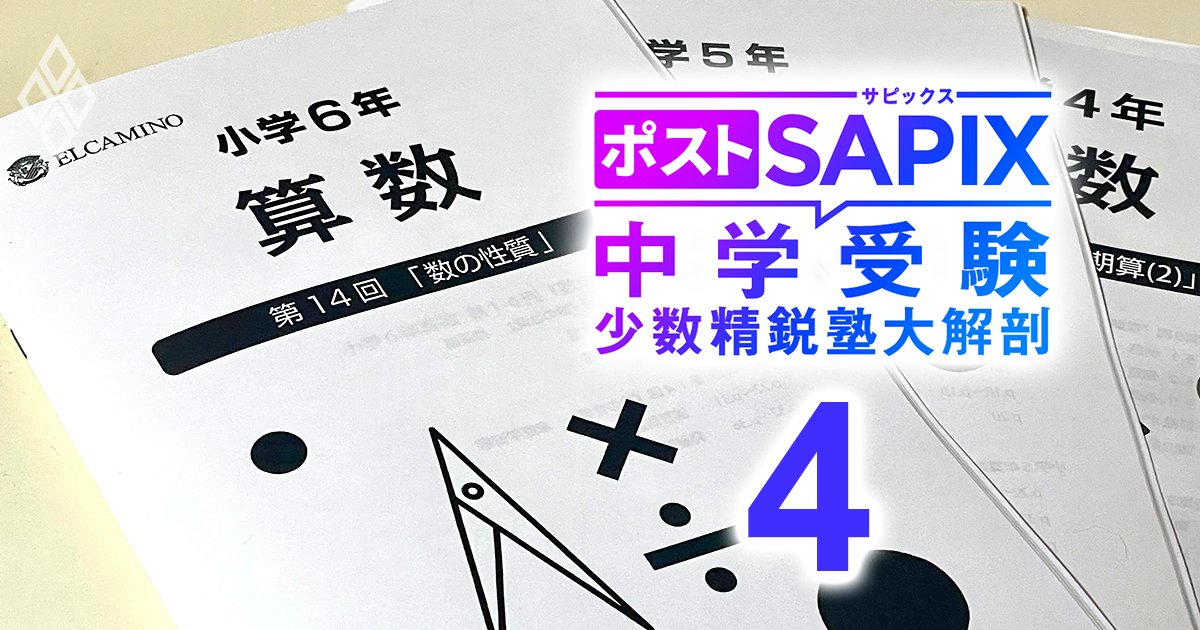 Photo by Toshimasa Ota
Photo by Toshimasa Ota
首都圏における中学受験塾の王者、SAPIX(サピックス)の凋落がささやかれる今、難関校志向を売りとする「少数精鋭型」の中学受験塾の人気が高まっている。知られざる少数精鋭塾の神髄を各塾のキーパーソンへの忖度なしのインタビューで明らかにする連載『ポストSAPIX 中学受験の少数精鋭塾大解剖』#4では、御三家など最難関校への合格率でSAPIXを凌駕すると言われ、ハイレベルの算数教育で高い支持を集める「エルカミノ」の幹部と対談。その前・中・後編のうち中編をお届けする。(教育ジャーナリスト おおたとしまさ)
寓話「ウサギとカメ」における
ウサギがぶっちぎりで勝利するための塾
おおたとしまさ いままでの首都圏の中学受験の形をつくってきたメインプレーヤーとして、もともと四谷大塚があり、1980年代に日能研が神奈川から東京に進出し、昭和と平成の端境にサピックスが出来て、いまは中学受験専門ではない早稲田アカデミーが台頭してきているという流れがあると思います。これらの塾を、それぞれどう分析していますか。
古庄歩エルカミノ副代表・理科総合責任者 四大塾さん、それぞれが独自の強みと意義を持たれていて、中学受験文化を引っ張ってこられたことに関しては敬意を持っていますし、純粋にすごいと思います。ですので、四大塾がこういう塾であるというのは、私の口からは恐ろしくて言えません。
ただ、自分たちにもやれることはあるんじゃないかと思っています。中学受験も多様化しているので、新しいニーズが生まれているのは間違いない。私たちは、そこにこそ自分たちの立ち位置があるのではないかと考えています。
おおた 多様化して、新しいニーズ、つまり大手では拾いきれないニッチが生まれてくるわけですよね。エルカミノさんが「ここだ」と狙いを定めている新たなニーズとはどういうところでしょうか。
古庄 ウサギとカメのたとえ話で、もしウサギに適切な指導者がいたら、そのままぶっちぎって勝っていただろうと。放っておくと怠けてしまうような、まだ能力を出し切っていない「ウサギ」の子たちの能力を正しく引き出す、というのが私たちのスタンスです。代表の村上(綾一氏)が個人塾のような形でいろいろな生徒を見てきた中で「この子の能力は出し切れていないな、もったいないな」と思うことが多々あったからです。
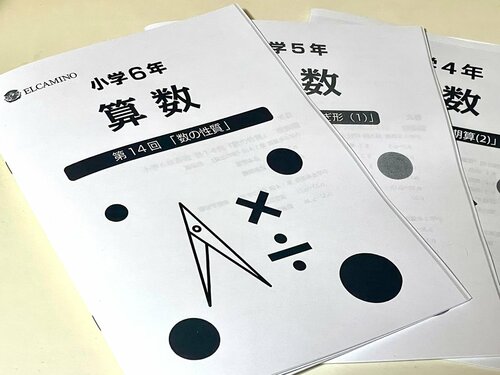 算数教育の強さで知られるエルカミノのノウハウが詰まったテキスト Photo by T.O.
算数教育の強さで知られるエルカミノのノウハウが詰まったテキスト Photo by T.O.
(エルカミノの)「筑駒算数講座」で本当に難易度の高い問題を扱っているのも、そこに理由があります。ぶっちぎりでできる才能のあるお子さんには、もっとレベルの高いものを与えてあげるべきだろうということで、「算数オリンピック」の指導も始めました。そういう子たちが「難しい、でも頑張って解けたら楽しい」と思えるようなものを与えてあげたい。
おおた なるほど。筑駒(筑波大学附属駒場)をそれだけ象徴的に置いている理由は?