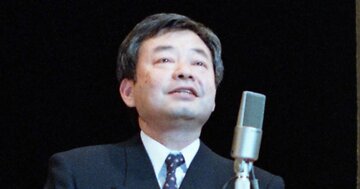女形を演じるために
己を「からっぽ」にできているか?
「からっぽ」というたとえは、『国宝』では次のような文脈でも用いられている。
 『吉田修一と『国宝』の世界』(酒井信、朝日新聞出版)
『吉田修一と『国宝』の世界』(酒井信、朝日新聞出版)
「……あの喜久雄さんってのはね、言ってみりゃ、いい意味でも悪い意味でも、本人が文楽の人形みたいな人ですからね。ある意味、このお役には打ってつけなんですよ。でもね、ずっと綺麗な顔のままってのは悲劇ですよ。考えてごらんなさいな、晴れやかな舞台が終わって薄暗い物置の隅に投げ置かれたって、綺麗な顔のまんまなんですからね。なんでも笑い飛ばせばいいって今の世のなかで、そりゃ、ますます悲劇でしょうよ」(同前)
「本人が文楽の人形」というたとえは、「本朝廿四孝」の八重垣姫をはじめ、文楽の人形振りが求められる「阿古屋」が『国宝』の最後で描かれていることを考えても、この小説で描かれる喜久雄に対するたとえとして最も的確なものと言えるだろう。
小説で「からっぽ」の人間存在を描き、そこに凄みと言えるものを見出す手法は、川端康成など近代日本の文学に通じる。また存在の根拠となる場所を無としてとらえる、西田幾多郎など京都学派の哲学者の思想にも共通するものである。
「自分はちゃんとからっぽになれているだろうか」という喜久雄の女形の歌舞伎役者らしいつぶやきは、近代日本の文学や思想にとって正統的な問いであり、「自分からは動けない」人物たちを繰り返し描いてきた吉田が、自分自身に向けた問いでもある。
そして、この「からっぽ」という内面を欠いた存在の極の1つが、女形という登場人物の造形に体現されているのだろう。