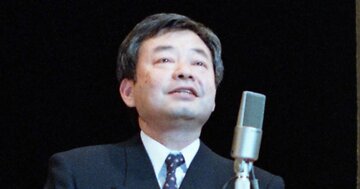中野は戦前にプロレタリア文学運動に関わり、共産党に入党した後、検挙されて転向し、戦後になって共産党に再入党、参議院議員として当選した作家である。彼は「五勺の酒」で人間天皇の人権を「実践道徳の問題」であると考えている。
操り人形となり演技に殉じる
喜久雄と平成天皇の姿が重なる
吉田修一が『国宝』の終盤で描く立花喜久雄の存在は、中野重治が言う「個を純粋に犠牲にした」天皇の姿に近付いている。喜久雄は「からっぽ」(編集部注/二代目・花井半二郎が、女形として舞台に立ち始めたばかりの喜久雄を、高く評価したときのセリフ。文楽の人形のように個を消しているため、役には打ってつけだという意)の存在となって、喜々として舞台に立ち続けているが、傍目からは、客席を埋めるために、周囲の人間たちが「ぐったりとした人形の紐を寄ってたかって繰っている惨い様子」のようにも見える。
興行会社「三友」の竹野に言わせれば、このような喜久雄の姿は、「錦鯉を小さな水槽で飼っているようなもの」である。吉田の『国宝』の終盤で描かれる喜久雄は、「出してくれ、出してくれ」と、尾を叩きつけて暴れていたのに、「誰もが気づかぬふりをして、放っておかれた」ような状態にある。
竹野は喜久雄と長年親交を結んできたこともあり、喜久雄が女形として芸にのめり込んでいく姿を気遣ったのである。これは中野重治が批判的に表現した「天皇で窒息している彼の個」のニュアンスに近い。
ただ、その一方で喜久雄は嫌々舞台に立っているわけでもなく、「個を純粋に犠牲にした」歌舞伎役者として周囲から頼りにされ、「からっぽ」の存在として操られることを楽しんでいる様子でもある。
年齢を重ねて喜久雄が傍目に「ぐったりとした人形」のように見えても、舞台に立つ喜久雄の一挙手一投足の演技は、伝統文化の継承者としての天皇のように威厳に満ち、洗練されている。その立女形(編集部注/一座の中で最高位の女方)としての姿は「高貴な香のかおり」「気高い香り」に包まれている。