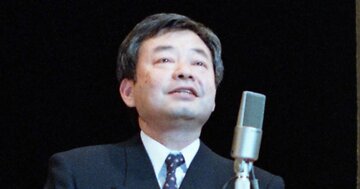このような喜久雄の姿は、病を抱えながらも東日本大震災の被災地訪問を繰り返し行い、被災者に一命をかけて寄り添った天皇の姿とも重なって見える。
つまり吉田の『国宝』は、2019年に生前退位した天皇の姿を、歌舞伎の女形として芸を極めた喜久雄の人生に重ねた、と解釈することもできる器の大きな作品だと私は考える。
「歌舞伎を超えた」喜久雄と
「人間を超えた」天皇
飛鳥井雅道の『明治大帝』を参考にすると、明治憲法の下で天皇は、軍事的な権力を有した「皇帝」と、政治的な権力を有した「元首」と、文化的な伝統の継承者である「天子」の3つの役割を担うことを余儀なくされた。しかし武士に軍事的・政治的な権力を奪われて以後、長らく天皇は「天子」として、伝統文化や祭祀を後世に伝える役割を担ってきた。
 『吉田修一と『国宝』の世界』(酒井信、朝日新聞出版)
『吉田修一と『国宝』の世界』(酒井信、朝日新聞出版)
『国宝』の終盤では、喜久雄が女形という伝統芸能の継承者として「天子」のような存在となって歌舞伎の舞台に立ち続ける姿が描かれている。
やがて喜久雄の演技は「歌舞伎を超えた」と評されるようになり、彼は同時代の梨園を代表する立女形となる。「からっぽ」の存在として舞台に立ち、演目を丸ごと呑み込み、その役柄を血の通ったものとして消化し、「振袖の一振りにも匂い立つ」ような芸能を体現していく。
「歌舞伎を超えた」状態にある喜久雄の存在は、「人間を超えた」状態にある象徴としての天皇の姿に類似している。喜久雄は「個を純粋に犠牲にした」立女形として、梨園の世界に閉じ込められ、「出してくれ、出してくれ、と尾を叩きつけて」いるというよりは、そういう梨園の世界の「構造的な暴力」ともいえる伝統を、半ば宿命として引き受けているように見える。
「人間国宝」が伝統芸能を伝えるための「からっぽの器」でしかないと読み取れる表現は、敗戦後に人間宣言をし、「象徴」として生まれ変わった天皇のメタファーであると私は考える。
「からっぽの底が、そんじょそこらのからっぽの底とは違い、恐ろしく深い」という表現は、人間国宝や象徴天皇に向けた最大の賛辞だと解釈できるかもしれない。