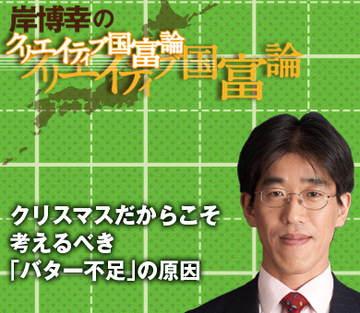中洞牧場牛乳。雑味のないきれいな味だ
中洞牧場牛乳。雑味のないきれいな味だ
盛岡から車で二時間。標高800mの北上山地の中腹の空気はひんやりとしていた。
あいにくの天気で、あたりは霧に包まれている。目の前にあるのは森と、なだらかな山の稜線。木々は深い緑色をたたえ、薄緑色の野シバが斜面に柔らかく茂っている。その斜面を牛がゆったりとした歩みで登っていく。ジャージー種の血が入った褐色の牛の体格はがっちりとしている。夕方の搾乳を終えた牛が山に戻っていくところだった。
中洞牧場には一般的な牛舎がない。話には聞いていたし、写真では見たことがあったけれど、実際に目にすると景色のスケールに驚いた。
牛たちは365日、山で暮らし、搾乳の時だけ降りてくる。植物生態学者の猶原恭爾博士が1960年代に提唱した山に牛を放牧する「山地酪農」というスタイルだ。
「自然と牛がつくりだした景色」
と牧場長の中洞正さんはそう表現する。牛が食べるのは山の野シバやクマザサ、木の葉といった山に自生する草、飲むのは山の清水だ。そうして育つ牛から搾る牛乳はかすかに黄色味をおび、あっさりと軽い。その味をして「奇跡の牛乳」と呼ぶ人もいる。
牛舎に牛が一杯いる
一般的な日本の酪農への疑問
遠くから牛の鳴き声が聞こえるが、姿は見えない。2012年にできたばかりの研修棟で牧場長の中洞正さんからお話を伺う。牧場にはスタッフが生活するこの研修棟と牛乳などを加工するプラント、それと搾乳用の小屋がある。
 牧場長に山の説明を受ける。スケール感が伝わるだろうか
牧場長に山の説明を受ける。スケール感が伝わるだろうか
──酪農というと牛舎に牛が一杯いるというイメージがあるので驚きました。
「というよりも、日本の酪農が異常なんです。今の日本の牛乳は虐待的に飼育された牛から搾られています。なんで密飼にして、1日に1頭の牛から30Lも50Lも牛乳を搾るのか。これはそもそも日本の畜産業界の仕組みが、アメリカのトウモロコシや小麦といった余剰作物を消化するためにつくられたものだからです」
日本で流通している牛乳は100%国産だが、カロリーベース自給率では43%しかない(『けいさん こくさん』より)。飼料を輸入に頼っているのが理由である。
昔から牛は経済動物と呼ばれ、酪農では一頭あたりの牛から搾れる乳量を増やすことが善とされた。しかし、2006年には生産量調整のために北海道で牛乳が廃棄された。たくさん搾っておきながら廃棄するというちぐはぐな状況にある。
酪農の世界は他にも多くの問題を抱えている。例えば、バター不足は慢性化し、現在もスーパーの棚に少ない。農林水産省は「バター不足に関するQ&A」という特設ページのなかで「年度内に必要なバターは、確保されたものと考えています」と書いている。この文言を書いた人も本当にそう思っているわけではないかもしれないが、あいかわらずバターは不足し、スーパーの棚にも少ないままだ。農水省はこの9月に追加の輸入の要否を決定するとしている。
バター不足の原因は酪農家の減少だ。高齢化も要因ではあるが、経営的な部分も大きい。元々安い乳価のため薄利だったところに、光熱費の上昇や輸入飼料の価格高騰を価格に転嫁できないのだ。通常の酪農では経営コストにおける飼料代の割合は47%(生乳1kgに対して)を占める。2008年に穀物相場を急上昇したという報道も記憶に新しい。