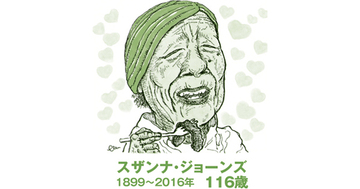樋口直哉
「フライパンに高さ1cmほどの油」でOK!からあげを上手に揚げる簡単な方法【プロが解説】
家庭で作ろうと思うと、ついつい億劫になってしまいがちの「揚げ物」。特に、調理後の油の処理について悩んだ経験を持つ人も多いのではないだろうか。だが実は、少量の油でおいしく揚げ物を作る方法があった……!料理家・樋口直哉が、本当はカンタンな揚げ物の方法を解説する。※本稿は、樋口直哉『料理1日目 たったの10皿で「料理の基本」はマスターできる』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。

卵を冷蔵庫のドアポケットで保存してはいけない理由、おすすめの場所とは?
栄養満点かつ手頃な価格で、毎日のように食卓に登場する卵。初めての料理が「目玉焼き」だったという人も多いのではないだろうか。実はこの目玉焼き、卵の選び方・保存・焼き方で見ていくと、とても奥が深いもの!料理家・樋口直哉が、おいしい目玉焼きができるまでの道のりを分かりやすく解説する。※本稿は、樋口直哉『料理1日目 たったの10皿で「料理の基本」はマスターできる』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。

高級みそを使えばいいってもんじゃない!「みそ汁のおいしさ」を決める“たった1つのこと”
日本の食卓の定番、みそ汁。代表的な家庭料理だが、いざ「おいしく作ろう!」と思うと意外と難しいもの。みその選び方からおいしく作るポイントまで、これから料理を始める人へのアドバイスを料理家・樋口直哉が語る。※本稿は、樋口直哉『料理1日目 たったの10皿で「料理の基本」はマスターできる』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。

『解体新書』の翻訳、『蘭学事始』の著者として知られる杉田玄白。江戸時代にしては卓越した長寿者だった彼は、古希(70歳)を迎える前年「養生七不可」という健康長寿のためにしてはいけないことを子孫のために書き記している。
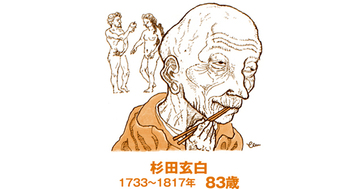
世界で一番有名な日本人画家は誰か? この質問に葛飾北斎と答える人は多いはずだ。88年の生涯で『富嶽三十六景』『北斎漫画』『東海道五十三次』など数多くの作品を残し、日本のみならず世界の画家、なかでもモネ、ドガ、セザンヌ、ゴーギャンといった印象派に大きな影響を与えた。
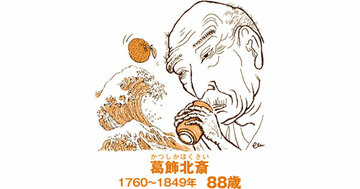
自動車王ヘンリー・フォードは成功すると田舎で理想主義的な生活を実践しようとした。その食生活は牛乳を飲まず、肉も食べないというものだった。代わりに大豆を好み、甘いものを避け、野草を摘んでサラダやサンドイッチにして食べた。
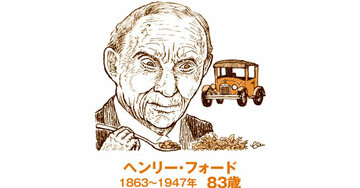
「葬式無用 弔問供物固辞する事 生者は死者の為に煩(わずら)わさるべからず」西洋画の大家、梅原龍三郎の訃報と共に報じられたこの遺言は世間の人々に強い印象を残した。
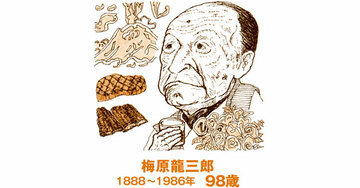
第43回
吉行あぐりは日本の美容師の草分けで、1997年4~10月に放送されたNHK連続テレビ小説「あぐり」のヒロインのモデルとなった。2005年に閉店するまで、90歳を過ぎても現役の美容師として働いたことが、NHKのドラマ放映とともに話題になった。
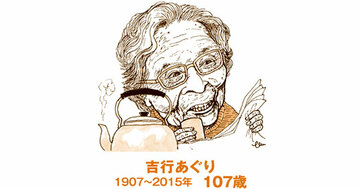
第42回
日本画家の横山大観が師、岡倉天心から学んだのは芸術だけではなかった。一生愛することになる日本酒である。大観はもともと、酒が飲めなかったというが、天心に勧められるまま、酒を愛するようになる。
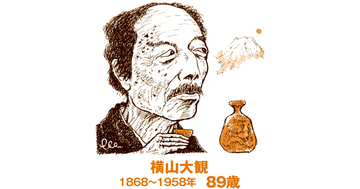
第41回
死の直前まで旺盛に仕事に打ち込んだ作家がいた。明治、大正、昭和を生き抜き、多くの作品を世に残した野上弥生子である。弥生子は1885(明治18)年に大分県で生まれた。
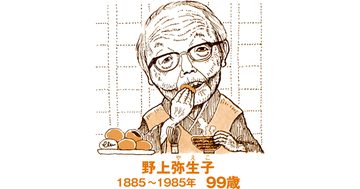
第40回
「盛期ルネサンスの三大巨匠」といえば一般的にレオナルド・ダビンチ、ミケランジェロ、ラファエロの3人を指す。ルネサンスという同時代に生きた彼らの中で最も長生きしたのがミケランジェロだ。
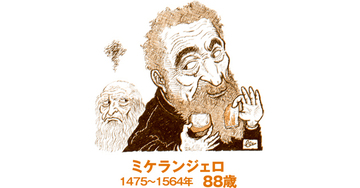
日本を代表する電機メーカーの一つ、東芝。2009年から6年間にわたって続けられたという粉飾決算が報じられ、買収した子会社が抱えた巨額の損失などもあって、ここ数年、経営危機がささやかれている。東芝は今から数十年前、1960年代にも一度、経営危機に陥っている。そのとき、改革を主導し、見事再建に導いた経営者が土光敏夫である。
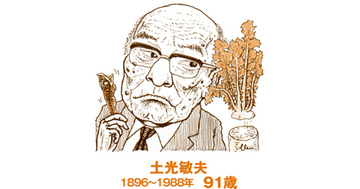
第35回
トマトは江戸時代に観賞用として珍重され、明治時代以後、日本に広まった。そこに大きく貢献したのが蟹江一太郎、トマトケチャップなどで知られる企業、カゴメの創業者である。
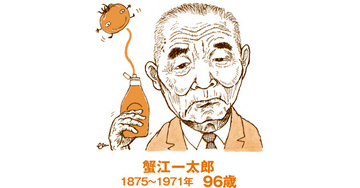
第34回
「豚一殿」というあだ名で呼ばれた人物がいた。徳川幕府最後の将軍、徳川慶喜である。もちろん、いいあだ名ではない。当時、日本人は公には獣肉を食べなかった。堂々と食べる慶喜を見て、世間の人は驚き、こんな風にささやいたのだ。
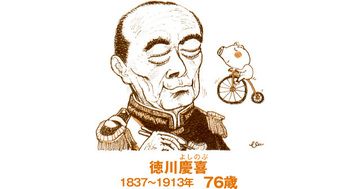
第33回
山梨県=甲州でブドウ栽培が盛んになったのにはいくつかの理由があるが、この地に棚栽培を広めたのは戦国時代から江戸時代初めにかけて活躍した医者、永田徳本といわれている。
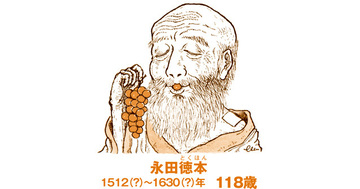
第32回
関ケ原本戦で破れた西軍の大名で最も遅くに没したのは誰だろうか。調べてみると意外な人物だった。備前国を治めていた宇喜多秀家である。秀家は西軍が壊滅した後、薩摩に身を潜めるが、結局幕府に出頭。八丈島への流罪に処された。
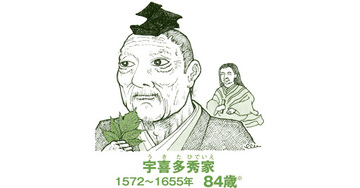
第35回
かつて「成人病」と呼ばれていた病気の罹患には生活習慣が関わっていることがわかり、「生活習慣病」と改められた。この改称を主導した医師の一人が聖路加国際病院の名誉院長、日野原重明先生である。

第51回・最終回
どのような食べ物にも歴史があり、人の物語がある。ここ千葉県山武郡横芝光町は日本のハム・ソーセージの父と呼ばれる大木市蔵の生誕地だ。かつてはあった大木ハム千葉工場も現在ではなくなり、町内でも大木を知る人が少なくなりつつあった。

第50回
お正月に食べる魚はブリや鮭が一般的だが、静岡県伊豆地区ではカツオの塩漬け=潮カツオを食べる風習が残っているという。西伊豆田子町にある創業1882年のカネサ鰹節商店を訪れ、5代目店主芹沢安久さんからお話を伺った。

第34回
昨年5月、ギネス世界記録上、〈存命人物のうち世界最高齢〉と認定されていた女性が亡くなった。彼女の名前はスザンナ・ジョーンズ。1899年生まれというから驚きだ。彼女は死の間際まで食欲旺盛で、ベーコンが好物だった。