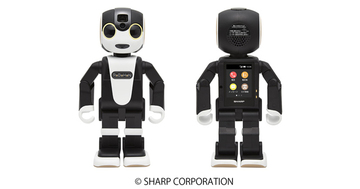シャープ経営危機の元凶とされる液晶事業だが、ほんの10年ほど前までは破竹の勢いだった。そして、その将来性に魅了され、液晶事業で世界を制するという夢を描いた男たちがいた。

かつて液晶事業の未来を周囲に語るとき、シャープ5代目社長の片山幹雄(が好んで口にした映画がある。スティーブン・スピルバーグが監督を務めた、2002年公開のSF映画「マイノリティ・リポート」だ。
2054年の世界を描いたこの映画の中で、片山が「わが意を得たり」と感じたのは、未来では今と比べものにならないほど、文字や映像を表示するディスプレイが日常にあふれていたことだ。
印象的なのは、トム・クルーズ演じる主人公の刑事が、目の前に広がる巨大ディスプレイにさまざまな映像を映し出す推理シーンだが、それだけではない。
未来の米大衆紙「USAトゥデイ」はそれ自体がディスプレイになっていて、紙面には映像も流れ、1面記事が緊急速報に差し替えられる。また、シリアルの箱の表面がディスプレイになっていて、主人公が手に取るとアニメーションが流れるシーンも描かれている。
片山は映画が描く2054年の未来と、自ら描く将来のビジョンを重ね合わせた。シャープの液晶パネルこそが、未来の日常にあふれるディスプレイになるのだと。
「液晶の次も液晶」。かつて、ブラウン管に取って代わった液晶の、さらに次にくるディスプレイについて問われた片山は、そう答えた。大阪の中小企業が「世界のシャープ」になる。そんな夢物語を現実にした液晶という技術と事業の将来性を信じ切っていたのだ。
液晶に社運を懸け
ブラウン管時代のコンプレックス払拭

その液晶事業の原点は電卓にある。ディスプレイに液晶を搭載したことが礎となった(写真(1))。
その後、液晶事業は破竹の勢いで成長を遂げていく。1986年に3代目社長に就任した辻晴雄の時代には、液晶部門は事業部、事業本部へと昇格した。
また、ビデオカメラ「液晶ビューカム」(写真(2))や携帯情報端末(PDA)「ザウルス」(写真(3))といった、液晶ディスプレイを搭載したヒット商品が生まれ、「液晶のシャープ」が確立した。
その後を継いだ4代目社長の町田勝彦は、液晶でテレビ市場の攻略を試みる。シャープは初の国産テレビを開発するも、ディスプレイに使うブラウン管は他社に頼らざるを得なかった。また、当時のシャープは存在感が薄く、「顔の見えない会社」とやゆされた。
これらに強烈なコンプレックスを持っていた町田は、液晶事業にのめり込む。テレビの“顔”であるディスプレイを自社生産の液晶パネルにすると同時に、リビングルームの“顔”であるテレビの市場を制する。そう決めた町田は、液晶事業に社運を懸けたのだ。