三越伊勢丹ホールディングス
関連ニュース
「コロナに強い」百貨店ランキング【完全版】
ダイヤモンド編集部,清水理裕
新型コロナウイルスの感染拡大で百貨店が青息吐息だ。そこで今回は「『コロナに強い』百貨店ランキング」を作成した。現在の逆境における耐久力が高い百貨店がどこなのか、確認してみよう。

第2回
ディズニーが「ゲストを喜ばせるため」実践するスゴい仕組み
上田比呂志
おもてなし・ホスピタリティのプロフェッショナル、上田比呂志氏が新著『ディズニーと三越で学んできた日本人にしかできない「気づかい」の習慣』を出版した。同書の中から、相手の心をつかむ心くばりの方法をレクチャーする。今回は、ディズニー時代に学んだ「ゲストを喜ばせる」ための徹底した仕組みについて。

第1回
ディズニーもマネできなかった「日本的な気づかい」とは
上田比呂志
老舗料亭の子として「心」を学び、三越入社後は「スキル」を、米国ディズニーでは「仕組み」を学んだ、おもてなし・ホスピタリティのプロ、上田比呂志氏が新著『日本人にしかできない「気づかい」の習慣』を出版した。同書の中から、人との付き合い方、育て方など、相手の心をつかむ心くばりの方法をレクチャーする。

コロナで地方百貨店が窮地、11社が3期連続赤字の構造不況業種を直撃
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
あらゆる業種にダメージを与える新型コロナウイルス。売り上げ減少に悩み、経営危機にあった地方の百貨店は、買い物客の外出自粛で“死期”がますます早まっている。3期連続赤字の百貨店は崖っぷちだ。

第44回
伊勢丹の創業家、2代目小菅丹治が語った丁稚時代と修養の訓
ダイヤモンド編集部,深澤 献
老舗百貨店の伊勢丹は、東京・湯島の呉服店に奉公していた初代小菅丹治が、1886年に東京・神田旅籠町で創業した伊勢屋丹治呉服店が発祥である。「帯と模様の伊勢丹」との評判を得た人気呉服店を、百貨店に進化させた“中興の祖”は2代目小菅丹治だ。

百貨店業界の売上2~4割減、新型コロナだけじゃない「三重苦」の難局
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
新型肺炎をめぐって社会が動揺し続ける中、3月2日に発表された大手百貨店の2月度の売上高速報値。東京・銀座や大阪・心斎橋などインバウンド需要への依存度が高かった店舗では2~4割の大幅減となった。昨秋の消費増税以降、苦戦が続く業界にとって新型コロナウイルスの感染拡大が追い討ちをかける形となった。百貨店業界が“三重苦”に苛まれる状況は今後も続きそうだ。

アジアの日系百貨店は「オワコン」か?中国やタイ資本に猛追される理由
姫田小夏
閑古鳥が鳴いていた上海高島屋だけでなく、バンコクに進出する伊勢丹や東急百貨店など、アジアの主要都市で集客に苦労する日系百貨店は少なくない。人気を集めるタイ資本や中国資本の商業施設は、一体どこが優れているのだろうか?

第11回
東横百貨店と三越の合併を画策、東急総帥・五島慶太が描いた夢
ダイヤモンド編集部,深澤 献
東京・渋谷の東急百貨店東横店が2020年3月31日で営業を終了する。渋谷駅に直結する同店は1934年に開業した「東横百貨店」が前身で、86年の歴史に幕が下りることになる。
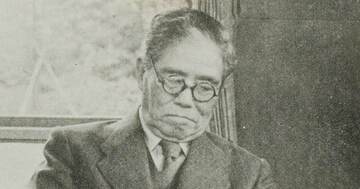
百貨店「大物4人衆」が去った業界でくすぶる営業系vs企画系
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
百貨店業界のトップは、営業と企画という百貨店の根幹を成す2部門を知り尽くした「ミスター百貨店」ともいえる人材が就いていた。だからこそ2000年代の再編を先導できた。だが今は、かつてのような人材がおらず、小粒だと評される。

三越伊勢丹HD、「中間目標」未達見通しで構造改革路線に黄信号
ダイヤモンド編集部,岡田 悟
実質的なクーデターによる社長交代を経て2年。三越伊勢丹ホールディングスは、前倒し達成できると説明してきた2020年3月期の350億円という営業利益の”中間目標”を引き下げた。前体制を批判して構造改革路線を掲げてきた杉江俊彦社長は果たして、有言実行のリーダーとなれるのだろうか。

第90回
アマゾンに圧倒される百貨店がリベンジを狙える「昔ながらの秘策」
情報工場
三越伊勢丹HDの展開するプライベートブランドが、2019年春夏シーズンをもって終了するという。売上げが伸び悩み、黒字化が見込めないとの理由だ。アマゾンと同様の「良質適価、かつ高感度」というコンセプトを掲げながら、なぜ勝てないのか。

第109回
会社を私物化するトップは、どんなふうに組織を腐らせるのか
秋山進
30代以下の方はそもそも知らないと思うが、経営者の会社私物化においては「三越岡田事件」という有名な事件がある。1982年のことだから、35年以上前の話だ。ただ、古い話ではあっても、経営者の会社私物化の原型のような例であるので、少し詳しく語ってみたい。

日本橋三越の大リニューアル不発、デジタル化で現場大混乱
週刊ダイヤモンド編集部,岡田 悟
デジタルを駆使した“もてなし”を目玉に昨秋リニューアルした三越日本橋本店。だが掛け声とは裏腹に売上高は前年を下回ってスタート。実態を無視した施策に、現場は混乱に陥っている。

百貨店「大閉店時代」に地域の地盤沈下を防ぐ3つの対策
圓角史人
地方都市・郊外では、百貨店の閉店が相次いでいる。消費行動の変化がその大きな要因だが、百貨店の閉店は「まちづくり」の視点からも大きな痛手だ。賑わいが消え、雇用を喪失させないためにも、地域経済の側面から百貨店の生き残り策を考える必要がある。
