
山下一仁
TPP合意で、日本は米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖の重要5品目について「聖域」を守ることに成功した。それは日本農業に影響を与えないことを意味する。にもかかかわらず巨額の農業対策予算が組まれようとしている。

第9回
規制改革会議の改革案は、農協の意向を無視できない自民党によって、骨抜きにされた。だが、もうひと波乱起こるかもしれない。今年の秋、米価暴落が待ち受けているからである。それは農協改革の千歳一隅のチャンスとなる。
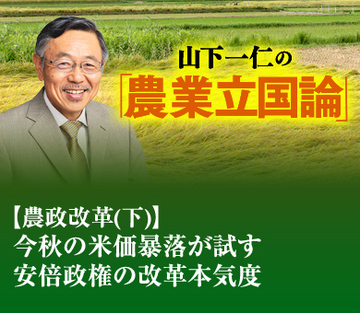
第8回
去る6月、政府はアベノミクス第三の矢である「成長戦略」の目玉の一つとして、農業分野の規制改革を決定した。本稿では2回にわたり、その狙いと行方について論じる。まず、日本農業が衰退してきた理由と改革の真意を考えよう。

第7回
戦後政治における最大の圧力団体であるJA農協は、その独占的地位を活用して、今や農家の利益よりも組織の利益が優先し、日本農業の高コスト体質をつくり上げている。戦後農政を変革するに、農協改革を推し進めなくてはならない。
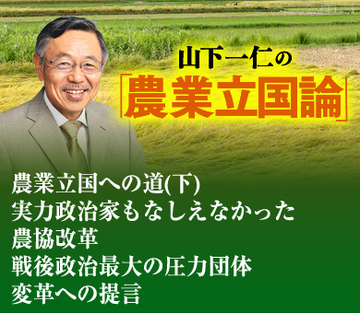
第6回
農業立国を実現するには経営規模を拡大する必要がある。それを阻害しているのが1952年にできた「農地法」。農地を集約し規模拡大を実現するには土地利用を定めるゾーニング規制を強化する一方、農地法を廃止する必要がある。
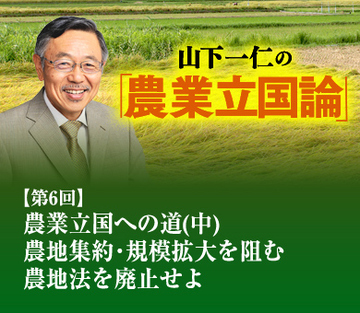
第5回
これから3回わたりいよいよ日本が農業立国の道を歩むための方策を論じる。この道を実現するために改革すべき政策とは、高米価、農地法、農協制度という戦後農政の3本柱である。今回は高米価政策にメスを入れる。
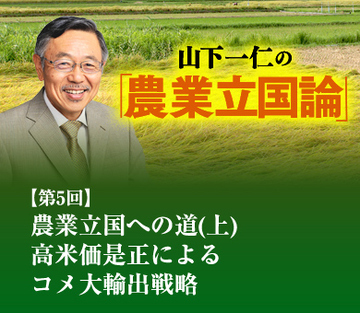
第4回
自民党は、コメなど5品目を関税撤廃の例外とし、これが確保できない場合は、TPP交渉から脱退も辞さないと決議した。だが、関税撤廃し減反政策をやめ、直接支払方式に転換すれば、米価が下がってコメ輸出拡大の道も開ける。
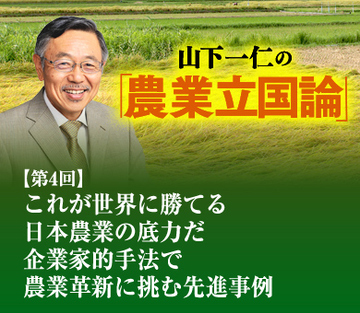
第3回
自民党は、コメなど5品目を関税撤廃の例外とし、これが確保できない場合は、TPP交渉から脱退も辞さないと決議した。だが、関税撤廃し減反政策をやめ、直接支払方式に転換すれば、米価が下がってコメ輸出拡大の道も開ける。

第2回
農協、農水省、農林族議員から成る農業村の人たちは、都市市民の農村に対する古いイメージを利用して、高い関税や農業保護を維持するための様々な主張を行ってきた。国民を惑わす「農業村」の主張の誤りを明らかにする。
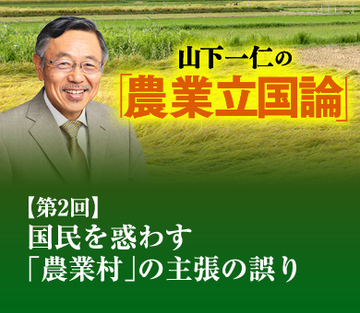
第1回
今の農業や農村は都会人が抱くイメージとは全く異なっている。都会人が信じている「農村伝説」の正体を明らかにし、いかに一般国民が抱いている農村・農家のイメージと現状がかけ離れているかを示す。
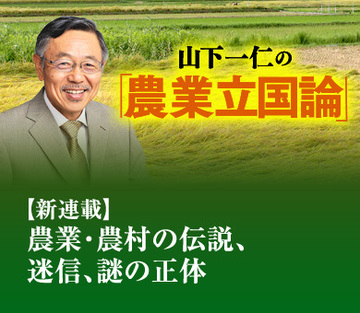
第386回
大手のマスコミがこぞって「減反廃止」を報道した。だが、戦後の農政の中核であった減反廃止=高米価政策の転換が本当なら、農村や農協はハチの巣をつついたような騒ぎになっているはず。それが起こらないのはなぜか。
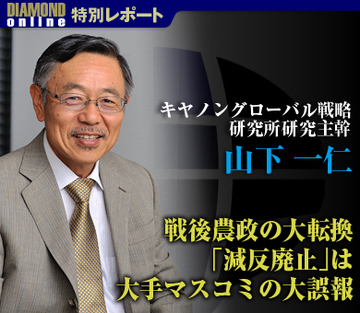
第21回
子ども2人を含む4人が死亡したユッケ食中毒事件は、単なる業務上の過失というより、被害者が病気になっても死亡しても仕方がないという「未必の故意」さえ感じる。事業者は、厳罰に処されるべきだ。また、行政の不備を放置した厚労省と政治家も「不作為の作為」の批判は免れない。

第20回
日本で生じる食料危機とは、お金があっても、物流が途絶して食料が手に入らないという事態である。それは今回の震災でも生じたし、最も重大なケースは、日本周辺で軍事紛争が起きてシーレーンが破壊され、食料を積んだ船が日本に近づけない事態だ。そのとき、想定外という言葉に逃げ込まないために、われわれはどう備えるべきなのか。

第19回
米韓FTA(自由貿易協定)が合意に達した。貿易自由化の波に取り残されないためにも日本は、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加する必要がある。その際、農業を守りたいならば、農政の欠陥を正さなければならない。それができれば、TPPは農業の救世主となる。
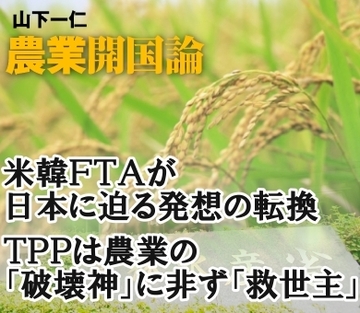
第18回
鳩山政権の誤った農業政策によって、兼業農家が補助金目当てに主業農家に貸していた農地を貸しはがす事態が起きている。このままでは、納税者の負担も雪だるま式に増えかねない。民主党政権の罪は深い。

第17回
既得権益に切り込む鳩山政権の覚悟を問う農政改革。だが、自民-農協-農水省の鉄のトライアングルを崩し、世界に通用する農業を作るには、あまりに公約に矛盾が多すぎる。筆者は、マニフェストの大幅見直しをお勧めしたい。
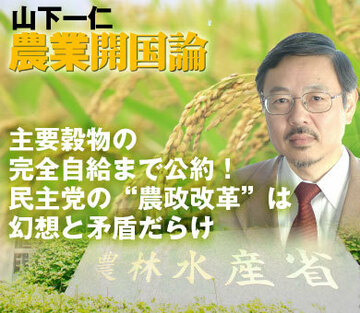
第16回
汚染米問題の再発防止策として今年4月に成立した「米トレーサビリティ法」は、農政をガチガチの統制時代に戻しかねない天下の悪法である。汚染米問題の原因は同省の対応ミスであり、流通の複雑化にはない。

第15回
はっきり言って、自民党と民主党の農政に、大きな差異はない。だが、期待を込めて言えば、民主党政権のほうが改革には適していそうだ。その根拠は、農協との敵対関係にある。

第14回
「所有から利用へ」をキャッチフレーズに掲げる農地法改正法案が衆院で可決された。農政当局は「平成の農政改革」と形容しているようだが、筆者には「昭和の懐メロ」に聞こえる。
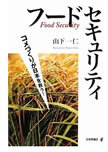
第13回
農政改革の一案として政府内から浮上した減反選択制は、実は民主党案に酷似している。総選挙の年だというのに、与野党間で争点がないのは由々しき事態だ。しかも、この案は、はっきり言って、まやかしである。
