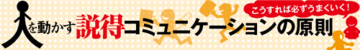福田 健
最終回
説得に応じない顧客や部下に対して、「やる気のない人たちには困ったものだ」と、嘆く傾向が見られる。でも、果たしてそうだろうか。やろうにも、やれない事情があると考えてみることも、説得のアプローチとしては重要なことである。
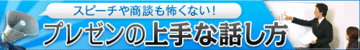
第12回
「すべてのプレゼンテーションは、説得を目指す」ものである。だから、説得から逃げ出すことはできない。ところが、説得は苦手という人が意外に多いのも事実である。なぜだろうか。
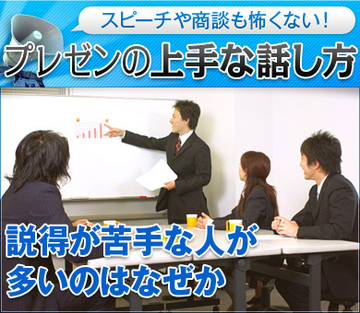
第11回
いまの時代、技術者も営業活動に携わる機会が増えた。ただ、すぐれた中身を持っていながら、人間関係づくりがスムーズに運ばないまま、プレゼンテーションの場に臨んでしまうケースも珍しくない。
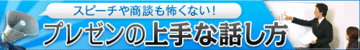
第10回
理屈によって相手の感情に働きかけることも、できないことではない。とはいえ、「印象深く」話すためには、話し手がある出来事なり、事柄に対して、感情を動かされるところから出発し、それを感情を込めて聞き手に表現することが常道だ。
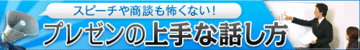
第9回
冗長なプレゼンテーションを聞いていると、何がポイントなのか、どこが重要な個所なのかを見つけるのに手間どって、しまいには聞くのが面倒になってくる。そこで今回は、プレゼンで簡潔に話すための要点、無駄の省き方をご紹介しよう。
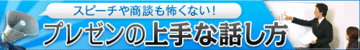
第8回
「わかりやすく」表現するというのは、プレゼンターの使命でもある。提案内容を説明するのに「わかりやすく」ないと、理解してもらえず、説得も不可能になるからだ。
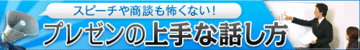
第7回
プレゼンターはタレントではない。面白おかしく話したり、奇抜な演出をこらしたりすると、かえって場が浮き上がってしまい、場違いな雰囲気になる恐れがある。とはいえ、聴衆に飽きられてしまった場合は、どう挽回すればよいのだろうか。

第6回
聞き手の心は「最初の10秒でつかめ!」などといわれるように、「導入部」での話の持って行き方には、充分に力を入れ、技術を磨く必要がある。今回は、そのための工夫を、3つにまとめて述べていこう。

第5回
プレゼンテーションのスタート時に「自己紹介」はつきものである。にもかかわらず、「名乗らない」、「姓だけ告げる」といった例は、決して珍しくない。では、相手に親近感をもってもらえるような自己紹介をするにはどうすればよいか。

第4回
あなたは、いまプレゼンテーションの本番のスタートを切ろうとしている。よいスタートが切れると、緊張がほぐれて、波にのれる。聴衆にとっては、第一印象がよければ、以後のプレゼンテーションを聞いてみようという気持ちが強くなる。
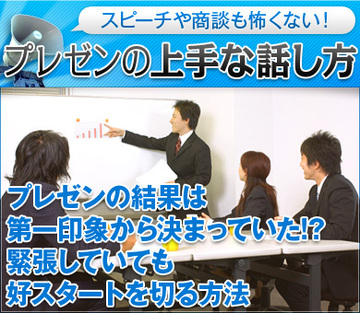
第3回
事前に準備しても、プレゼンテーション会場に入ってみると、予期せぬことが待っていたりする。メンバーの顔ぶれが変わっている、時間が予定より短くなった、場がシラケているなど…。この状態を打破するには、どうすればよいのだろうか。
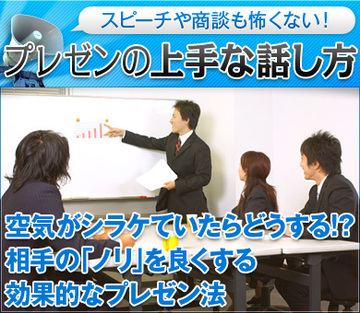
第2回
何事も準備が大切であることは、誰もが承知している。そのわりには準備を怠る人が多い。プレゼンテーションの上手な人は、例外なく充分に準備をしている。逆に、下手な人ほど準備に手抜きをする。
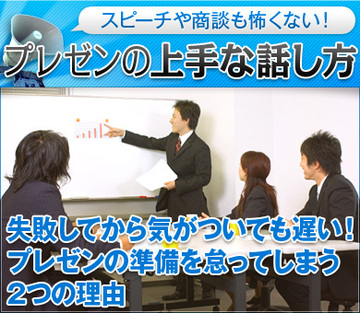
第1回
プレゼンテーションは、対面のコミュニケーションとして、その場に、直接、話し手が姿を現す。機械ではなく、プレゼンターという人間が目の前で話すのである。聞く側に回れば、真っ先に気になるのは、プレゼンターの姿・態度である。
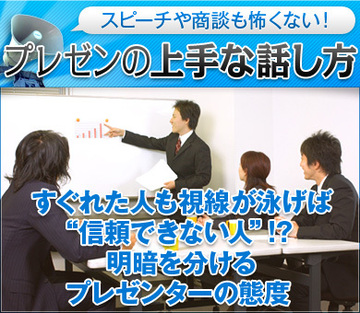
最終回
正面から説得しても、相手にしてもらえない場合がある。そんな場合、視点を変える、ずらすなどの方法が局面を打開して、説得を前進させるのに役立ってくれる。今回は、「視点を変える」説得方法をいくつかみていこう。
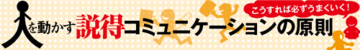
第16回
人間は「時」と「場所」の影響を受けやすい。したがって、人を説得する場合、どんな時や時間で話すかは十分考えておくべき問題である。自分が選んだ時や場に、ふさわしい出方を工夫することも、大切なことである。
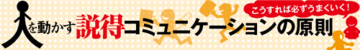
第15回
人間にはイメージを浮かべる能力があり、直接目にしなくてもイメージを浮かべることによって視覚を刺激される。人を説得する場合、イメージが浮かびやすいように表現すれば、視覚が刺激されて相手も説得されやすくなる。
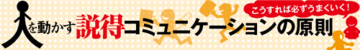
第14回
説得の場合、普段口数の少ない人でも、説得しなければとの思いに駆られて、しゃべりすぎてしまうケースは多い。熱意は底に秘めて、最初はしゃべるのでなく、聞くこと。聞くだけで、実にたくさんの宝ものが手に入る。
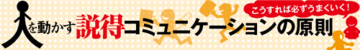
第13回
頑張って説得をしても、行動してもらわなければ説得は完結しない。しかし、「立ち止まり」「戸惑い」でなかなか行動に踏み切れない。思い切って行動に踏み切らせるには、説得者はどう話を持っていけばよいのか。
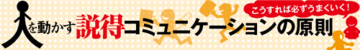
第12回
相手にしてほしいこと、してほしくないことを伝えて、そのとおりにしてもらううまい方法はないものか。1つの方法が「マジック・フレーズ」だ。使うことで、以後の発言がスムーズに受け入れられやすくなる。

第11回
人の心は変わりやすい。否定されると反発して、手に負えなくなる。しかし肯定されると素直になり、説得にも応じやすくなる。つまり、人の心をつかむためには、欠点を強調するよりもよい面に目を向けることが大切だ。