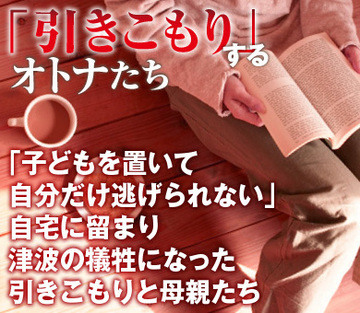池上正樹
第84回
10月16日、被災地支援を目的にしたライブトーク『ひきこもりたちの東日本大震災』を開催した。当日は100人ほどの参加者が集まったが、驚いたのは引きこもり当事者が自らカミングアウトしたり、参加者同士のつながりが生まれていたことだ。
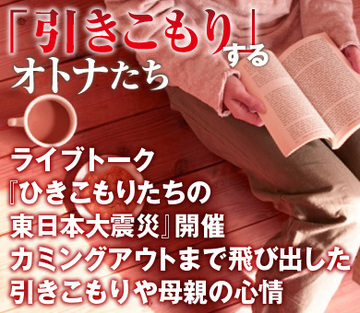
第83回
人や社会とつながりをもてずに生活していた引きこもりの人たちは、東日本大震災からどのような影響を受けたのか。実は、震災を機に症状がさらに悪化した人と、反対に社会復帰している人とに分かれていることが取材でわかった。

第82回
人や社会とつながりをもてずに暮らしてきた「引きこもり」の人たちは、東日本大震災のとき、どうしていたのだろう。今回は、家の2階から出て来られず、津波に飲み込まれたものの、奇跡的に生還した当事者の話を紹介したい。

第81回
東日本大震災後、引きこもりなどの外来利用者や近隣住民が逃げ遅れて取り残され、4日間にわたって孤立していた精神科クリニックがある。実はこの間、引きこもり当事者たちがスタッフを手伝って、近隣住民の面倒を見ていたという。

第80回
あの大震災から、9月11日で半年を迎える。家から出られないタイプの引きこもりのなかには、大津波来襲を知りながら、家から出られず、亡くなった人たちがいる。彼らとその母親は大津波を前にどんな最期を迎えていたのか。

第79回
90年代後半に起きた金融再編のうねり。その現場で働いていた就職氷河期世代は、合併などにより“不機嫌な職場”にて仕事をせねばならなくなった。しかし、彼らの先輩であるバブル世代は、そんな環境でも要領よく生き延びているようだ。
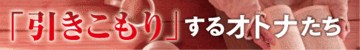
第78回
社会には出ていても、自分もいつ、自信を失って、引きこもるかわからない。そんな不安定な気持ちは、就職氷河期世代の多くの人たちの間に共有されているように思える。なぜ、彼らはこれほどまで自己否定感に襲われるのか。
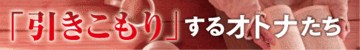
第77回
ここ最近、社会に適応できない「新たな引きこもり層」が大量に生まれている。もはや引きこもり全体に占める社会人経験者は、半数を超えた。一体なぜ、大人の引きこもりの存在がこれほど浮き彫りになってしまったのか。
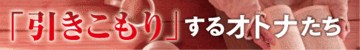
第76回
引きこもりの子どもに対して、「子どもが動き出すのを待ちましょう」と言われたことがあった。しかし、待っていても何も始まらない。「引きこもり家族会」役員の子どもの多くが社会復帰できたというように、親たちが動き、変わることが重要だ。
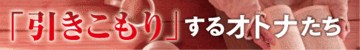
第75回
発達障害を持つ人々は、周囲と円滑なコミュニケーションを取ることができず、社会に出ていくことが難しいケースが多い。しかしその反面、彼らはある分野における優れた才能や心優しい性格を併せ持つことも少なくないようだ。

第74回
引きこもり支援において、相談先の窓口に「当事者」がいることは家族や本人たちにとって敷居を低くするため、非常に重要なことだ。しかし、逆に相談を受ける当事者は、自分のトラウマを思い起こし、追い詰められてしまうリスクも伴っている。
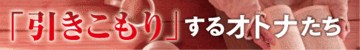
第73回
「発達障害」と、高年齢化、長期化する引きこもりとの関連性が、調査報告によって明らかになった。調査からは、不登校の延長というイメージと違い、半数以上が就労してから職場不適応を起こす“新たな引きこもり層”の存在も伺い知ることができる。
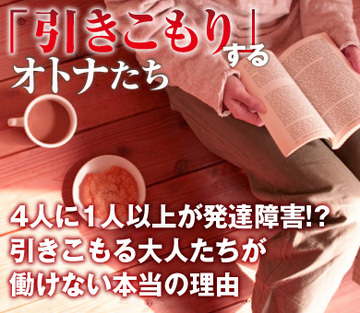
第72回
『ひきこもりゼロの社会はつくれる』――。そう言い切るのは、「引きこもり」など、一見、就業が困難と思われる人たちも積極的に採用してきたアイエスエフネットの渡邉社長だ。一体、どのように彼らを採用・育成してきたのだろうか。

第71回
新潟県に住む「いっしー」さんは、1995年に起きた地下鉄サリン事件を機に、当時勤めていた都内の大手ビル管理会社を退職。その後、休職を繰り返し、妻と離婚するなど、不安定な生活状態に陥った。そして、さらに彼に追い打ちをかける出来事が発生する。
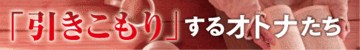
第70回
自ら被災しながらお年寄りや子どもなどのケアを続ける人が被災地にはたくさんいる。カウンセラーの蜂屋美子さんもそんな1人。彼女は震災で落下した天井の下敷きになりながらも、直後から無償でカウンセリングを開始した。
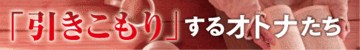
第69回
3月11日の東日本大震災をきっかけに、被災地の引きこもり当事者が、自ら支援を求めて相談に訪れたり、家族との団欒の時間を持ち始めている。それには、家族などが施した“ある仕掛け”が重要な役割を果たしているようだ。
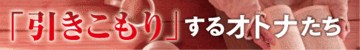
第68回
大震災を機に、親が引きこもっている息子に「大変!」「早く!」などと声をかけたら、息子は部屋から出てきて、その後、親や兄弟と一緒に過ごすようになった――。今回は、そんな家族団欒が復活した話を紹介したい。
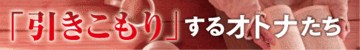
第67回
被災地では、震災を機にボランティア活動のために外に出る引きこもりの人たちが少なくない。誰かを助けたい気持ちが彼らを回復に導くのだが、被災者の支援だけでなく、平常時でも認知症のお年寄りのケアを通じて社会復帰を遂げた当事者がいる。
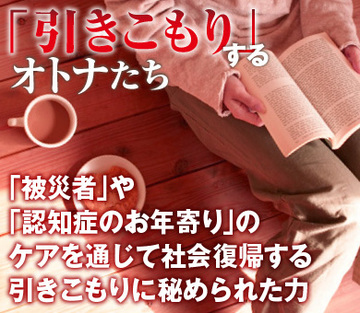
第66回
被災地の東北では地域性が強いために、子どもが引きこもりになれば、当事者だけでなく、家族まで伏せてしまうことがあるという。とくに母親は、夫やその両親から責められることいなり、辛い思いをしている人が少なくない。
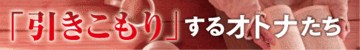
第65回
被災地に住む引きこもりの人たちはいま、どんな状況にあるのだろうか。震災で大きな被害を受けた岩手県宮古市にある「みやこ若者サポートステーション」を訪ねると、現状はもちろんのこと、犠牲になった方々のことも知ることができた。