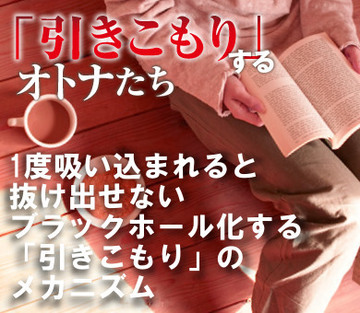池上正樹
第44回
職場の上司や同僚の中にも、日頃の言動や行動が不安定だったり、ひそかに心の闇を抱えていたりする人たちは、たくさんいる。しかし、今では多くの人が声を上げやすい時代になりはじめているようだ。
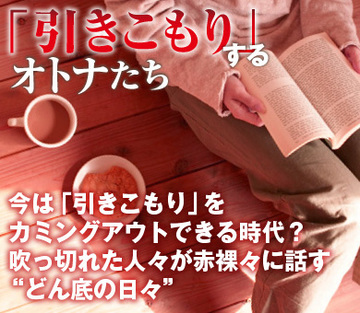
第43回
「3高」がもてはやされ、「ねるとん」が大流行したバブル期。中身よりも外見の華やかさが重視され、そうしたまぶしさの影で存在を消されそうになっていた人々がいた。それが現在「引きこもり」と呼ばれる人々の一部だ。
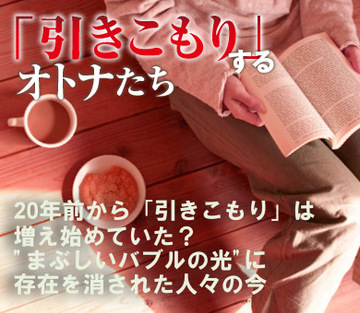
第42回
最近、空気を読めない“KYな人”が、非常に析出しやすい社会になっているところがある。その背景にあるのが、“コミュニケーション偏重主義”の蔓延であり、その能力次第で身分階層さえできてしまっている。
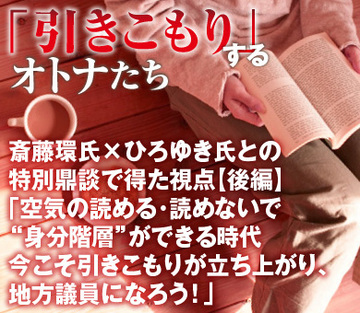
第41回
10月14日夜、『ニコニコ動画』の生放送に再び出演した。今回はひろゆき氏の他に「引きこもり」問題に詳しい精神科医の斎藤環氏も新たに参加。両者と話をするなかで、日本以外にも広がる「世界の引きこもり」事情が見えてきた。
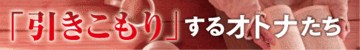
第40回
自分自身や家族が引きこもりになってしまったが、どこにも行き場がない。でも、どこに相談したらいいのかわからない。そんな彼らに手を差し伸べようとする民間側は、採算上厳しい状況にはあるが、少しずつ新たな模索も始まっている。
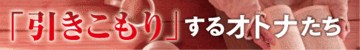
第39回
「引きこもり」のなかでも、深刻化しているのが自宅や自分の部屋などからまったく出られないタイプ。そんな人たちを対象に家庭訪問を行い、その結果、彼らの大半が社会的に自立した生活を送れるようになるほどの高い効果を上げているケースがある。
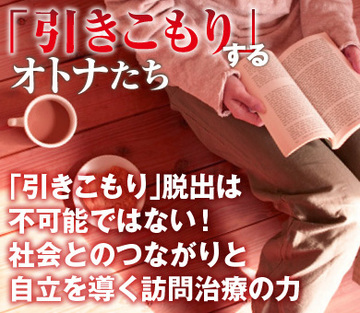
第38回
厚労省は今年9月、うつ病や自殺による日本の経済損失額が、年間約2.7兆円に上るという推計結果を公表した。ただ、精神疾患全般にわたって考えると、なんとその2倍である15.2兆円という推計も出ているほど、深刻な状況だ。
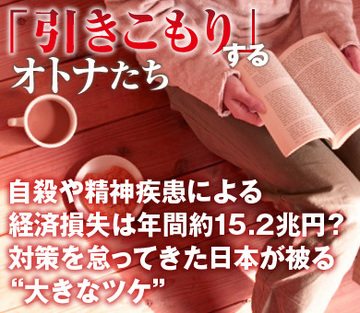
第37回
学生時代は何とかやれていても、社会に出てから立ち行かなくなり、引きこもりになってしまう人が少なくない。しかし、わずかな社会とのつながりが、こうした人たちを救うケースがある。その“つながり”の1つが交換ノートだ。
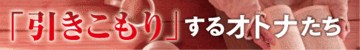
第36回
きちんと仕事をしているにもかかわらず、「引きこもりの気持ちがわかる」という社会人は少なくない。内閣府の調査によるとその数155万人。では、彼らはどういったことをきっかけに実際の引きこもりになってしまうののだろうか。

第35回
子が親の死を隠し、親の年金を不正に受け続ける。そんな「消えた高齢者」の問題が、連日のように報道されている。この問題は、数多く生み出され続ける「引きこもり」問題と社会的弱者が追い詰められる点で根っこは同じだ。
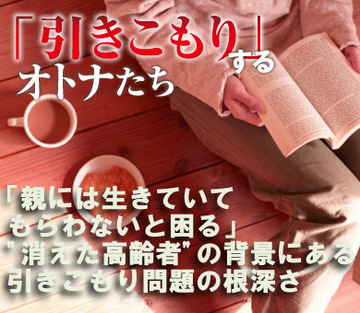
第34回
厚労省発表した新しいガイドラインの考え方によれば、引きこもりの相談に来た人たちの95%に、何らかの精神疾患があるという診断名が付いた。しかし、そんな人たちの一部には「どこかで病気と認められたい」という傾向も推測できる。
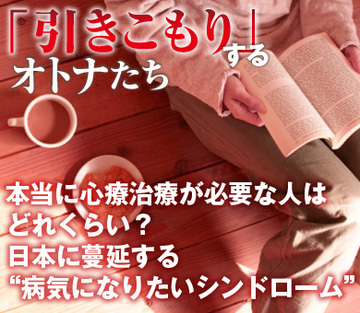
第33回
8月24日夜、『ニコニコ動画』に生出演。元2ちゃんねる管理人の西村博之(ひろゆき)氏と対談した。対談をするなかで、ひろゆき氏は、これまでの引きこもりに対するイメージとその処方箋に新たな発見や驚きを与えてくれた。
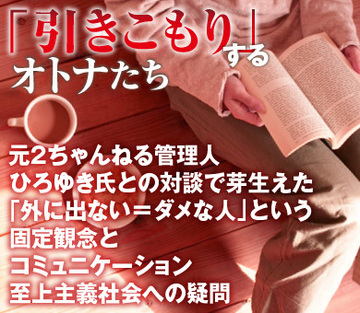
第32回
引きこもりの問題は、当事者とその家族の関係が深刻に語られることが多い。しかし、そんな状況をほのぼのと、ときに明るく伝えるものがある。それが、引きこもり経験者の女性たちが協同制作している「4コマ漫画」だ。

第31回
内閣府の調査によって「引きこもりの中高年化」が進み、「職場や就職上の理由をきっかけに引きこもりになる割合が多かった」という傾向が改めて裏付けられた。ただ、引きこもりの人々が“脱引きこもり”を図っても「社会のハードル」は非常に高い。
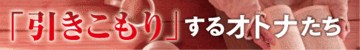
第30回
「自分の趣味に関する用事のときだけ外出するが、外でコアな人間関係を持つことはない」――そんな人たちが、いまの日本で新たな引きこもりの中核を占めつつあるという注目すべき調査結果が発表された。
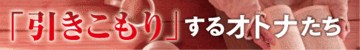
第29回
日本では現在、膨大な数の人たちが、何らかの疾病や様々な理由で社会からはじき出されてしまって、支援を受けることもできずに引きこもらざるを得なくなり、クリニックにだけ通っているという。

第28回
職場で働いたりして、社会生活を営んでいるのに、実は「引きこもり」と同じような心のメカニズムを持つ人たちが顕在化している。いわゆる“仮面引きこもり”ともいうべき人たちだ。
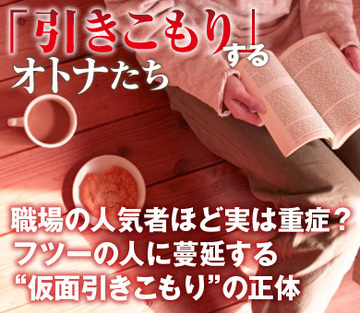
第27回
かつて『家族ゲーム』という映画では、横一列に並んで食事する家族のシーンが印象的だった。しかし、現実の家庭で起こっている光景は、映画で描かれる脚本家の想像をはるかに超える悲しさを秘めている。
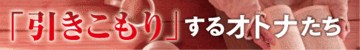
第26回
周囲に知られないよう、身を潜めるように暮らす「引きこもり」の当事者たちはよく、テレビのホームドラマを見ては、「ドラマのシーンに出てくる家庭像が、本当の家族の姿なのだろうか?」と困惑するという。
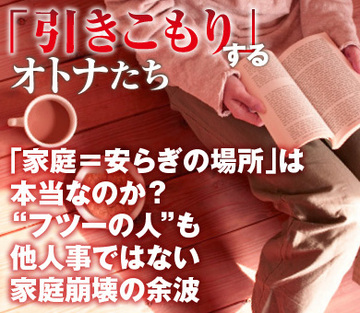
第25回
引きこもりになるメカニズムは、意外にもブラックホールのように恐ろしいものだ。1度吸い込まれてしまうと、本人はいつでも抜け出せると思っているにも関わらず、なかなか抜け出せなくなってしまう傾向がある。