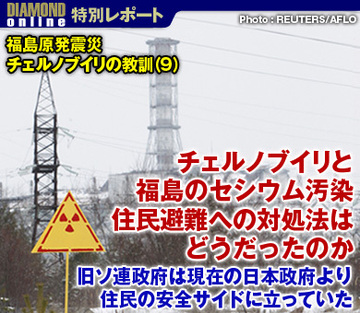坪井賢一
第42回
高橋是清は2度、窮地の日本経済を救った。1931年12月、高橋は蔵相に就任すると、金本位制からの再離脱を発表。財政拡張政策やインフレ政策によって、昭和恐慌を収束させた。高橋が行ったケインズ以前のケインズ政策を後世の研究者は高く評価している。

第41回
高橋是清が昭和恐慌によって窮地に追い込まれた日本経済を救う直前、大蔵大臣に就いていたのが井上準之助だ。インフレ政策を導入した高橋とは対照的に、井上はリストラを伴うデフレ政策によって日本経済を立て直そうとしていた。

第40回
高橋是清は、1921年11月から22年6月まで首相兼蔵相、立憲政友会総裁も経験している超大物政治家だった。1920年代末の金融恐慌と昭和恐慌からの素早い脱出を図り、成功させている高橋を当時、周囲はどう評価していたのだろうか。

第39回
「ダイヤモンド」1936年1月1日号で座談会「議会解散と政局」が掲載された。この当時の岡田啓介内閣は、民政党主体の挙国一致内閣ではあるものの、野党的な政友会が衆議院の多数を占め、衆参がねじれる現在の民主党政権のような状態だった。

第38回
「ダイヤモンド」1937年3月1日号では、有力政治家を招いた大座談会が掲載された。当時の内閣は陸軍出身の林銑十郎首相のもと、日本興業銀行総裁・結城豊太郎が大蔵大臣に就任するなど、金融資本家と軍部の結びつきが話題になっていた。

第37回
「ダイヤモンド」は1937年3月1日号で有力政治家を招いた大座談会を掲載している。その座談会に出席していた芦田均は、自由主義的資本主義からの「現状打破」を訴える代議士や革新官僚への不満を明らかにした。

第36回
近衛文麿は、3度の組閣により、挙国一致のまったく新しい国家体制を目指した。しかし、第一次近衛内閣成立の直前には、軍部が圧倒的な力を誇り、組閣・辞職まで軍部の意のままになるという状況に至っていた。

第35回
近衛文麿は、日本の死命を決する段階で3回組閣をした人物である。1930年代後半には、右翼から左翼まで巻き込んで、近衛を首班とする新しい政党をつくり、挙国一致のまったく新しい国家体制をつくろうという運動まで起きた。

第34回
1951年の日本社会党分裂後、左派社会党政策審議会長、そして書記長となった和田博雄は、もともと企画院の革新官僚で、自由党の閣僚だった。それにもかかわらず、社会党の大幹部へと転身したのは、一体なぜだったのか。

第33回
大正中期から「ダイヤモンド」は、臨時増刊号として、政財界の多くの人物評を掲載した「財界人物」を発行している。その書き手の1人が、幸徳秋水らと「近代思想」を舞台に社会主義者として活躍し、日本社会党の衆議院議員も務めた荒畑寒村だ。

第192回
7月の第4週に2つの重要な議論が政府の食品安全委員会と衆議院厚生労働委員会で行なわれ、すぐに公表された。2つとも福島原発震災によって放出された放射性物質の影響に関わる大きな問題である。
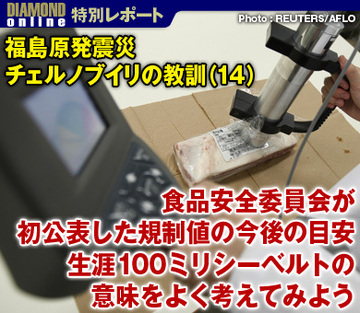
第32回
1945年8月、第2次大戦終結も、兵士の帰国や海外からの引き揚げ者への対応などで財政支出は巨額にのぼり、政府が貨幣増発したことで激しいインフレに襲われた。その後、ドッジ・ラインによりインフレは終息したが、逆にデフレが進行、大不況に陥る。

第31回
第2次世界大戦の敗北から日本経済が復興する過程で、朝鮮戦争特需が大きな契機となった。その特需は当時のGDPの約5%を占めるほどだったが、その後迎える戦争の終結によって、日本経済は危機的状況に置かれることとなる。

第185回
千葉県の東葛地域6市(松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷)の空間放射線量がほかの関東各地より一桁高いことはすでによく知られている。東葛地区は原子力災害を宣言された地域ではない。したがって、平時の年間1mSvが適用され、これに向けて行政はもっと努力すべきではないのか。
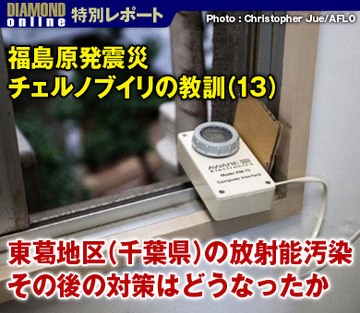
第30回
市場競争を生き抜いてきた電力会社は、革新官僚らによって、民有国営化の流れに巻き込まれていく。そして1939年から1942年まで、資本家・経営者の最後の抵抗が繰り広げられた。今回は、そのなかでも代表的な2人の意見を読んでみよう。
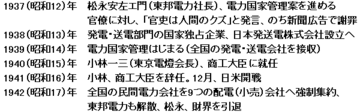
第183回
汚染水はおろか、溶融した核燃料が格納容器を破り、建屋の床も貫通して地面まで落ち、さらに地下へ浸透すれば、膨大な放射性物質が地下水を通じて環境へばらまかれることになる。この事態を回避するためには、地下遮蔽壁をめぐらせるしかない。
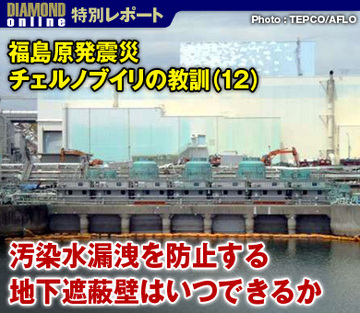
第182回
除染は早く進めたほうがいい。とはいうものの、政府は動かず、自治体は政府の指示を待つ、という拘束された状況が続いている。除染作業は市民ができるとしても、線量計の準備や内部被曝を避ける手順など、専門家の手引きが必要で、その段取りは自治体にしかできない。
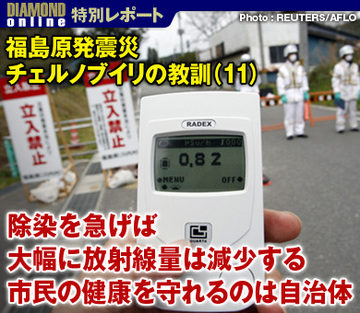
第29回
1940年9月、「資本と経営の分離」、すなわち企業の所有は株主・資本家のままで、経営を国有化して生産力を戦争へ集中させるという統制経済手法を企画院が編み出した。これに財界は大反対したが、結局、案を作った革新官僚に“敗北”する。

第181回
関東地方の都庁、県庁、区役所、市役所が地域内でかなり細かく空間放射線量の測定を進めており、各役所のホームページで公開している。実態がかなりわかってきた。
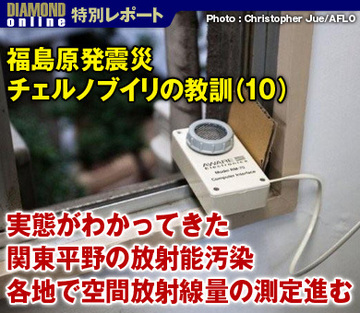
第179回
いつのまにか福島原発の4つの事故炉から放出された放射性物質の総量が倍増していた。今、最も心配なのは原発から80キロ圏だ。チェルノブイリ原発事故時の旧ソ連政府の住民避難への対処法から学べることはあるのだろうか。