
坪井賢一
第16回
1971年に起きた「ドル・ショック」は、通貨単位の切り下げを意味する「デノミ議論」を浮上させた。過去にもハイパーインフレ対策などのために行われ、近年も北朝鮮などで行われている「デノミ」だが、その実施には様々な不安も含まれる。

第15回
1971年8月、米国のニクソン大統領は、議会にも相談せずに「金とドルとの交換停止」を発表した。世界は「ドル・ショック」一色に染まることとなったが、なぜ、ニクソン大統領はブレトンウッズ体制を崩壊させたのだろうか。

第14回
第4次中東戦争の影響により、石油価格は上昇し、日本では狂乱インフレが始まった。インフレ下では、供給側が原材料を買い占めて製品を売り惜しみすることで利益は増大した。企業の社会的責任など、言葉すらなかった時代だ。

第13回
1973年10月6日、エジプト・シリア連合軍がイスラエルに先制攻撃し、第4次中東戦争が始まった。これをきっかけに第1次石油危機へと至るが、アラブ産油国の石油戦略はイスラエルとの戦争で突然出てきたものではないことに注意せねばならない。
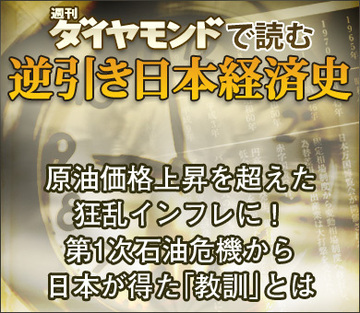
第12回
1970年代に2度の石油危機が起きた。中東の政治情勢の変化=衝撃によって世界に経済的な影響が波及したものである。これによって原材料価格が上がり、産業界のコスト構造が急速に変化する。そしてその結果、スタグフレーションが常態となった。
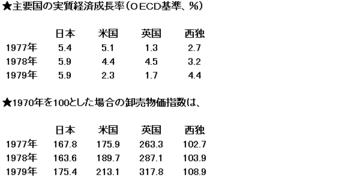
第11回
米国は1960年代半ばからインフレが続いていた。それに対して高金利政策によるインフレ退治、そしてその後乱高下したドルに対してドル安誘導が行われた。この一連の国際金融制度のチェンジを振り付けたのが元FRB議長ポール・ボルカーである。

第10回
1989年12月29日、日経平均株価は大納会のこの日、終値で3万8915円のピークにいたった。「4万円乗せも翌年春あたりに達成するのではないか」という読みもあったが、実際の株価は1990年に入ると下がり、10月には暴落することとなった。

第9回
1990年当時、都心のオフィスビルの空室率は0.2%、ほぼ満杯、需要超過、供給不足で過熱していた。しかし、株価が下落をはじめていたこの年、すでに不動産バブルがはじけ、不動産不況の到来を予想する声は高まっていた。

第8回
1990年のバブル崩壊は、「昨日までの世界」と「今日の世界」の分水嶺だった。つまり、資本主義と社会主義の並存の世界から全面的に地球を覆うグローバリザーションの世界へと変化したのである。

第7回
宮澤喜一政権が誕生した1991年11月、国民はうすうすバブル崩壊を感じはじめていた。そして9か月後の1992年8月、1万4000円台に突入。危機感を強めた大蔵省は、「金融行政の当面の運営方針」を急遽発表し、対策に乗り出した。
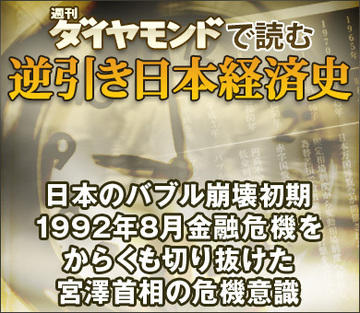
第6回
菅民主党・国民新党連立政権はこれからどうなるのだろう。1993年に始まる現代の連立政権時代では、小泉自民党・公明党連立政権以外、いずれも短命だ。今回は、55年体制以前の連立政権をひもときながら、あるべき“連立政権の姿”を探りたい。

第5回
日本のバブル崩壊は、1990年の株価暴落、1991年の地価下落に始まり、1997年の北海道拓殖銀行と山一証券の破綻で頂点に達した。その2年前の1995年、住宅金融専門会社は経営が立ち行かなくなり、膨大な不良債権の処理をめぐって大混乱に陥っていた。
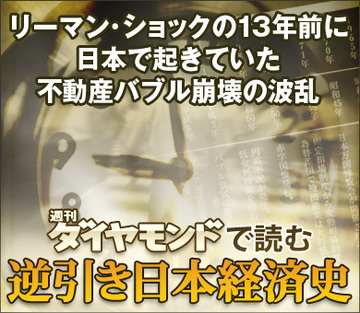
第4回
米国の住宅バブルはいつ発生したのだろう。「週刊ダイヤモンド」をさかのぼってみると、2002年7月に掲載されたレポート「米国景気の牽引車『住宅バブル』の熱狂にひそむ不安」にたどりついた。今から8年前の記事である。
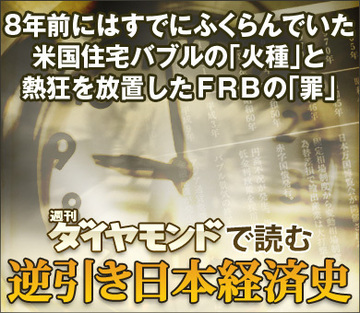
第3回
米国の住宅バブル崩壊が現在の欧州金融危機の発火点だが、これはいつ起きたのだろうか。住宅価格の下落が始まったのは2006年初。年末の12月にはサブプライムローンの販売会社の倒産が始まり、2007年には倒産事例が激増している。
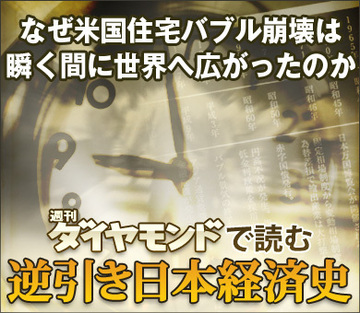
第2回
現在にいたるユーロ危機を引き起こした直接的な原因は、もちろん09年8月に起きたリーマン・ショックにある。しかし、その1年前から欧州には危機を招く他の火種がくすぶっていたという。
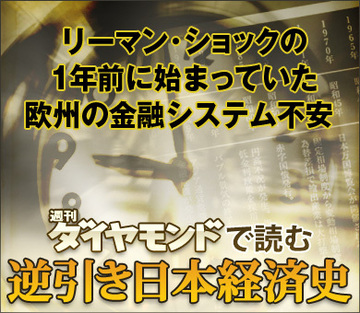
第1回
創刊約100年となる週刊ダイヤモンドのバックナンバーでは、日本経済の現代史が語られているといってもいい。初回となる今回は週刊ダイヤモンドを紐解きながら、「ギリシャ危機がなぜ起きたのか」、その歴史を逆引きしていく。
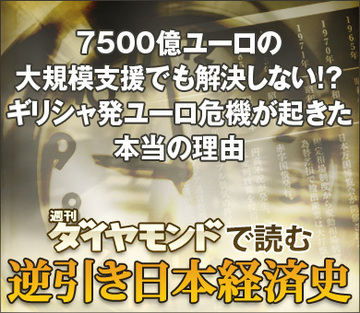
最終回
シュンペーターの冒険旅行は、1932年にハーバード大学で終着駅に到着した。彼の理論は自説についてモデル化できていないので、その後の理論経済学への影響はほとんどない。ただ、経営学には多大な影響をもたらしている。

第64回
日本での講演旅行を終えたシュンペーターは、ボンへ帰って行った。そして、ラブコールを続けたハーバード大学のオファーを受けることに心を決めつつあった。しかし、その頃ドイツはナチスの独裁寸前の状態だった。

第63回
日本滞在中のシュンペーターは神戸に降り立ち、神戸商大で講演を行った。そして、日曜には京都旅行へ出かけた。京都で出迎えたのが高田保馬と柴田敬であり、2人はここぞとばかりにシュンペーターへ質問攻めをした。

第62回
シュンペーターが日本を訪れたのは、世界恐慌の影響によって日本も大不況に陥り、金解禁を行なった1年後の大デフレの最中だった。シュンペーターは様々な講演を通じて、日本の沈滞を招いた原因を鋭く分析した。
