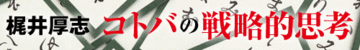梶井厚志
第19回
「メタボ」(公開終了)
米国では、生活習慣病の原因と考えられる5項目のうち3項目に該当すると、メタボと診断する。メタボと肥満とが同義になる必然性はないようだ。なぜ「肥満」という意味でのメタボという言葉が出現したのであろうか。
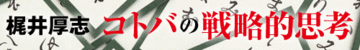
第18回
「千両みかん」(公開終了)
「千両みかん」は上方古典落語の1つである。聴衆に経済学の素養がないと、この噺の落ちで本当に笑うことはできない。ここで求められている経済学的な考え方とは何なのか、あえてより深く考えてみたい。
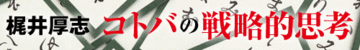
第17回
「遺憾」(公開終了)
記者会見などで「遺憾で残念」という表現をよく聞く。しかし、陳謝の言葉としてふさわしい言葉なのだろうか。文字を素直に見れば、遺憾という2文字の中に謝罪を意図する要素を見出すことは難しいはずだ。
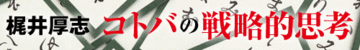
第16回
「……のほう」(公開終了)
「お買い上げの品物のほう、あちらでご精算願います」という表現をよく聞く。ここで気になるのは「…のほう」という部分だ。「お買い上げの品物は、あちらでご精算願います」というのが、はるかに自然である。
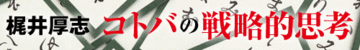
第15回
「空気読め」(公開終了)
「空気読めよ」という表現がある。その場の雰囲気を把握しろ、状況をよく考えろという意味だそうだが、なんとなく不自然なものを感じる。「空気」を雰囲気と同義にみなすことに抵抗を感じるように思う。
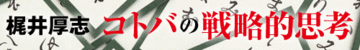
第14回
「過去疑問系言葉」(公開終了)
飲食店で食べ物を頼むと「ご注文は以上でよろしかったでしょうか」と言われることがよくある。あえて過去形にしている点は、その理由がよくわからない。どうして「よろしいでしょうか」ではないのだろう。
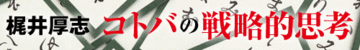
第13回
「お疲れさま」(公開終了)
「お疲れさま」。こんな言葉をかけあう光景をよく目にする。私はこの言葉があまり好きになれず、かねてから気になっていた。その理由を探ってみようと思う。
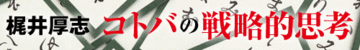
第12回
「やばい」(公開終了)
最近「これ、やばいです」という表現をよく耳にする。若者を中心にこの「やばい」という言葉の意味が変化を遂げているようだ。しかも、肯定の意味にも否定の意味にも使われるそうでとてもややこしい。
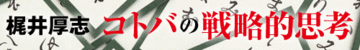
第11回
「格差」(公開終了)
格差という言葉が近年、頻繁に使われる背景には、平等性や公平性が欠けてきたという意識があるのだろうか。それならば、「不公平」や「不平等」という言葉の入った記述も増えていてよさそうである。
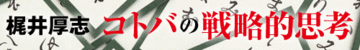
第10回
「情けは人のためならず」(公開終了)
「情けは人のためならず」という慣用句がある。そこには情けの見返りをどのように保障するか、という重要な論点があるが、これは同じ原則で成り立つ年金・保険問題に関しても言える。
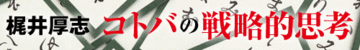
第9回
「遠慮」(公開終了)
一般的に「遠慮」とは、行動を控えることを指すが、文字どおり読めば「遠い先まで見通して深慮する」という意味である。それがなぜ「控える」ことにつながるのだろうか。
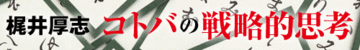
第8回
「一物一価の法則」(公開終了)
スーパーでできるだけ日付の新しいものをとろうと、棚の奥を覗き込む行為にはれっきとした経済学的理由がある。また一物一価の法則の正しさを示唆するのも、彼らのような人々なのだ。
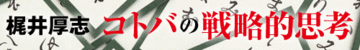
第7回
「とんでもありません」(公開終了)
「とんでもありません」という表現が使われることがある。「とんでもない」を丁寧に表現しようという気持ちはわかるが、言葉の感じはなんとなく変である
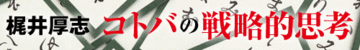
第6回
「していただいてもよろしいですか」(公開終了)
「していただいてもよろしいですか」という表現は丁寧な言い方だと思われているが、ときとして人を不愉快にさせることもある。なぜそうなるのかを、分析してみたい。
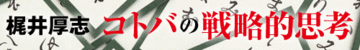
第5回
「博奕理論」(公開終了)
控除率16.7%の「チョボ一」に比べ、現代日本の公営ギャンブルはおおむね25%、宝くじなどはなんと50%だ。日本の公営ギャンブルはとんでもないチョボ一なのである。
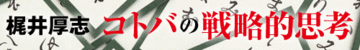
第4回
「わらしべ長者」(公開終了)
「わらしべ長者」が大儲けの話に解釈されるのは大変残念なことだ。ここには、交換による経済学的価値の創造という経済の基本原則が美しく表現されている。
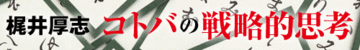
第3回
「ご説明させていただきます」(公開終了)
巷に溢れる「させていただきます」という言葉。文法の面から必ずしも誤りではないこの表現だが、蔓延する背景として、責任逃れ気質の広まりと無関係ではない。
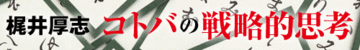
第2回
「ら抜き言葉」(公開終了)
連載2回目のテーマは「ら抜き言葉」。書き言葉においても「ら抜き」で書くほうが合理的なのではないか。そのような合理性を感じるからこそ、人は抵抗なく「ら抜き」で話すのではなかろうか。
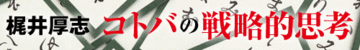
第1回
「よろしくお願いします」(公開終了)
連載第1回目のテーマは「よろしくお願いします」だ。ごくごく日常的に使われるこの言葉の中に潜む3つの戦略的思考(もしくは含意)を取り上げる。