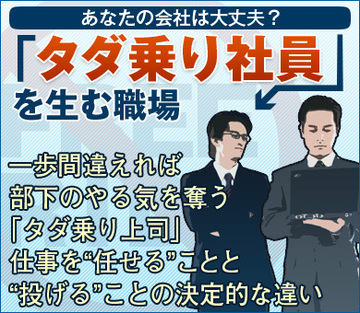渡部 幹
第12回
大学、会社、結婚など、日本は“籍”を持つことで安心を得る「堤防型社会」だ。これまではその価値観が、社会制度とマッチしてうまく機能していた。しかし、もはやそうはいかないことを若者は知っている。あなたは堤防の外に出られるか?
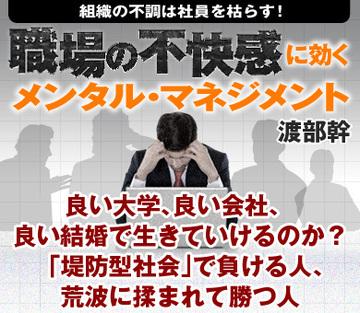
第11回
「新型うつ」を語り、周囲に責任を押し付け、甘えるタダ乗り社員が増えている。問題なのは、本当にうつで苦しんでいる社員にまで偏見の目が向けられることだ。職場を悩ませる「なりすましうつ」の実態と見分け方を考える。
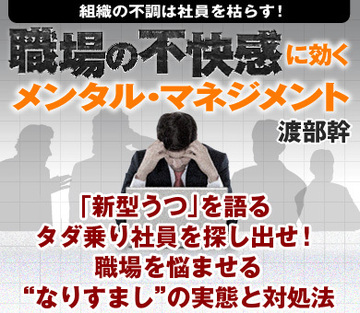
第10回
「頑張れば誰かが拾ってくれる」と考えるアメリカ人に対して、日本人は「どうせ頑張っても報われない」と考える。これは日本の労働規範が整備されていないせいだ。日本企業の社員は、自らポジティブな評判を広げる必要がある。
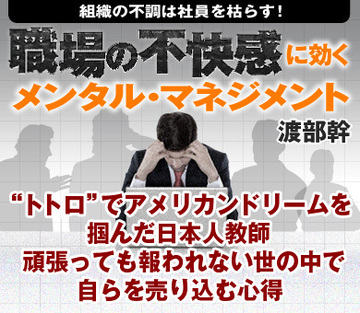
第9回
かつては、会社での縁が人生の縁になった時代があった。しかし、雇用の流動化が進む昨今、日本の会社員は人脈をつくることが困難になっている。増加する「無縁職場」の社員たちが人脈を広げるためには、どうしたらいいのか。
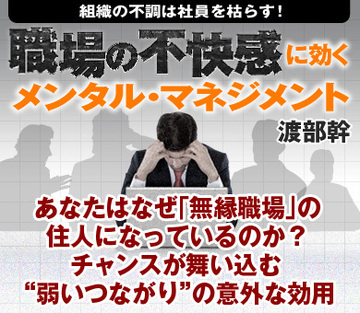
第8回
どうせ何をやっても無駄だ――。現在日本企業には、こんな無力感が蔓延している。無力感が漂う職場で、ビジネスがうまくいかないのは当然だ。閉塞状況を破るために、上司は部下を「賢いポジティブバカ」に育てなくてはならない。

第7回
米国とは違って日本の職場では、社内で評判が良い社員が必ずしも重用されるとは限らない。それは日米における人材雇用の流動性の違いに起因している側面が大きい。フェアで優秀な社員がステップアップできる環境を整える意義とは何か。
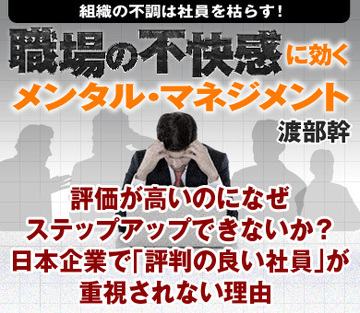
第6回
働くモチベーションの核、すなわち「キャリア・アンカー」は、人それぞれ違う。チームのパフォーマンスを上げるためには、各人のアンカーを認知し、適正な役割分担を考えなくてはならない。あなたの「心の錨」は、どににあるだろうか。
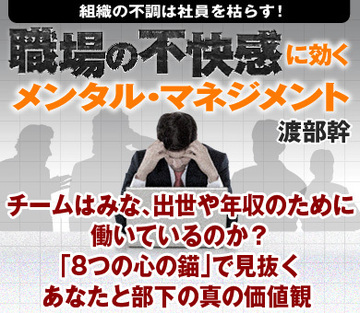
第5回
日本人を含むアジア人は、皆と同じことを重視する相互依存的な自己観を持っている。しかし最近の若手には、皆と違うことを重視する相互独立的な自己観を持つ人も多い。上司はこのタイプによって、部下への接し方を使い分けるべきだ。
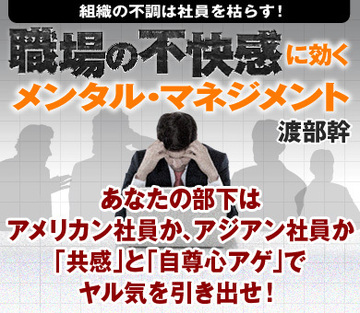
第4回
かつての日本では、軍部という最も「ムチ」が振るわれやすい環境においても、認知と感謝をもって部下を育てるという「アメ」の采配術があった。これは、今の企業社会においても有効だ。「伸びしろ」をほめないと、部下は育たない。
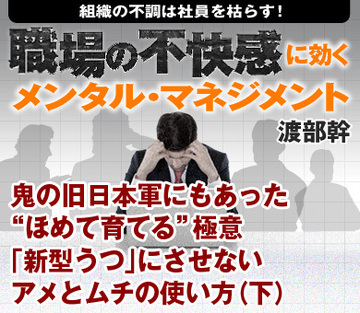
第3回
社員が滅多に会社を辞めなかった昭和時代と、雇用が流動化した現在とでは、上司が部下を叱る効果は様変わりしている。下手な叱り方をすれば若手の心を壊し、「新型うつ」にさせかねない。正しい「アメとムチ」の使い方を考えよう。
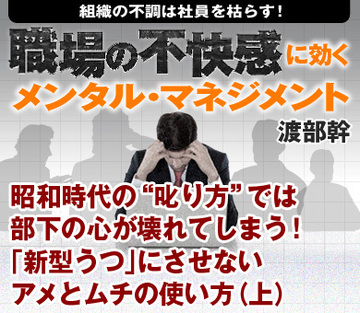
第2回
長期休暇をとっている若手は、職場に1人や2人は必ずいるもの。最近では、「新型うつ」「社会不安障害」の社員も増えている。その背景にあるのは、昭和の価値観を引きずったまま、若者を社畜化して使い捨てにする上司たちの存在だ。
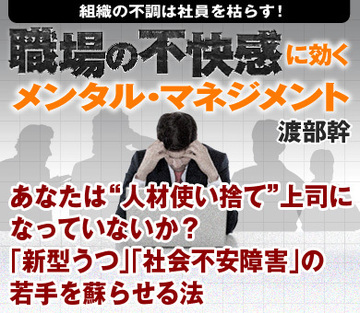
第1回
あいつは“ゆとり社員”だから――。日本の職場では、こんな言葉がそこかしこで聞こえてくる。しかし、そうした“レッテル貼り”が若手社員を本当にダメにし、「不快感」が蔓延する職場にしてしまう恐れがあることを、知るべきだ。
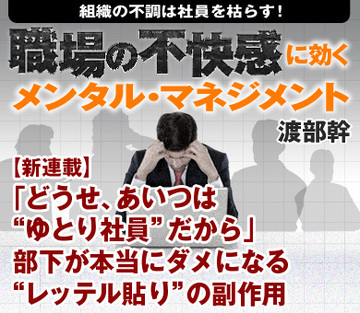
第43回・最終回
今や「タダ乗り」に対する世間の目は、以前とは比べ物にならないほど厳しくなっている。最終回は、タダ乗り社員を罰するのではなく、始めから出さないためにはどうしたらいいかを改めて考えてみよう。それは、タダ乗り問題の本質を問うことになる。
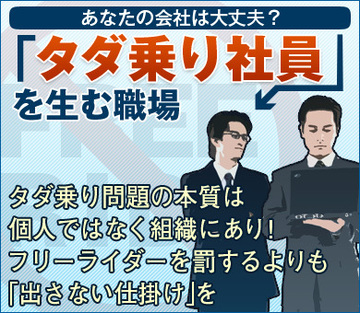
第42回
オリンパスや大王製紙などの有名企業で、経営者による深刻な不祥事が相次いでいる。その背景には、企業が陥りかねない普遍的なリスクが潜んでいる。それは「権威のリスク」と「集団のリスク」だ。タダ乗り経営者の出現をどうやって防いだらいいのか。
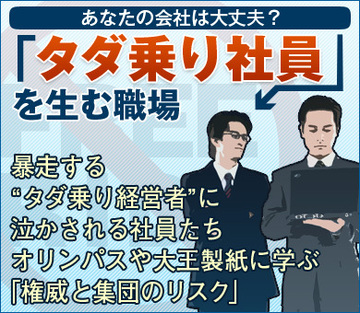
第41回
新進気鋭のコンサル会社「コーチングアワセルヴス」の創始者であり、高名な経営学者ヘンリー・ミンツバーグの義理の息子でもあるフィル・レニール氏と過ごした。かつて「不機嫌な職場」に悩んだ彼が、義理の父から得た「開眼の経営論」とは。
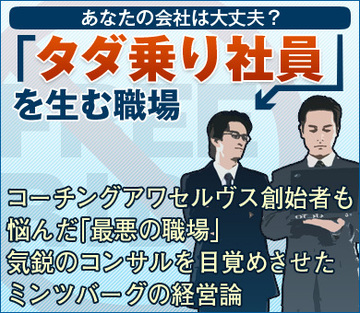
第40回
企業で「タコつぼ型職場」が増えるなか、まじめに仕事をする社員とタダ乗りしようとする社員の間で「心の格差」が広がっている。企業が社員のボランティア精神を高める上で本当に必要なことは、「知育」よりも「徳育」を重視することだ。
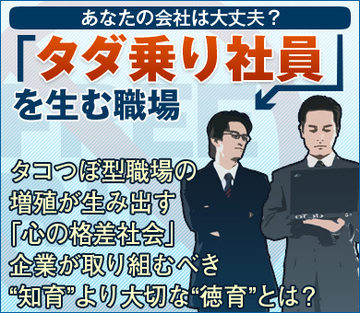
第39回
職場に迷惑をかける傍若無人な社員は、えてして「タダ乗り」扱いされ、排除されがちだ。しかし、そんな社員たちが突出した才能を持っている場合もある。日本企業と違い、米国企業では彼らをうまく組織に取り込む「人材活用」が重視されてきた。
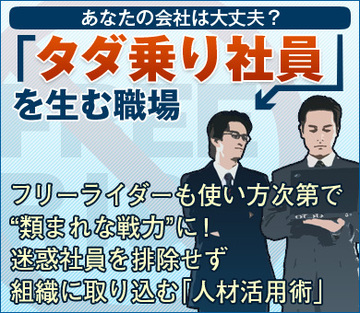
第38回
若手社員を「お客さん」扱いする企業が増えている。過剰サービス会社は、求め、甘え、頼ることに慣れ切った社員を増殖させる。その典型例が、根拠もなく「他人はバカだ」「自分はデキる」と信じて周囲と軋轢を起こす「クラッシャー型社員」である。
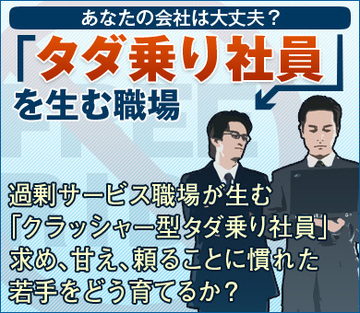
第37回
仕事をせずに高待遇を貪る社員が多いと、職場は「フリーライダー化の連鎖」に陥り、崩壊する。そうならないためには、社員が自分と会社との「フェアな交換」を自覚することが重要だ。実はそのヒントが、京都の鈴虫寺で日々行なわれる説法にあった。
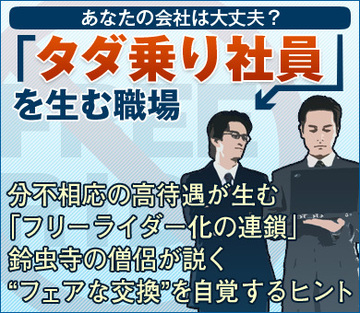
第36回
世の中には、部下に仕事を任せる上司と、仕事を投げるだけの上司がいる。前者は部下に信頼され、後者は「タダ乗り上司」として部下に嫌われる。その差はまさに「紙一重」である。本当のリーダーシップを発揮するためには、どうしたらよいのか。