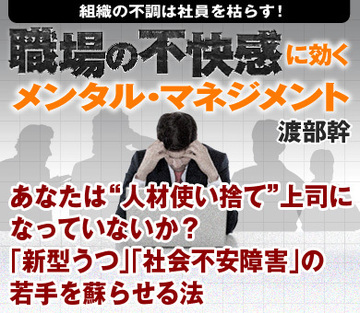「人が勝手に育つ」仕組み
があった昭和時代の企業組織
皆さんには、仕事を身につける上で「恩師」と呼べる人物はいるだろうか。いるならば、その人は幸福である。いないならば、幸福になるべくそのような人物を探さなくてはならないだろう。
新入社員として会社組織に入ってきたばかりのときは、どんなに優秀な人でも役には立たないのが当たり前である。その後、研修や実践を通して仕事の中身を理解し、スキルを身に着けていく。膨大なスキルを確実に、そして柔軟に身に着けていくためには、もちろん本人の頑張りが最も重要だが、それをアシストする社内制度や上司のコーチングも重要となる。
高度経済成長時代以来、業種や組織が細分化し、仕事上必要なスキルの種類も格段に増えている。そんなときに重要となるのが、きちんと仕事を「叩き込んでくれる」上司であり恩師だ。
このコラムですでに幾度か触れているが、バブル期以前の日本企業は、終身雇用制と年功序列制に基づく、長期的雇用関係が主であった。そのような制度の下では、新入社員が辞めるという事例は稀で、大抵は会社に骨を埋めるつもりで入社してくることが常だった。
こういった制度の下で、上司が部下に仕事を覚えさせる一番手っ取り早い方法は、「ムチ」を使うことである。これは、懲罰や叱責、減給など、本人にとって経済的、心理的に損になるフィードバックと言える。
「恩師」と呼ばれるような人は、そのムチの使い方が上手い。ひとことで言えば、「愛のムチ」を使うことができる人だ。