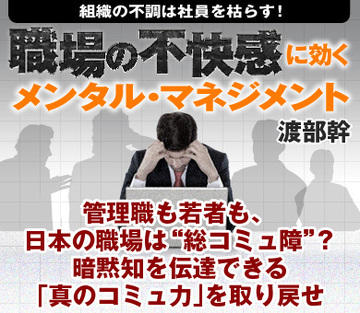渡部 幹
第32回
小学生でも英語、マレー語、中国語、タミル語を自由に話せる――。これが多言語文化圏であるマレーシアの現実だ。日本人が「国際的コミュ力」を身に付けるには理想の環境だろう。「おもてなし」を国際ビジネスに育てられるチャンスも見える。

第31回
イギリスから赴任してきた筆者の同僚がマレーシアで日本車を購入したところ、あまりにもルーズな顧客対応に振り回されたと聞いた。確かにマレーシアン・ウェイには辟易するが、その背景に見えるのは「日系グローバル化」の綻びでもある。
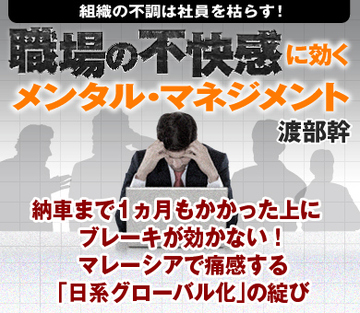
第30回
マレーシアのフォーラムに参加したときに感じたのは、ASEAN諸国の中国に対する警戒心だった。しかしミクロの面で見れば、中国人のネットワークづくりの積極性には感心するしかない。この点については、日本人も学ぶべきことが多い。

第29回
真のグローバル人材と呼べる人は、日本にはまだ少ない気がする。ビジネス英会話を習得することだけがグローバル人材の条件ではない。米国や英国の言語ではないローカル英語を学べば、創造力を養い、多文化性を身に付けることができる。

第28回
現在、マレーシアに赴任している筆者が研究しているのが、脳のミクログリア細胞が経済行動に及ぼす影響についてだ。これは、新しい研究分野であるニューロビジネスの分野に近い。いわば、ビジネスマンの意思決定を左右する大脳生理学である。
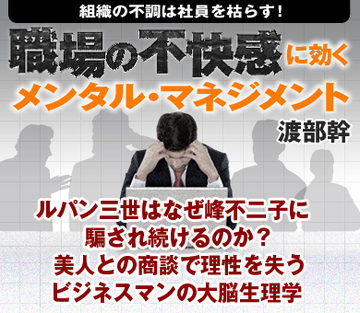
第27回
先月、マレーシアに赴任したばかりの筆者は、ビジネスにおける「文化の違い」には驚かされた。在庫がない掃除機を展示し続けるスーパー、水漏れ対応にテープを巻くだけのマンション業者など、日本企業ならやるはずのない対応ばかりなのだ。

第26回
かつて米国大学院に留学した筆者は、英語が堪能ではなかったこともあり、成績が低迷、一時は退学寸前まで追い込まれた。しかし、よき理解者となってくれた2人の教授のお蔭で再生することができた。なぜ筆者は頑張れたのか。それは「期待と認知」の効力だ。
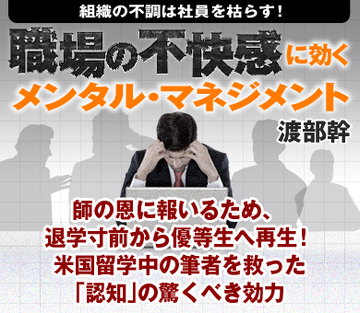
第25回
周囲が判断する社員のパーソナリティは、実はあまりアテにならない。職場を離れたその社員の素の顔を垣間見る機会が、今の日本企業では減っているからだ。「対人的情弱」に陥っている人事部は、真に使える社員をどうやって見極めるべきか。

第24回
仕事上でもプライベートでも話ができる友人は、職場で強力な武器になる。しかし、つながりが強すぎるとむしろ逆効果になりかねない。強いつながりか、弱いつながりかは重要ではない。本当に役立つのは「オープンでイーブンな関係性」だ。

第23回
職場を離れるときに不満をブチまける人と、最後まで周囲との関係に気を遣う人がいる。辞めるときにこそ、その人の本性が出るものだ。「評判重視社会」の現在、これはどちらが有利でどちらが不利だろうか。社会学的な見地から考えてみよう。
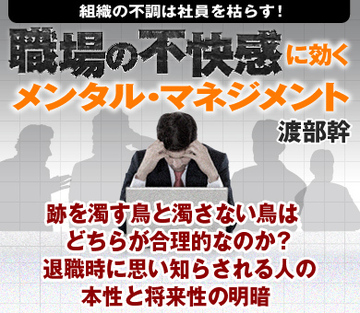
第22回
ある中堅企業の管理職は、退職する派遣社員の引き継ぎ業務を見て、仰天した。彼女の仕事の質量が、正社員の仕事の3倍に匹敵するほど高いものだったからだ。実は、こんな事例がそこかしこにある。真に必要な“人財”の損失を防ぐためには?
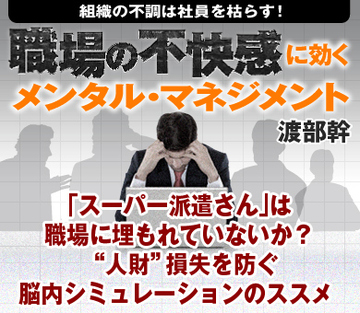
第21回
村上春樹氏が新作を出版し、発売わずか1週間ほどで100万部を突破する人気を博している。だが、氏の作品に描かれる主人公にはある種の「時代遅れ感」が漂う。今の日本人が求めているのは、共同体からの離脱ではなく、コミットだからだ。
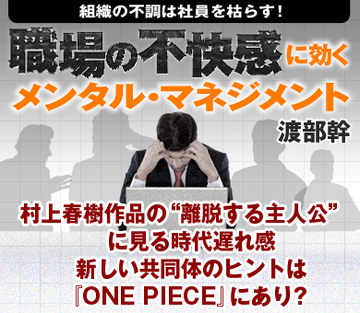
第20回
できるだけ面倒な業務はやりたくないという、無責任な社員が増えている。しかし、一概に彼らを批判することもできない。今は、仕事から学ぶ意義を見出せない時代だからだ。奮闘するチャレンジャー社員を潰さないためには、どうすればいいのか。
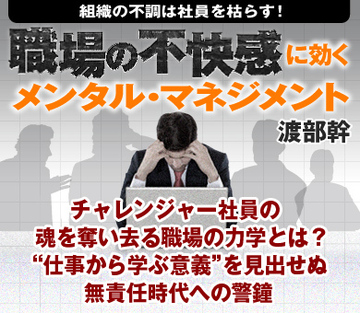
第19回
成果主義の失敗で不機嫌な職場が蔓延し、孤立主義の社員が増加するなか、多くの日本企業は新卒採用の際に「コミュ力」を重視するようになった。しかし、組織に従順な社員が「コミュ力」の高い社員ではない。「協力できる個人主義社員」こそが最も理想的なのだ。
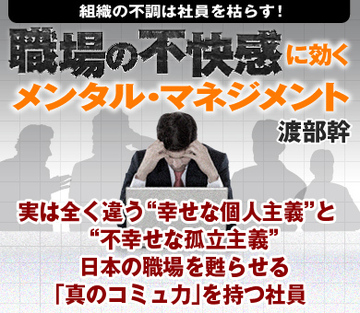
第18回
1人ぼっちで行動するほうが落ち着くという「ぼっち社員」が増えている。興味深いのは、彼らの多くが集団で行動する人たちを「キモイ」と思っていることだ。このことは、組織をダメにする集団意思決定が増えていることを暗示している。
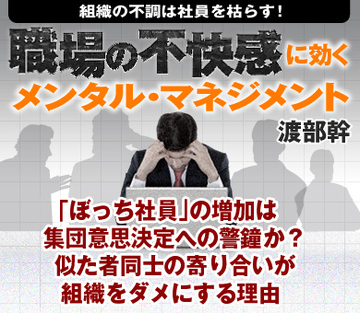
第17回
来日しているカナダ・マギル大学のヘンリー・ミンツバーグ教授のワークショップやインタビューに、参加する機会を得た。彼が唱えていたのは、米国流マネジメントが日本企業にも悪影響を与えている点と、コミュニティづくりの重要性だ。
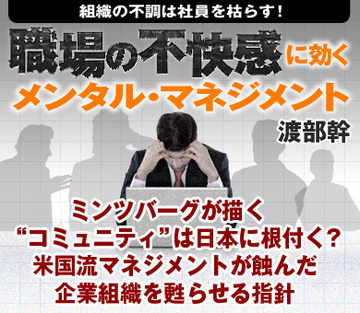
第16回
安倍政権が掲げるリフレ政策への注目が高まる一方、日銀の意思決定に対して疑問が唱えられている。社会心理学の見地から見ると、かつてケネディ大統領が「ピッグズ湾作戦」で陥った集団意思決定のワナに、日銀もハマッているように見える。
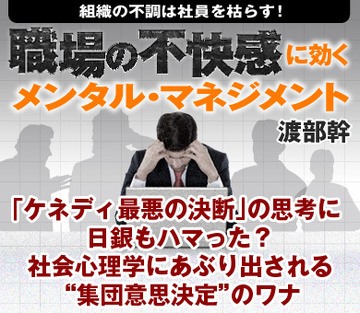
第15回
出張でマレーシアに行った際、インド人のタクシー運転手の言葉にハッと気づかされた。「日本のメーカーは違うよ。韓国や中国のメーカーと比べてもまだまだずっといいよ」。この言葉には、日本の組織を見つめ直すための示唆に富んでいる。
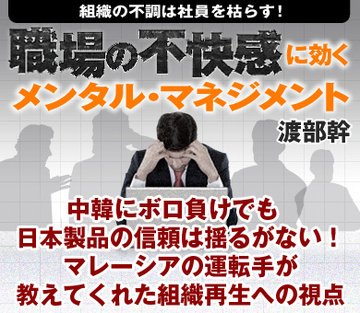
第14回
日本人のプレゼンの下手さやつまらなさは、一目瞭然だ。プレゼン後に質問が殺到すると、欧米人に喜ぶのに日本人はビビってしまう。こうした背景には、成功のためのチャレンジよりも失敗の回避が評価されるという日本社会の特性がある。

第13回
今、企業で最も重視される能力の1つがコミュニケーション力、いわゆる「コミュ力」だ。昔は業務に必要な職人技が暗黙知によって自然に継承されていたが、人間関係が希薄化した今、管理職も若者もお互いをわかり合えなくなっている。