
渡部 幹
第17回
職場のコミュニケーションを円滑化するために、飲み会は必要か。議論が分かれるところだが、肝心なのは飲み会に参加することではなく、コミュニケーションの内容と効率だ。飲み会に参加しなくても味方を増やす社員の「生き残り術」を考えよう。

第16回
タダ乗り社員が跋扈するのは、ブラック企業――。その考え方は間違いである。超優良企業にもフリーライダーはいるのだ。しかも彼らは「知性派」だけにタチが悪い。ある中国のプロジェクトでエリート社員が見せた、とんでもない言動を紹介しよう。

第15回
専務一派が社長を追い出した企業のクーデーター、そして1人の女子学生を巡る騒動の背景に横たわっていたセクハラ・ストーカーの闇。筆者がこれまで見聞きしてきた事例に照らすと、普通の人がブラック化する「コミュニケーションの罠」が見えてくる。
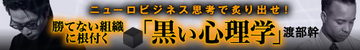
第14回
グローバルコミュニケーションの重要性が問われて久しいが、真のコミュ力とは異文化に染まらず相互理解を深めることができるコミュ力だ。これは日本の職場における世代間ギャップの解消にもつながる考え方だ。論じるべきは「文化的知性」である。

第13回
筆者は現在、ワシントンDCで行われている北米神経学会に参加している。その中で出た興味深い議論が、「物理的な温かさは人間関係も温めるのか」ということだ。実はこれ、現実のビジネスでもかなり参考になる考え方だ。具体的な場面を考えてみよう。
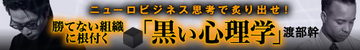
第12回
日本の男女平等度は、先進国中で最低レベルにあるという。だが、実際に日本の職場を見るとそんな雰囲気はない。このギャップを解き明かすヒントになる話がある。「女性にやさしい会社」でシングルマザーが言い知れぬ違和感に襲われたという話だ。

第11回
大手金融会社の人事部で働いていた女性が筆者に語ったこと、それはまさに、組織にはびこる黒い心理学の実例だった。問題は、当時幹部候補と言われていたエリート人事マンにまつわる闇にあった。彼は、なぜか優秀な人材ばかりを不採用にするのだ。
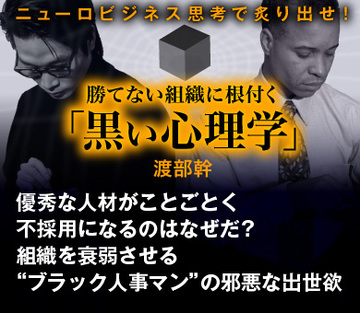
第10回
気づけば、入社数年目の女子や派遣社員を中心に仕事が回っている――。あなたの職場は、そんな状態になっていないだろうか。働かないオジサンが増える背景には、職場の構造的な病理もある。仕事の中心と組織図の中心が、ズレてしまっているのだ。

第9回
なぜ日本の多くの組織は、グローバル化に苦労しているのか。この問題提起は、日本の負け組組織を考える際も、実は大きな意味を持つ。マレーシアの小学校1年生の宿題を例に出しながら、グローバル化によって日本の組織はどう変わるべきかを考える。
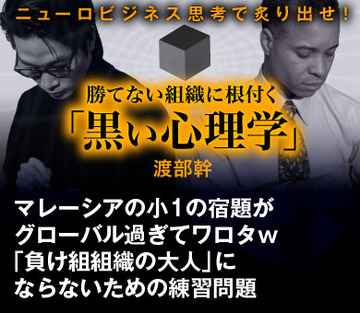
第8回
今の若手は、何かと言えば「ブラック企業」だと言い、自分たちが若いときほど熱心に働かないと上司は嘆く。バブル期に流行った労働ソングの歌詞を見てもわかる通り、実は企業のブラックさは今も昔も変わらない。違うのは「将来への希望の有無」だ。
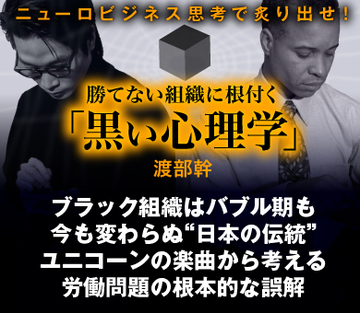
第7回
今回は趣向を変えて、グローバル時代のリーダーに求められる「白い心理学」をお伝えしよう。真に優れたリーダーとは、どんなタイプなのか。数多くのボスに仕えてきた有能な女性秘書へのインタビューから、「優れたリーダーの条件」を導き出す。
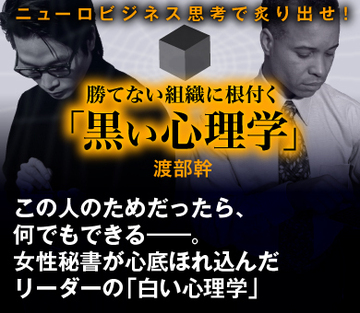
第6回
最近、日本にも「自己愛型」の社員が増えているように思える。そうした傾向は、組織内に様々な支障をきたす場合がある。たとえば、グローバル時代に必要とされる英語スキルの獲得だ。「自己愛型社員」は、なぜちっとも英語が上達しないのか。
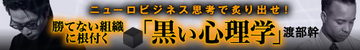
第5回
フリーライダーが世間の耳目を集めて久しいが、足もとで社員のタダ乗り問題はより複雑化しているようだ。あなたの職場に、頭もいい、人もいい、でも仕事ができない、という人はいないだろうか。そんな人には底知れぬ病みが潜んでいる。

第4回
根っからのワルい企業ばかりでなく、普通の職場が気づけばブラック化していると思しきケースは多い。背景には、社内の制度的ひずみと、それに伴う弱者へのストレスのつけ回しがある。うつ社員が溢れる職場は、あなたにも原因があるかもしれない。
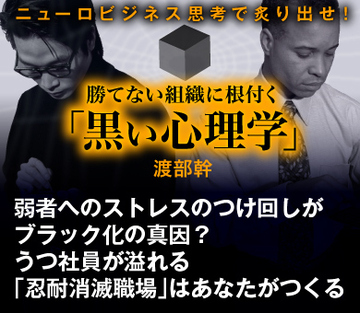
第3回
今の日本人には、他人との比較によって自信を失ったり、他者に対して優越感を感じたりする偏りが見られる。「自己高揚」と「自己卑下」という観点から、勝てないビジネスマンの「黒い心理学」を炙り出し、どうしたら勝てるようになるかを考えよう。
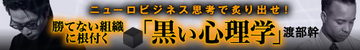
第2回
なぜ人はブラック企業を辞められないのか。その背景には、今の関係から他の関係に移る際に得られる「利益」の評価軸の違いがある。たとえブラック企業を辞められても、この評価軸の違いによって、成功する人と失敗する人の明暗が分かれるのだ。
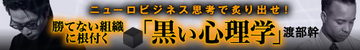
第1回
社員を疲弊させる組織には、「黒い心理学」が根付いている。ニューロビジネスという思考によって、心理学、大脳生理学的な側面から、「勝てない組織」の原因と再生法を考えていこう。連載第1回は、ブラック銀行で働く2人の秘書を題材にしよう。
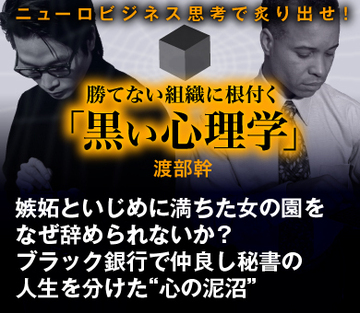
第35回・最終回
不機嫌な職場の増加を世代間ギャップのせいにする論調が目立つが、本当は各世代が生きてきた時代の違いにまで問題意識を掘り下げ、解決策を練るべきだろう。できる経営者やマネジャーは、常日頃からこの「なぜ?」を深く追求し続けている。
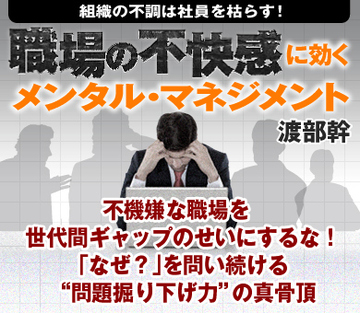
第34回
『半沢直樹』はなぜこれほどまでに支持されるのか。筆者はゲーム理論や神経科学の見地から、主人公のキャラクター設定に興味深い点を見出している。組織から排除されかねない「倍返し」を繰り返す半沢は、なぜヒーローたりえたのだろうか。
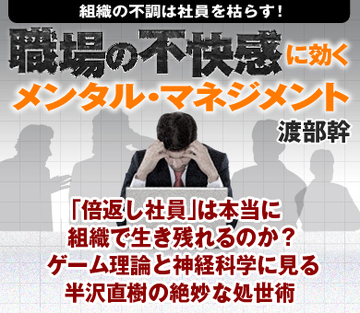
第33回
筆者が研究している「ニューロビジネス」という分野は、消費者の購買決定の際の脳の働きから、どんな宣伝が効果的かを分析するもので、実際のビジネスにも役立っている。マーケティングの現場において、その効果には侮れないものがある。
