
山崎 元
第95回
投資をするうえでは、総選挙のような大きなイベントの影響がどうしても気になるしかし、将来の政策のように特別な情報を自分だけが知っている場合でない限り、投資の材料にはなりにくい。。同様に、株式でも外国為替でも、マクロの経済イベントや政治などを材料として儲けるのは大変だ。

第97回
三井住友と大和の合弁解消に際しては、銀証融合の現状について当事者から真反対の見解が示されている。筆者は、現状認識は一体化を世界の潮流と見る三井住友の奥頭取が正しいと思うが、見識としては弊害を指摘した大和の鈴木社長を支持したい。
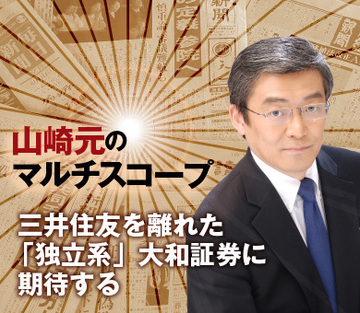
第94回
運用資産の配分比率の決定は、教科書的には、資産の期待リターンとリスクとを基に最適に計算されるべきだ。この際に、国内株式や外国株式といった資産分類ごとの期待リターンを求めることが特に難しく、苦労する。

第96回
過大なリスクテイクを誘引しバブル発生の原因になったとして、金融マンの報酬制度が批判されている。確かに急所を突いた指摘もあるが、金融マンの報酬を抑えたとしても、現実にはバブルは起こり得る。どうすればよいのか。
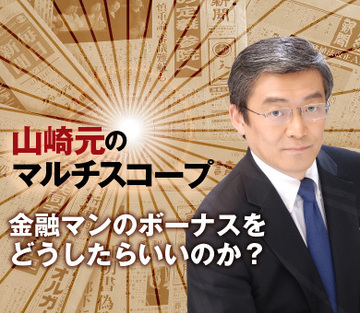
第93回
日本悲観論の中で最も影響力のあるのは財政破綻論だろう。日本政府の債務はGDPの170%以上で、日本の破綻は不可避だという。確かに日本政府の財政は普通ではないが、財政破綻の危機にあるとは決めつけられない。

第95回
メディアの自民党敗因分析は釈然としない。小泉改革の実行が官僚に丸投げで停滞したことが総括を難しくしているのか。民主党には、市場原理主義を敵視するのではなく霞ヶ関のムダづかいの削減で「小さな政府、大きな福祉」を目指して欲しい。
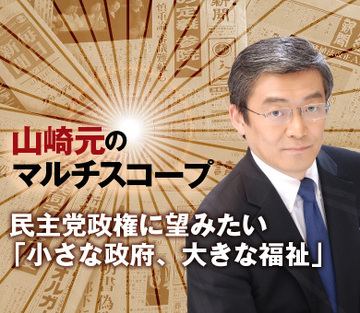
第92回
この問題の時効が何年なのか知らないし、時効が過ぎても悪いことは悪いのだが、筆者がかつてかかわった悪事の思い出について書く。筆者はある生命保険会社の特別勘定運用部で働いていた。

第94回
選挙の情勢分析データが候補者に漏れているケースが相当あるようだ。特に出口調査の漏洩は投票行動への影響だけでなく、投票のプライバシーに対しても問題がある。そもそも投票日の出口調査には社会的なメリットを見出し難い。
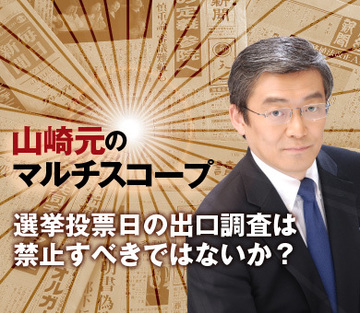
第91回
主に株式投資についてだが、「長期投資」のあれこれについて論点整理しておきたい。長期の株式投資が確定利付きの運用よりも絶対に儲かるというのは歴史的事実か?

第93回
筆者は戦後生まれだが、終戦記念日前後の報道を見て、昔を振り返ってみたい気分になった。といっても、経済の話で、それも近年の出来事だ。読書用のガイドも兼ねながら、金融危機の原因を考えてみよう。
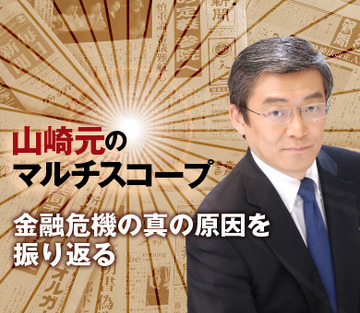
第90回
あらかじめ謝っておこう。筆者も例外ではないが、おカネの運用についてコメントする人は、「運用のやり方を間違えると大変なことになる」と過剰に言いたがる傾向がある。「大変申し訳ない」。しかし、世間を見渡すと、おカネの運用に関する正しい知識を備えた人はごく少数であるにもかかわらず、運用が失敗したことで人生が破綻した人は案外少ない。その原因は、「人的資本」と「人的負債」の柔軟性にあるようだ。

第92回
古くから「国策に売り無し」という相場格言がある。ただ、それは国策に逆らって空売りすると危険という戒めで、「買うべし」と言い切っているわけではない。「エコ」は本当にこれからも買えるテーマなのか、検証した。
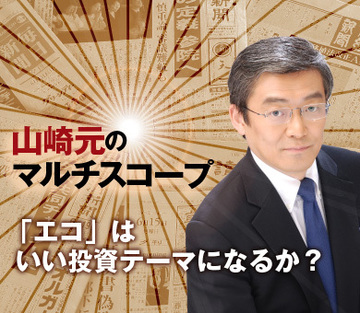
第89回
ファンドマネジャー経験者が運用会社をつくろうと思うと、十中八九は運用体制に注意が向く。サラリーマン時代に、勤務先の会社の運用に対する態度に不満を持っていると、いざ自分で独立となると運用に力が入る。

第91回
自民党のマニフェストは、民主党の公約を意識してか、これを批判ないし相殺しようとする政策が多く、文書のあちこちから、「野党っぽい」臭いが立ち上っている。民主党のマニフェストも確認しながら、中身を点検してみよう。
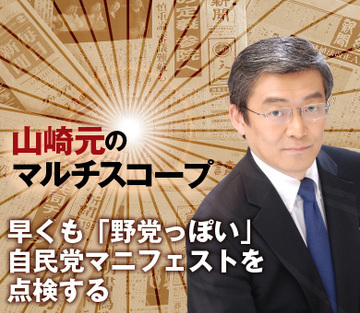
第88回
昨年度の公的年金の運用損失が約10兆円となったことを受け、舛添要一厚生労働大臣は7月3日の閣議後の会見で「(年金資産の)15分の1か10分の1をファンドにするなど、少しチャレンジしてもいい」と述べたという。大臣が言う「ファンド」が国家ファンド推進派の想定するヘッジファンドや投資ファンドのようなものなら、これは運用業界にとって巨大なビジネスだ。

第87回
ここのところ、個人を主な消化対象とした社債の発行が増えている。「個人向け社債」という言葉もある。しかし、一般論として、社債は個人のおカネの運用対象として適当だとは思えない。

第90回
さて、民主党への政権交代に現実味が出てきてた現在、注目のマニフェストだ。27日の夕方には全文がダウンロードできたので、同党が重視する生活・経済関係の政策を並べた「5つの約束」に沿って見てみよう。「5つの約束」のテーマは、民主党が挙げた順に、(1)ムダづかい、(2)子育て・教育、(3)年金・医療、(4)地域主権、(5)雇用・経済、だ。
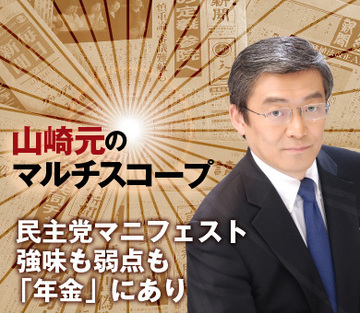
第86回
ここのところ、個人を主な消化対象とした社債の発行が増えている。「個人向け社債」という言葉もある。預金よりも明らかにいい利回りになっており、発行主体によっては、2%台後半くらいから5%前後くらいのものもある。株価の変動のようなかたちでリスクを気にせずに、この程度の利回りが得られるなら魅力的だと考える個人がいるかもしれない。実際に人気を集めている銘柄もある。しかし、一般論として、社債は個人のおカネの運用対象として適当だとは思えない。

第89回
日本航空(JAL)に関しては「そこまでやるのはどうなのか?」と思うことが二つある。一つは公的支援であり、もう一つはその支援の条件とされる企業年金改革に含まれる同社OB(退職者)への年金支給削減だ。
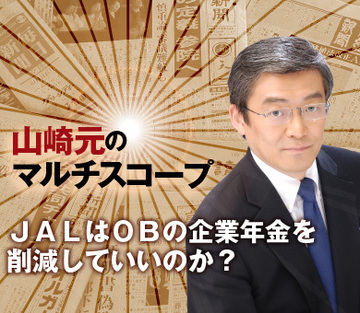
第85回
債券運用や外国為替は競輪に似ていて、株式投資は競馬に似ている。前者では政策や市場参加者の行動を、利害を考慮しながら「展開を読む」ように考えることが必要なのに対して、後者では影響する多くのファクターのなかから個々のケースで決定的な役割を果たすものを見つけ出す選択眼が要る。状況と着眼点の組み合わせはそれぞれだが、今回は銘柄のカテゴリーを分けて、そのカテゴリーごとに決定的に重要なポイントを着眼点とする考え方をご紹介しよう。
