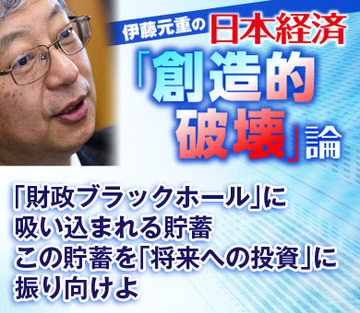伊藤元重
第17回
経済成長というと、既存の企業や産業が生産性を高めるというイメージがある。しかし実際は、生産性の低下した産業から、高い生産性を期待できる産業に資本や労働が移行できるかが重要なカギとなる。
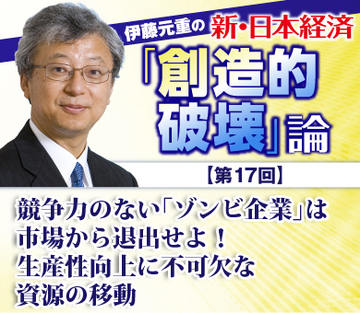
第16回
なぜ日本では「革新型」のイノベーションが生まれにくく、米国の後塵を拝しているのか。それは日本のベンチャー企業に特有の「再チャレンジの難しさ」にある。日本の起業家が、何度でも挑戦できるようにするには何が必要か。
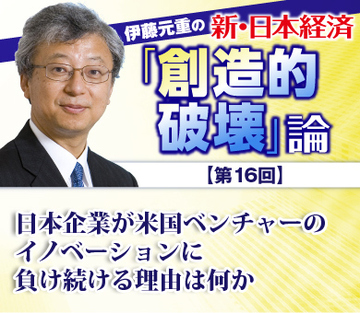
第15回
アベノミクスの成長戦略にも盛り込まれている「GNI(Gross National Income:国民総所得)」という概念は、これからの経済成長を考える中で重要な意味を持ってきている。その定義とGNIを増やすための課題をまとめる。
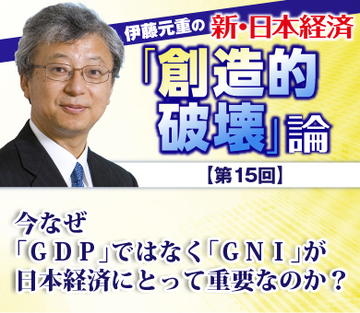
第14回
米国FRB(連邦準備制度理事会)がQE(量的緩和)政策からの出口を探ることが、市場に大きな影響を与えている。日本の金融市場をその影響を受ける。だが日本のアベノミクスは何ら変更する必要はなく、むしろ、これまでの方針をさらに推し進める必要がある。
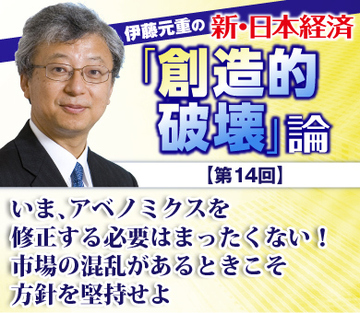
第13回
アベノミクスの金融政策は、予想や期待という微妙なものに働きかける政策だった。そのためにも、あえて次元の違う大胆な金融緩和が必要だった。同様に成長戦略が成功するためには、アベノミクスが企業の予想や期待を変えることに成功するかにかかっている。
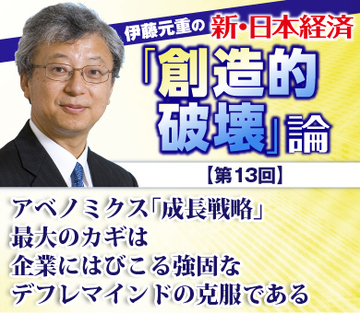
第12回
米国のFRBが行ってきたQE(量的緩和)政策がいよいよ出口戦略を探りだしたとの見方が出始めている。これは日本での金利上昇の原因となるのか、それともさらなる円安なのか、あるいはその組み合わせなのか?米国の動向にも気を配る必要がある。
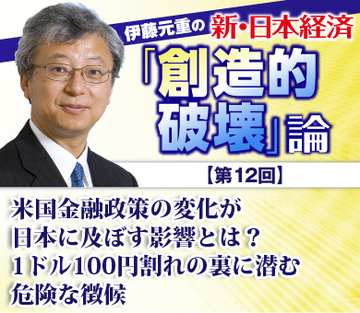
第11回
言うまでもないが、今回の長期金利の大きな変動のきっかけをつくったのは、黒田東彦日銀新総裁のもとでの大胆な金融緩和策である。なぜ、黒田日銀はこれまで日銀が手を出さなかった長期金利の購入を決めたのか。そしてそれは、市場にどんな影響を与えているのか。
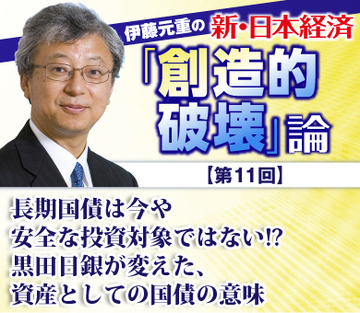
第10回
長期金利に世の中の関心が集まりつつある。日本銀行が大胆な金融緩和を行い、長期国債を大量に購入する。その動きを受けて、長期金利が大きく変動し始めたのだ。長期金利を決める重要な要素について論じたい。
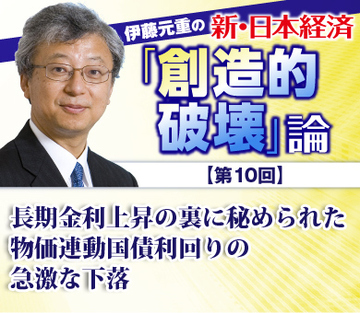
第9回
日本が「失われた20年」という罠に陥ってしまったのは、大きな経済環境の変化に対応できていないからだ。アベノミクスの成長戦略に求められることは、経済制度や産業構造の変化のスピードを速めることだ。
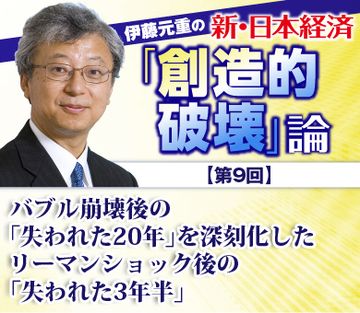
第8回
今、世界のどの地域を見ても、大国が参加した巨大な経済連携への動きが顕著である。地域経済協定は近隣国との限定的な存在から、世界全体の通商ルールを決める中心的な存在になりつつある。
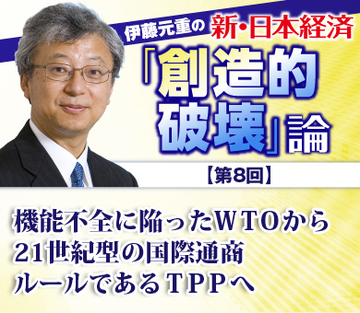
第7回
政府は、日本がTPPに参加することで約3兆円の経済利益が期待できるという算出結果を発表している。しかし、これは非常に保守的に見た結果である。新しいアイディアを積極的に採り入れた試算では、相当に違った数値が出てくる。
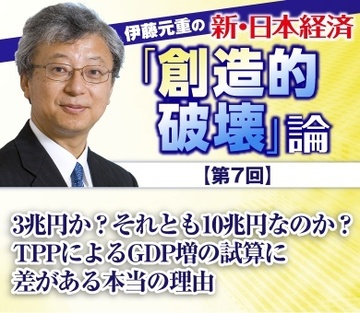
第6回
TPPに参加しても、自動車の最大市場である米国の関税の壁が取り払われるのには相当な時間がかかりそうである。自動車業界にとってメリットは非常に小さいのではないか、という議論が出始めている。果たしてそうだろうか。
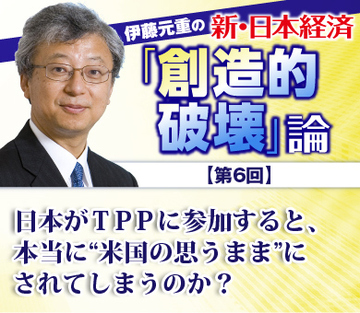
第5回
日本のエネルギーの将来は、再生可能エネルギーを抜きにして考えることはできない。再生可能エネルギーの不確実性を軽減するためには、コスト削減と同時に電力ネットワークの広域化・分散化など、様々な課題をクリアしていくことが必要である。
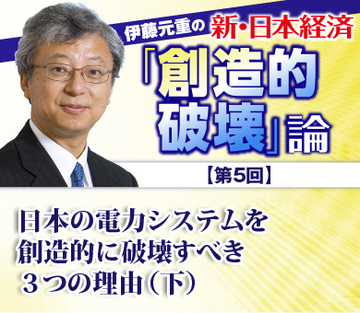
第4回
電力システム改革案が4月2日に閣議決定された。わたしは電力システム改革専門委員会の座長として今回の案をまとめる立場にあった。なぜいま電力システムの改革なのか、過去、源氏あ、未来に分けて考えて議論してみよう。
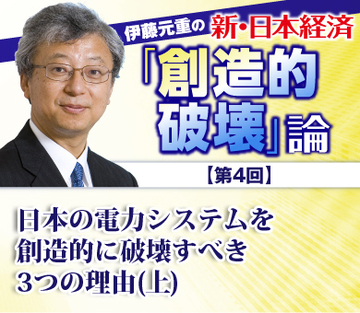
第3回
黒田日銀が初回の金融政策決定会合で「異次元金融緩和」を決めたことで、市場は激しく反応した。世界の注目を集めるインフレ目標政策は、はたして2年で2%の物価上昇率を実現できるのか?
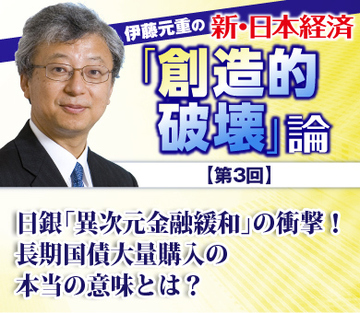
第2回
アベノミクスの最大の懸念材料は国債暴落と金利急騰。だが、物価上昇率が2%程度で、金利上昇も緩やかなら、企業も家計も必ずや支出を増やす。そのメカニズムを明らかにしよう。
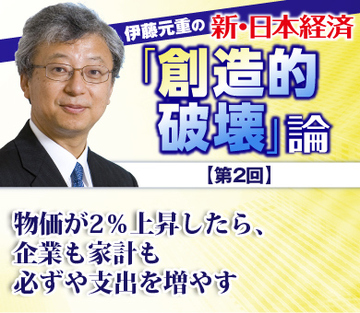
第1回
好調な滑り出しを見せた安倍政権の「アベノミクス」。はたして期待先行から実体経済の回復へとつなげることはできるのか?現政権の経済財政諮問会議議員をも務める著者が、日本に向けてリアルタイムに直言する新連載。
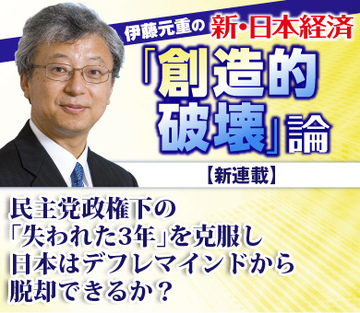
最終回
新政権の課題はマクロ政策、成長政策、財政健全化政策の三つをいかに調整していくかだ。さらに、GDPの大宗を占める国内サービス産業のイノベーションこそが、日本経済活性化のカギを握っている。
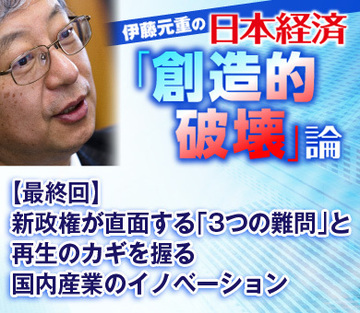
第25回
消費税率を10%に引き上げたくらいでは、日本の財政状況は改善しない。支出・収入両面の改革が必要だが、改革が遅すぎれば財政は破綻、速すぎる改革は政治的に導入困難だろう。長い道のりをかけて改革を続けていくしかない。
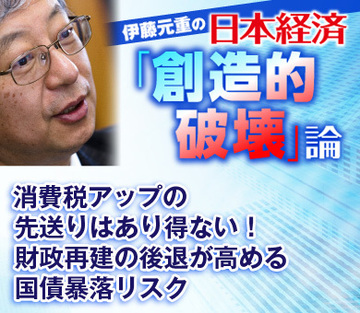
第24回
日本には潤沢な貯蓄があるが、大半は財政赤字というブラックホールに吸い込まれている。貯蓄率が低下に向かう今、この状況を打破して将来に向けた投資にを振り向けないと、日本は衰退してくばかりだ。