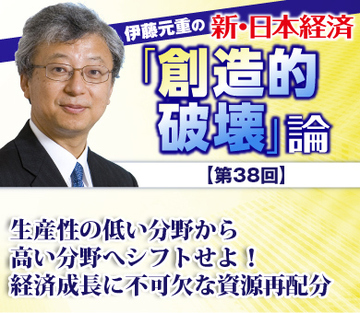伊藤元重
第57回(最終回)
アベノミクスは想定以上の好スタートを切った。しかし、議論されてきたのは、主として供給サイドの政策である。これから求められるのは、民間部門の需要サイドからの変革である。
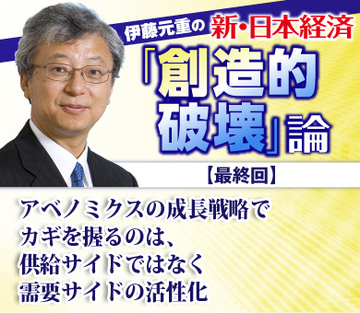
第56回
世界の多くの国で電力料金の自由化が進められているのは、規制料金の弊害をできるだけ排除したいという狙いがあるからだ。日本でも大口電力から料金規制が撤廃されてきたが、今後はこれをすべての電力料金に広げていくことになる。
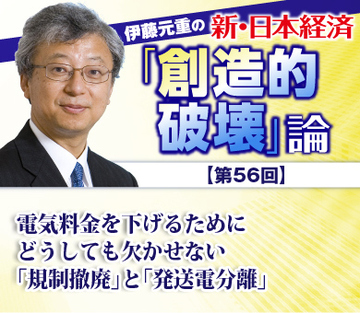
第55回
現在の一連の電力市場の動きで興味深いのは、地域を越えた一般電気事業者(旧来の地域大手電力会社)同士の競争が促進されようとしていることである。特に、東京電力管内で積極的な動きを見せている中部電力が気になる。
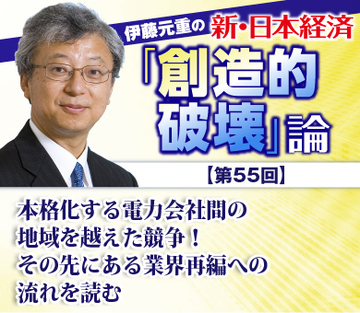
第54回
電力自由化を議論するうえで、原発が停止中の状況を考えると、電力を安定的に供給するための「需要調整(ディマンド・コントロール)」が重要となってくる。電力を節約した事業者がその節約分の権利を「ネガワット」として電力会社に売ることができれば、事業者のモチベーションにもなる。
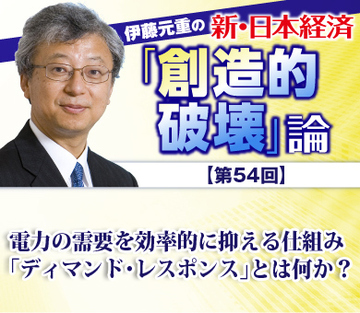
第53回
電力小売の自由化をしても料金が下がらないと主張する電力業界関係者の主張は、説得力がない。たとえば航空業界の自由化を議論していた時、今日のLCCの台頭と、顧客にとって自由で幅広い料金設定が実現するとは思われていなかった。電力業界も先に自由化を行い、異業種の新規参入と新しいビジネスモデルの登場を待つべきである。
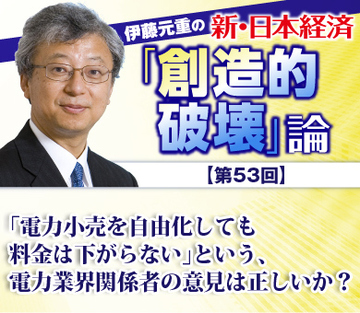
第52回
電力小売市場へさまざまな企業が参入を目指している。発電事業に既存の電力会社以外にガス会社などが参入しているが、カギになるのは、既存の電力の送電網の分離と、電力メーターの情報の解放だ。それにより新しいサービスの導入が加速する。
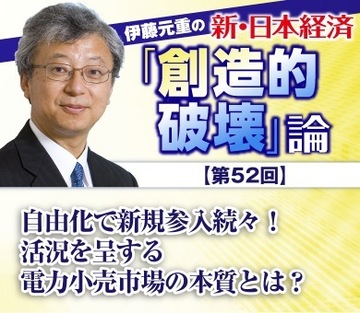
第51回
来年の通常国会で発送電分離(アンバンドリング)を盛り込んだ法案が審議されることになっており、いよいよ発電や小売の分野でより大胆な市場原理を導入しようという議論が活発化しそうだ。今回は、宅配便や情報通信分野でのアンバンドリングの先行事例を検証してみたい。
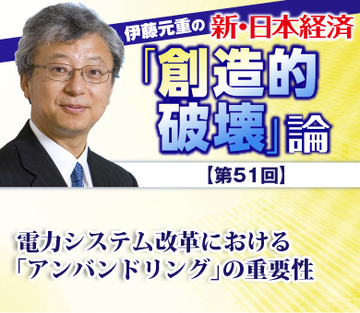
第50回
今回から、医療と並んで日本の成長戦略のもう一つの重要な産業である電力、エネルギー政策を取り上げる。福島の原発事故から3年が経つが、電力システムの改革はこれから数年が勝負だと言っても過言ではない。
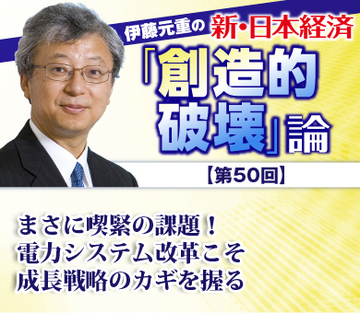
第49回
日本の医療における情報システムの活用については、評価する声よりも問題点を指摘する声のほうが圧倒的に大きいように思える。情報システムの活用は、産業としての日本の医療の改革を進めていくうえで重要なカギとなるだろう。
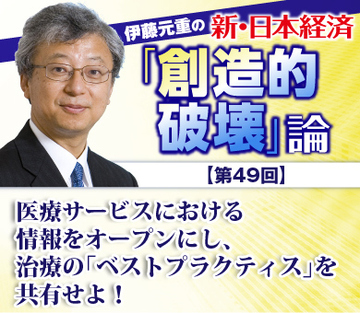
第48回
医療制度改革を進めるにあたり、地域密着型医師GP(General Practitioner)の役割が重要度を増している。高度な専門性と地域の患者を考慮した長期的な医療ケアの両立がGPには求められる。GPの活動を支援する仕組みづくりが必要だ。
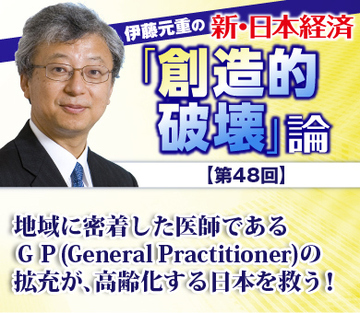
第47回
医療は典型的なサービス産業である。品質が高くて費用が安い医療を受けるために、医療機関への「フリーアクセス」を制限することが重要なカギになる。そのためには「かかりつけ医師」の利用を促進し、専門医へのアクセスを制限することが重要である。
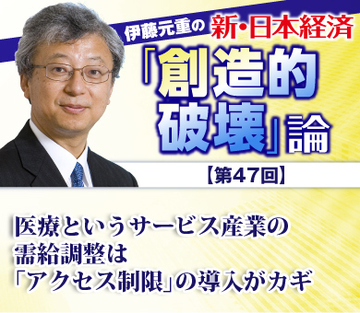
第46回
時々氾濫する川沿いに家を建てないように、政府は「堤防を作らない」と宣言した。しかし誰かが家を建ててしまえば、政府は膨大な費用をかけて堤防を作るしかなくなる。これは社会にとって最悪の展開だ。この例えと同じことが、日本の医療現場で起きている。
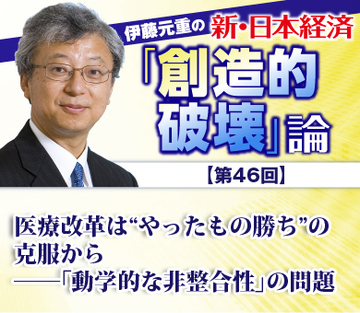
第45回
市場メカニズムをいかにうまく活用するか。それが日本の医療を改革するうえで欠かせない論点である。混乱を招くだけの乱暴な市場メカニズムの導入ではなく、複雑な医療システムを好ましい方向にうまく導いていく市場メカニズムが求められる。
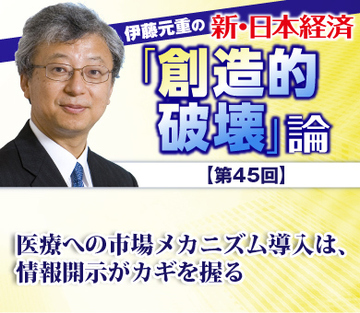
第44回
前回とりあげた医療供給体制の事例もそうだが、医療や介護の分野では、通常の市場でなら当たり前の需給のバランスが取れていない。これを是正することが、資源配分の効率性につながる。今回は、ジェネリック薬品の利用が進まないことと、救急車の過剰利用について取り上げる。
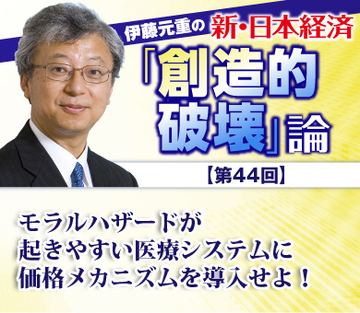
第43回
医療供給体制の調整は、日本の医療コストを下げるうえで決定的に重要な課題である。病床数は、高度医療に対応する高価な病床が異常に多い「ワイングラス型」の分布を示す。この構造を見直していくには、政府が規制するか、市場原理が働くようにするか、どちらかしかない。
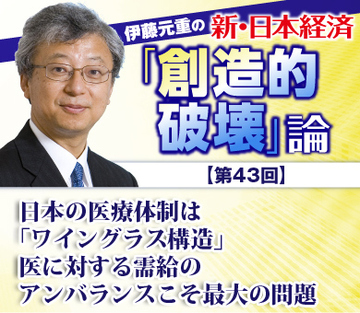
第42回
今回から、成長戦略の議論をセミマクロのレベルに広げたいと考えている。まず医療・介護の分野から取り上げることにしたい。感情的に抵抗する意見はあるが、医療・介護を産業としてとらえ、将来にわたって制度を維持していくための方策を考えていきたい。
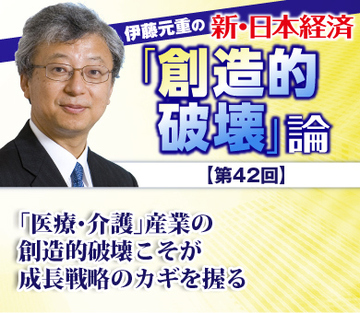
第41回
今回は、日本のTFP(全要素生産性)を引き上げるために必要なもう1つのチャネルである「集積効果」を取り上げたい。産業のサービス化が進む中で、大都市における異質な産業の融合によるシナジー効果が経済発展の重要な要素となる。
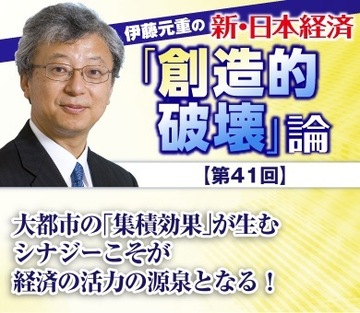
第40回
米国の経済学者ハーヴェイ・ライベンシュタインは、独占などに潜んでいる非効率性を「X非効率」と呼んだ。独占企業や規制で守られた企業が持っている、外から見えないさまざまな非効率性のことだ。X非効率の解消で、産業内資源再配分の効果はさらに高まる。
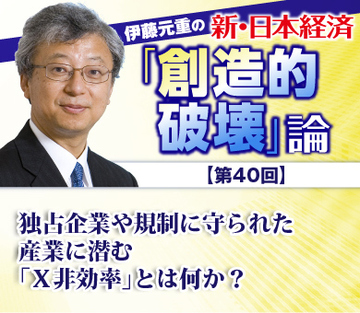
第39回
日本のTPP参加による経済効果は、日本政府の発表では約3.2兆円であった。小さくもないがそれほど大きくもない。対して、米国ブランダイス大学のピーター・ペトリ教授らが出した試算結果は、2035年までの10年間で少なくとも100兆円前後と非常に大きい。この違いの理由は何か。
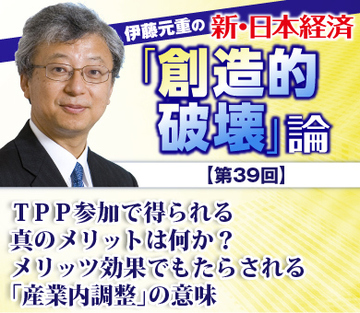
第38回
日本の産業の生産性を高めていくうえで重要なのは、資源の再配分である。とくに、同じ産業内で、構造的な理由から競争力が低下した生産者から、競争力の高い生産者へ資源を再配分することが求められている。