上田惇生
第313回
じつはわれわれは企業とその機能が何であるかを知っている
『マネジメント』とは、54年の名著『現代の経営』によりマネジメントの父とされるに至ったドラッカーが、その後20年の企業研究の成果を注ぎ込んだマネジメントの百科全書ともいうべき大著である。
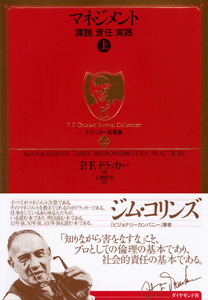
第312回
「理論は現実に従う」したがってグローバル企業は自らの道は自ら探るしかない
第二次世界大戦後、多少の所得と情報が得られただけで、世界中が同一の需要パターンを発展させた。自動車、医療、教育、テレビ、映画が世界共通の需要となり、世界は一つのグローバルなショッピングセンターとなった。その結果…。
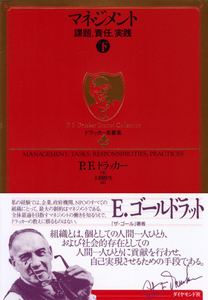
第311回
知識労働の生産性向上は業種・職種にかかわらず至って簡単なはずである
ドラッカーは、今日の学校の先生の生産性が、100年前の先生の生産性を超えているとはとても思えないという。ドラッカーによれば、知識労働の生産性を上げる方法は、業種・職種にかかわらず、ほぼ共通し、かつ至って簡単だという。

第310回
技術のダイナミクスを理解せよ技術が製品や産業を生み出しそれが文明の発展を加速させる
ドラッカーは、まず、いかなる技術の変化が、いつ頃起こりそうかを知る必要があるという。もちろん技術の変化の日程は、あらかじめ知りうるものではない。しかし、かなりのことはわかるはずだという。

第309回
リーダーといえども他の者の範となるには自らの得意を知る必要がある
ドラッカーは、リーダーたる者は、なすべきことからではなく、なされるべきことから考えよとさえいう。なすべきことを考えよというと、安易に、なしたいことから考えてしまうからである。

第308回
予期せぬ成功というものは天からの贈り物である無視すれば誰かが持ち去る
成功したイノベーションをしらみつぶしに調べ、それらの契機となったものを分類したところ、いちばん多かったのは発明・発見ではなかったという。それは予期せぬ成功だった。

第307回
規模のメリットが消えた大企業であるにもかかわらず頑張るにはどうしたらよいか
有能な人材の確保については、中小の組織が負っていたハンディが消えつつある。特に、大企業への就職が終身の保障を意味しなくなったために、中小の組織が有能な若者の選択の対象になった。

第306回
経営者が成果を上げるには8つの習慣を身につければよい特別の能力はいらない
経営者が成果をあげるには、近頃の意味でのリーダーである必要はない。これまで会ったCEOのほとんどが、いわゆるリーダータイプではない人だった。彼らが成果をあげたのは、8つのことを習慣化していたからだ。

第305回
真に新しいものは市場調査することはできないモニタリングするしかない
ドラッカーは、真に新しいものには、イノベーションを行なった者や企業家には想定できなかったニーズや市場が必ずあるという。それはほとんど、自然の法則といってよい。

第304回
完璧な組織構造はないある程度の問題は覚悟しておく
組織に欠陥があるときに表れる症状にはどのようなものがあるか。ドラッカーは、会議が多過ぎるということは、仕事の分析や仕事の大きさが十分でなく、仕事が真に責任を伴うものになっていないからだという。
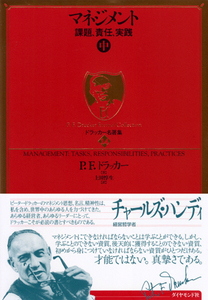
第303回
企業とは経済的な存在であり社会的な存在でありかつ理念的な存在である
ドラッカーとは、「今日の転換期の到来を予告した現代社会最高の哲人」(ケネス・ボールディング)であると同時に、体系としてのマネジメントを確立しマネジメント手法のほとんどを生み出したマネジメントの父である。

第302回
成果を上げて成長するために自らの強みを知って自らをマネジメントする
「誰でも、自らの強みについてはよくわかっていると思う。だが、たいていは間違っている。わかっているのは、せいぜい弱みである。それさえ間違っていることが多い。しかし、何ごとかをなし遂げるのは、強みによってである。弱みによって何かを行うことはできない」

第301回
成功するイノベーションは3つのタブーを注意深く避ける
ドラッカーは、イノベーションに成功するには避けるべきタブーが3つあるという。それはちょうど、イノベーションに成功するための心得を反対側から見た注意事項でもある。

第300回
イノベーションは企業家の道具イノベーションに成功するには3つの心得がある
ドラッカーは、イノベーションに成功するには、3つの心得が必要だという。いずれも当たり前のことでありながら、しばしば無視される。

第299回
問題はすべて複雑であるあらゆる視点から見るにはあらゆる異論を必要とする
問題は、すべて複雑である。あらゆるものが、あらゆるものに、複雑に絡み合っている。あらゆる視点から見るには、あらゆる異論を必要とする。

第298回
企業をはじめあらゆる組織が社会のための機関であるその組織の機関がマネジメント
あらゆる組織が、人を幸せにし、社会をよりよいものにするために存在する。ドラッカーは、「そのようなことは考えたこともないと言える組織は、修道院とギャングだけだ」という。
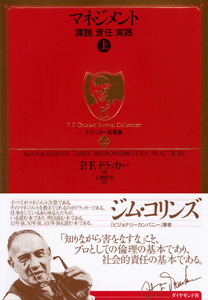
第297回
行政そのものが自ら成果を上げるには峻別、廃棄、強化が必要
今日では、ほとんどあらゆる政治リーダーが行政の縮小を唱えて政権に就く。だが、彼らの成果たるや惨憺たるものである。世界中いずれの国でも、彼ら反行政のリーダーの下で、政府支出と政府規制は増加する一方である。
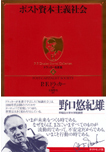
第296回
なぜ一転して失敗するのか事業提携の打率を上げるには5つの準備が必要である
今日、提携は百花繚乱である。合弁をはじめ、情報収集、研究開発、マーケティング、その他事業活動のあらゆる局面で、多様な形態の下に行なわれている。

第295回
高年者はまだまだ増える社会全体としての生産性の向上が喫緊の課題
「流行や修辞、あるいはマスコミ用語として、先進国で若さが強調されることはありうる。しかし現実には、あらゆる先進国が、その関心と行動の双方において、中高年中心、年金中心となっていかざるをえない」
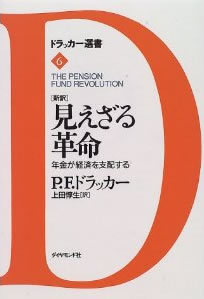
第294回
人口構造の変化が社会だけでなく経済と政治を変える
急速な社会の高齢化は、何をもたらすのか。高齢化社会の到来を、「見えざる革命」と名づけたドラッカーは、三つの変化を教える。
