上田惇生
第279回
大きな流れを知り基本に従う個々の変化には振り回されず流れそのものを機会とせよ
日本では誰もが経済の話をする。だが、日本にとって最大の問題は社会のほうである。この50年に及ぶ経済の成功をもたらしたものは、社会的な制度、政策、慣行だった。

第278回
最初から全員一致ではダメうわべを決めただけでは問題の本質に辿り着かない
ドラッカーは、独裁や官僚支配のない社会を探し、自由と自治を基本とする産業社会がその答えたりうると考えた。サラリーマン経験のないドラッカーに、企業の内部を見せてくれたのが、GMだった。

第277回
乱気流時代の鉄則は「機会には糧食を与え問題からは糧食を絶て」
資源を生産的な仕事に集中して、初めて生産性を上げることができる。逆に、資源の分散は、成果を上げることを不可能にする。

第276回
政治家や官僚や学者は高齢化社会と真正面から向き合うべき
「人口構造の重心が移動すれば、社会そのものが変化する。組織や問題はもとより、社会の風潮、性格、価値観が変わる。激震が走る」
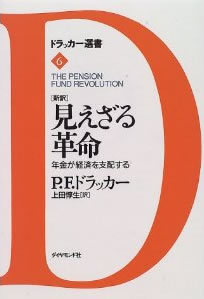
第275回
仕事で成果を上げるには中世ヨーロッパに伝わる“秘法”が参考になる
仕事で成果を上げるには、何をおいても、“自らの強み”を知らなければならない。だが、この自らの強みを知る人が著しく少ない。そもそも、そのようなことは考えたこともないという人がほとんどである。

第274回
これから求められる人材は会社の寿命よりも長く活躍する“プロフェッショナル”である
会社のほうとしては、寄りかかりの社員ばかりでは困る。今では、想像もできないことになったが、かつては働く者のほとんどが肉体労働者だった。

第273回
成功への道は自ら未来をつくることにより切り拓くことができる
先進国については、そしておそらく世界全体についても、すでに一つのことが確実である。根本的な変化が続く時代に入っているということである。

第272回
日本は人を大切にする国人を大事にしない国が他国のモデルにはなりえない
今日日本は、140年前と50年前の2つの転換期に匹敵する大転換期にある。ただし前の2つの転換とは違い、今回のそれは失政、混乱、敗北の類がもたらしたものではなく、主として成功の結果もたらされたものである。

第271回
必ず長期低迷を招くドラッカーが説く事業上の5つの大罪
「立派な企業が長期低迷に入る。いずれの場合も主たる原因は、事業上の5つの大罪の少なくとも1つを犯したことによる。だが、それらは、犯さずにすませる罪である」
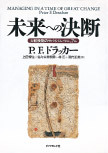
第270回
事業上の目的による企業買収に成功するには5つの原則がある
ドラッカーは、40年にわたる企業観察の結果、すでに1980年代の初めに、企業買収に成功するための5つの原則を「ウォールストリート・ジャーナル」に発表している。

第269回
この大転換期はいつ始まりいつまで続くのか
ドラッカーは『断絶の時代』の20年後の1989年、『新しい現実』において、歴史にも峠があると書き、さらにその4年後の93年には、『ポスト資本主義社会』において、この大転換期は2020年まで続くといった。

第268回
われわれは再び教育ある人間とは何であるか見直す必要に迫られている
ドラッカーは、学校に対して、二つの要求を行なう。第一に、肉体ではなく知識が中心の社会となったからには、知識の変化が急である。第二に、知識が中心の社会では、知識ある者がリーダーの役を務める。

第267回
中小企業には成長に足を取られる危険がある
ドラッカーは、ほぼ20年間、米国を代表する日刊の経済新聞「ウォールストリート・ジャーナル」への寄稿を重ねた。何を書いても、その日のランチで話題になった。しかも、なかなか内容が腐らなかった。
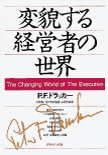
第266回
組織で成果を上げる能力は生まれつきのものかそれとも習得するものか
ドラッカーは、成果を上げる能力は、生まれつきのものか、後天的に習得するものかと問い、“習得するもの”だと断言する。

第265回
リスクの大小はリスクの大きさではなくリスクの性格で判断する
世界で最初の、かつ今日に至るも最高の経営戦略書とされている本書において、ドラッカーは、経営計画では、まずリスクの種類を明らかにせよといった。

第264回
文明の担い手は“組織”を動かすマネジメントである
産業社会は社会として成立するか、それは社会的存在としての人間を幸せにするかとの問いを発したドラッカーが、一年半をかけ下した結論が、「成立する」「幸せにする」だった。

第263回
予測はせずとも見えてくるグローバル化の流れ
ポスト資本主義社会における“ポスト”とは、○○の後という意味である。したがってそれは、資本主義社会の後の社会である。

第262回
企業は社会的組織であり共通の目的に向けた活動を組織化するための道具である
ドラッカーは、いかなる経緯でマネジメントを体系化し、“マネジメントの父”とされるようになったのか。もともとは、1909年にウィーンで生まれたオーストリア人である。

第261回
株主至上主義によって“産業が機能する社会”は構築することができるか
今から約70年前の1939年、ドラッカーは、処女作『「経済人」の終わり』を書いた。「経済人」とはエコノミック・マン、すなわちエコノミック・アニマル、経済至上主義のことだった。

第260回
現代日本が抱える機会不平等にも通じる“経済至上主義”
生産手段を人民のものにするというマルクス社会主義の処方もブルジョア資本主義と同様、約束した平等は実現できなかった。しかも両者は、経済を中心に置く経済至上主義だった。
