上田惇生
第333回
経営者が今なすべきことはリーダーシップを取り戻すこと それを社会が待っている
やがて不合理は終わり、合理が全面支配するようになるという近代合理主義の約束は反故となり、〈必然の進歩〉への信仰は裏切られた。進歩は、自動的に得られるものではなく、一歩一歩の積み重ねによるしかないことはますます明らかになった。

第332回
経済史上、偉大な企業の興隆は3つの保証ずみのアプローチのいずれかによっている
GMの中興の祖アルフレッド・P・スローンは、価格と性能の異なる5つの車種で市場をカバー。各車種は、上下の車種と競争関係にあるよう設計した。それまで厄介者だった中古車市場こそ大衆市場であるとし、新車は数年で下取りに出せるよう設計。スローンの構想は、大掴みの〈理想企業〉のビジョンによるものだった。

第331回
自らのイノベーションの成果を常時評価していくことによって企業家精神を醸成する
自らのイノベーションを評価することは難しいことではない。行なうべきことは三つある。さらには、わが社が得意とするイノベーションの方法が明らかになり、不得手とする方法が明らかになる。

第330回
都立高校の野球部にとって「われわれの事業は何か」「われわれの顧客は誰か」
ドラッカーとは、現代社会最高の哲人である。同時に、マネジメントを発明したマネジメントの父である。かつ、“それぞれのドラッカー”である。

第329回
組織は本業に焦点を合わせ成果を上げて収入を得る他の仕事はアウトソーシングする
ドラッカーはこういう。「それは、いかにコストがかかっていようとも、トップマネジメントの内の一人として大きな関心を持たず、十分な知識を持たず、面倒を見ようとせず、重要とも思っていない領域である。それは、組織の価値体系の外の領域にある仕事である」。
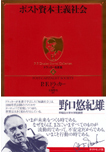
第328回
マネジメントたるものは自らの打率を知り上げていかねばならない
事業の将来は、投資、人事、イノベーション、戦略についての、今日のマネジメントの仕事ぶりによって左右される。しかもこの4つの分野において、打率を測定することは可能である。マネジメントは自らの打率を知ることによって、それを向上させることができる。

第327回
自己目標管理は全員のビジョンを方向づけ個の強みと責任を全開する
組織に働く者全員が、自らと自らの率いる部門が上位部門に対して果たすべき貢献、つまるところ、組織全体に対して果たすべき貢献について、責任を持たなければならない。
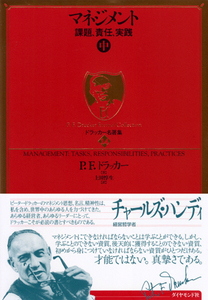
第326回
景気の変動にかかわりなく計画し発展していくために押さえておくべきこととは
景気循環から目を離してはならない。しかし、景気循環に焦点を合わせている限り、なにもできなくなる。そもそも今、景気循環のどこにいるのかさえ、いかなる経済学者にもわからない。景気循環についてなにかがわかるのは、循環の波が通り過ぎた後である。

第325回
公的機関が必要とするのは卓越した人材ではない六つの“規律”である
今ようやく日本でも、公的機関の見直しが急ピッチで進められている。しかしドラッカーは、すでに3分の1世紀前に、公的機関に成果を上げさせるための規律を明らかにしている。
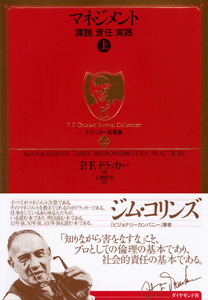
第324回
企業家精神を当然とするにはイノベーションの機会に注意を払わせる仕組みが必要
マネジメントの目を機会に集中させなければならない。人は提示されたものは見るが、提示されないものは見逃す。そこでドラッカーは、効果が実証ずみの、企業家精神浸透のための方策を三つ教える。

第323回
いつの間にか時代はモダン(近代合理主義)からポストモダンへと移行した
暗黒の中世にあって、一つの真理を得るならば、論理の力によって、もう一つの真理を得られるはずと考えた幾何学者がいた。とするならば、さらにそこから、もう一つの真理を得る。こうしてやがて、森羅万象、神の存在まで論理の力によって明らかにすることができるとした。

第322回
上司を高く評価せよ上司をマネジメントすることは上司と信頼関係を築くこと
ドラッカーは、上司との関係において、第一に行なうべきことが、上司リストの作成だと言う。上司とは、自分が報告すべき相手、自分に指示を出す者、自分の仕事と仕事ぶりを評価する者、自分が成果を上げるうえで必要となる者全員ある。

第321回
80歳のヴェルディのように失敗しようとも完全を求めて挑戦していこうと決心した
ドラッカーは、知識によって働く者にとって多少なりとも参考になるのではないかと言って、自らの経験をいくつか教えてくれる。その一つが、イタリアの大作曲家ヴェルディの最晩年の作品「ファルスタッフ」との出会いだった。

第320回
人事には“手順”があるトップが全力を尽くさなければ組織そのものへの敬意を損なう
人事に関する手順は、多くはない。しかも簡単である。仕事の内容を考える、候補者を複数用意する、実績から強みを知る、一緒に働いたことのある者に聞く、仕事の内容を理解させる。

第319回
成果を上げるには仕事の手段としての会議の生産性を上げよ
知識労働の生産性向上の基本は、行なう必要のないことは行なわないことである。常に、それをしなければ、会社はつぶれてしまうのかを考えなければならない。

第318回
定年で退職した人たちの多くが自分たちが欲していたものは長期休暇だったことを知る
ドラッカーは、65歳定年制はとうの昔に時代錯誤になっているという。定年年齢として65歳が定められたのは、19世紀のビスマルク時代のドイツであり、それが米国に導入されたのは第一次世界大戦時だったという。

第317回
20世紀を生きたドラッカーが21世紀のために遺したものがマネジメントだった
産業革命が人類に膨大な生産力を与えた。そこにブルジョワ資本主義なるイズムが現れ、自由に経済活動を行なわせるならば、見えざる手によって、自由と平等は万人のものになると約束した。
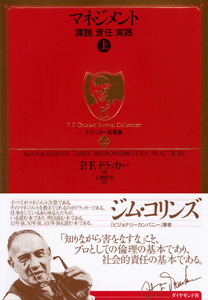
第316回
チェンジ・リーダーたるには変化するための前提として“廃棄”が必要不可欠である
ドラッカーは、1980年代半ば以降、少なくとも企業の世界では、変化への抵抗という問題はなくなったという。内部に変化への抵抗があったのでは、組織そのものが立ち枯れとなる。かくして、変化できなければつぶれるしかないことは、ようやく納得された。

第315回
21世紀の企業はグローバル化することによって文明と文化の懸け橋となる
市場がグローバルになったために、あらゆる経済活動がグローバルに行なわれるようになり、かつ、企業そのものがグローバルな存在になった。一国の文化、慣習、法律にとらわれることなく、グローバル経済において成果を上げるべき存在となった。
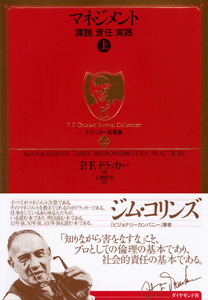
第314回
強みを持つ分野を探しそれを仕事に適用させることは人の特性からくる必然である
パナソニックの中村邦夫は、ある事業を任されたとき、ドラッカーを座右の書としたという。ユニクロの柳井正は、ドラッカーの教えによって今日のユニクロを築いた。このような人たち、このような会社が無数にある。
