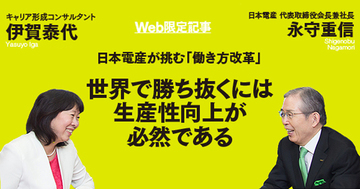永守重信
日本電産の永守重信会長は、「経営者は自分自身の器を大きくしていかなければなりません。私もこれまで器の大きい人からたくさんのことを学んできました」と告白する。あるとき、オムロン創業者の立石一真さんのところに出向くと、衝撃の光景に出くわし、自分の器を省みる機会になったという。

日本電産の永守重信会長は、「泣かない、逃げない、やめない」の「3ない主義」を貫くことができれば、必ず物事は好転すると説く。【「この円安ではねえ……」「これは私のせいじゃない。私は精一杯やっているが、外部環境がこうも変わってくると難しい。これが限界です」と言ってもよいのであれば、そもそもリーダーは必要ありません。為替も変わらない、売値も買値も変わらない、外部環境も変わらないのだったら、誰が経営しても結果は一緒になるからです。】

日本電産を売上高1兆9000億円の巨大企業にした永守重信会長兼CEO。創業当初から従業員の育成について熱心に取り組み、社内にもいろいろな塾や経営人材育成プログラムなどをつくって人材を育ててきました。日本電産で活躍しているのはどのような社員なのでしょうか?また、大声試験、早食いなど一風変わった採用試験を行った理由などを永守氏の著書『大学で何を学ぶか』(小学館新書)より抜粋して紹介します。

経営者として今まで1万人以上の従業員の採用に携わった日本電産の永守重信会長兼CEO。今までたくさんの大学生や院生を採用してきたからこそ、永守会長は今の若い人たちに何が足りないのか、なぜ元気がないのかが分かるそうです。大学進学を考える高校生に向けた著書の中にも、今の時代を生きるビジネスパーソンへの熱く厳しいエールが随所に見られます。永守会長は、若い社員たちに「失敗したくなかったら、たくさん失敗せよ」と伝えています。また「リーダーこそ挫折や失敗を数多く経験しておく必要がある」と言います。その真意とは?『大学で何を学ぶか』(小学館新書)より抜粋して紹介します。

カリスマ経営者として知られる日本電産の永守重信会長兼CEOは、「人間は基本的に失敗するようになっています。それを防ぐには、異常と思えるくらいのことをやるべきだということです」と説きます。どういうことか、永守会長自身の失敗談を交えながら語ります。

結果がすべての経営者が唯一やってはいけないことは、会社をつぶすということです。会社がつぶれるということは、人間が死ぬのと一緒で、逆にいえば、つぶれない限りは、何度だってチャレンジして、業績を回復させたり、業界トップになることだってできます。要は、「リスク管理」をどうするかということです。もちろん、「つぶれないように、つぶれないように」と思い過ぎてしまうと、それはそれでうまくいきません。

日本電産の永守重信会長兼最高経営責任者(CEO)は、「事実として、経営者には子分が必要」と説く。親分からの無理難題であっても、「わかりました」と親分を信じて実行する部下のことだ。永守会長の独特な経営者論とは?

カリスマ経営者として知られる日本電産の永守重信会長は、京都先端科学大学の理事長として、偏差値教育に偏った日本の大学教育の変革に取り組んでいる。その中で、自分の夢を持ち、夢を語ることができる人材の育成に力を注ぐ。優れたリーダーに求められる「夢を語る力」とは?

日本電産の永守重信会長兼最高経営責任者(CEO)が定義する「ハードワーキング」とは、長い時間働くことではなく、競争相手に勝てるスピードで仕事をして、結果を出すことができる働き方のこと。このハードワーキングを実践してきたことで、日本電産は今日の発展を遂げ、永守会長のカリスマ経営者としての名声も高まったといえる。結果を出すために求められる働き方と姿勢について語った。

世界で勝ち抜くには生産性向上が必然である
残業をゼロにするため、2020年までに1000億円を投資する──。働き方改革が求められる中、日本電産・永守重信会長兼社長によるこの発表は、大きな注目を浴びた。「モーレツ」を代名詞とする同社の永守会長はなぜ、このタイミングで大きな決断を下したのか。そこには、真のグローバル企業になるうえで生産性向上が欠かせないという危機感があった。ベストセラー『生産性』の著者であり、マッキンゼー・アンド・カンパニーで人材育成のマネジャーを務めた伊賀泰代氏が、その真意に迫る。