大塚玲子
PTAは本来「任意で活動する団体」のはずだ。強制参加が常態化しているが、仕事や育児の都合で「参加拒否」しても全く問題ないはずである。では、PTAが苦痛だという人が実際に活動をやめるにはどうすればいいのか。その際に周囲の保護者からの心証を悪くしない方法とは――。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#2では、PTAや学校、保護者に豊富な取材経験を持ち、書籍『さよなら、理不尽PTA!』などを上梓している筆者が、参加拒否の具体的方法と注意点を伝授する。

わが子が小学校に入り、PTAの活動が始まった親も多いだろう。連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#1では「PTAの問題点」を基礎から解説する。PTA会員の仕事内容に応じてポイントを付与し、獲得数のノルマを課す「ポイント制」など、悪名高い仕組みが生まれる背景とは――。

保護者に負担がかかることから、昨今はベルマーク集めやバザーなどの恒例行事を取りやめるPTAが出てきています。その一方で、これらの作業を続けるPTAも根強く残っており、組織ごとの方針の違いが鮮明になってきました。ベルマーク不要論が出ても「やっぱり続ける」PTAが存在するのはなぜなのでしょうか。PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が考察します。

保護者・教員によるPTAへの加入は、本来は「任意」であって「強制」ではありません。にもかかわらず、加入意志を確認しないまま会費を徴収するPTAがいまだに多くあります。近年は、そうした組織体制のおかしさに気付いた保護者や教職員が、PTAを相手取って調停や裁判を起こす例が見られるようになりました。その結果はどうなったのでしょうか? PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が解説します。

PTAの運営体制においては、かねて「会費を強制徴収」していることが問題視されてきました。この悪しき風習を脱却するべく、実は今、会費を「無料」にするPTAがじわりと増加しているのです。そうしたPTAは、どうやって運営しているのでしょうか。会費無料化が進む一方で、「それでは困る!」と難色を示す、意外な抵抗勢力とは――。PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が解説します。

PTAの問題点は「強制参加」「ポイント制度」「ベルマーク集め」などの旧態依然とした仕組みや行事だけではない。各自治体のPTAが集まって結成する、実質的な上部組織(=P連)の運営体制にも課題が山積みである。多くの保護者や教職員はP連の存在すら知らないままお金を納めており、P連による資金の使い道はあまり表に出てこない。だが、実は「数千万円の使途不明金」が生じて問題になることも――。

本連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」では、2024年もPTAの最新動向や問題点に迫っていく。今回のテーマは「PTAの解散」。コロナ禍の到来によって対面での組織運営が難しくなったことから、ここ数年間でPTAのあり方が見直されるようになった。解散を決断するPTAも見られるようになった。では、コロナ禍が一段落した今、PTAを解散する動きはどうなっているのか。解散した学校はどうなったのか。PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が、リアルな現状をリポートする。

経営者や弁護士といった「大物PTA会長」が、旧態依然としたPTAの風土を変えたという報道を見かけることがある。だが実は、こうした成功例はごく一部だ。表に出ていないだけで、大物会長によるPTA改革がうまくいかなかった例も多い。改革を阻むのは、体制を元に戻そうとする「抵抗勢力」である。PTAの問題点が広く知られるようになった今も、反対派はなぜ出現するのか。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の番外編では、PTA改革が難航する理由について解説する。
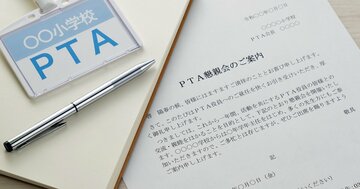
PTAの旧態依然とした組織風土に苦しめられているのは保護者だけではない。PTAのT、すなわち教職員も「強制参加」「会費の強制徴収」などに苦しめられている当事者なのだ。中には「退会しようとしたが、校長に止められた」「『加入は必須』と間違った説明を受けて会費を引き落とされ、少額訴訟を起こした」という教員も存在する。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の番外編では、世間にはあまり知られていない「PTA活動における教職員の負担」について徹底解説する。

入学式の季節から1カ月がたった。中にはPTA役員が決まるまで、保護者が体育館の外に出られない“儀式”を経験した人もいるかもしれない。これからのPTA活動について「先が思いやられる」という親もいるだろう。だが、小・中・高と、子どもの学生生活は今後も続いていく。父母のPTA活動は、まだ始まったばかりだ。そこで短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の番外編では、中学・高校など「小学校以外」のPTAの実態について解説する。「小学校よりも楽」という通説の真偽と、意外な注意点とは。

女性の社会進出が盛んになった今もなお、「PTAは母親がやって当然」という固定観念が色濃く残っている。だが、一くくりに母親と言っても、専業主婦もいれば働く母もいる。時代の変化の中で、いつしか両者は、PTAへの参加頻度や役員選びを巡って対立するようになった。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の最終回となる#6では、「ひとり親」として働きながら子どもを育ててきた筆者が、取材や私生活で見た対立の実態と、それらを踏まえて考えた解決策を語る。

保護者が当たり前のように支払っているものの、その使い道がよく分からないのが「PTA会費」だ。PTAの活動資金が会計担当者などに横領される事件も毎年のように起きている。本来「寄付金の強制徴収」は違法に当たるが、実は学校に寄付されているケースもある。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#5では、PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が、そうしたPTA会費の「不条理な使い道」の実態を徹底解説する。

昨今はPTAを解散(廃止)したり、その活動を「代行サービス業者」に委託したりといった学校が増え始めた。解散や外部委託には至らないまでも、ひとまず休止している学校もよく聞くようになった。だが、そうした学校の“後日談”についてはあまり知られていない。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#4では、PTA・学校・保護者に豊富な取材経験を持つ筆者が、既存のPTA運営からの脱却を試みた各学校のリアルな現状をリポートする。
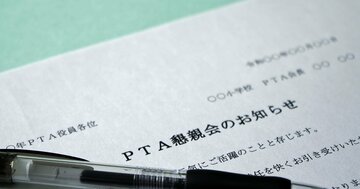
新型コロナウイルス感染拡大は学校のあり方だけでなく、PTAの活動にも少なからず変化を及ぼした。中には、これまで「強制参加」としていた活動を廃止したり、減らしたりしたPTAも存在する。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#3では、PTAが旧態依然とした体制から脱却しようとする動きについて、具体例を挙げながら解説する。コロナ禍を機に「なくても問題ない」と判断され、今後も復活の見込みが薄い活動とは――。
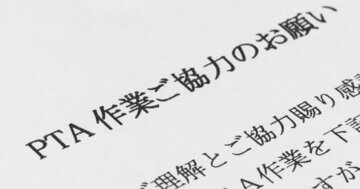
PTAは本来「任意で活動する団体」のはずだ。強制参加が常態化しているが、仕事や育児の都合で「参加拒否」しても全く問題ないはずである。では、PTAが苦痛だという人が実際に活動をやめるにはどうすればいいのか。その際に周囲の保護者からの心証を悪くしない方法とは――。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#2では、PTAや学校、保護者に豊富な取材経験を持ち、書籍『さよなら、理不尽PTA!』などを上梓している筆者が、参加拒否の具体的方法と注意点を伝授する。

進学・進級の季節になった。わが子が小学校に入り、PTAの活動が始まった親も多いだろう。だが、PTAはメディアやSNSで「恐ろしい組織だ」と批判されがちだ。実態が分からないまま、漠然とした不安に駆られている人もいるかもしれない。短期集中連載「大塚さん、PTAが嫌すぎるんですが…」の#1では、そうした層に向けて「PTAの問題点」を基礎から解説する。PTA会員の仕事内容に応じてポイントを付与し、獲得数のノルマを課す「ポイント制」など、悪名高い仕組みが生まれる背景とは――。
