片山晃
2003年「バブル崩壊後の長い停滞」から日本市場が底打ち、ドン底からの上げ相場では“無知こそが最大の武器”となった
連載『片山晃 東証相場録』の第3回は、1999年のマザーズ市場の創設から、その直後のITバブル崩壊、さらには2003年の歴史的な底打ちまでを振り返る。ITバブル崩壊以降の日本株は下落率、下落期間の長さ共に悲惨であったが、それだけに反転した際のエネルギーも大きかった。そして、雪解け後の日本市場では、デイトレーダーと呼ばれた開拓者たちの中から、常識外れのリターンをたたき出す若者が誕生することになる。
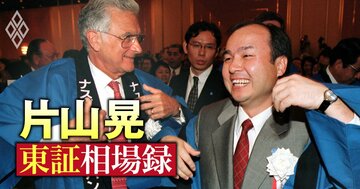
手数料自由化がもたらしたトレード革命、初期のデイトレは手法そのものに「新規性」と「収益機会」があった
連載「片山晃 東証相場録」の第2回。今回はインターネット証券の黎明(れいめい)期や、デイトレードが脚光を浴びた時代を振り返る。売買手数料の自由化により誕生した「デイトレード」だが、当時は手法そのものに新規性があり、それに気が付いただけで収益機会があった。BNF氏やcis氏など個人投資家の台頭、ライブドアショックが襲うまでの熱狂の新興市場バブル……、その裏側で片山氏が考えていたことも公開する。

「3.11の記憶」がよみがえった8月の暴落、愚か者のリストに署名した
「元手65万円から資産160億円」を築いた片山晃氏が、自らの投資行動やその時々に感じたことを交えながら、インターネット証券の黎明(れいめい)期から今日までの相場を振り返る連載『片山晃 東証相場録』がスタート。ネットの発達や企業の開示姿勢が柔軟になったことで、個人投資家も株式投資に必要な膨大な情報を集められるようになった。ただし、その大部分は銘柄情報や金融政策の変更など目先の内容である。相場は姿や形を変えて繰り返すことが多い。投資の教科書には掲載されない歴史や、リアルな投資判断の裏側にある考え方を知ることは、皆さまの投資技術の上昇にも役に立つはずだ。
