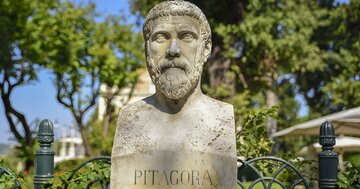天才数学者たちの知性の煌めき、絵画や音楽などの背景にある芸術性、AIやビッグデータを支える有用性…。とても美しくて、あまりにも深遠で、ものすごく役に立つ学問である数学の魅力を、身近な話題を導入に、語りかけるような文章、丁寧な説明で解き明かす数学エッセイ『とてつもない数学』が6月4日に発刊。発売4日で1万部の大増刷となっている。
教育系YouTuberヨビノリたくみ氏から「色々な角度から『数学の美しさ』を実感できる一冊!!」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。連載のバックナンバーはこちらから。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
よく考えると矛盾した発言
「自己言及のパラドックス」というのをご存じだろうか。パラドックスというのは、正しく見える前提や論理から、納得しがたい結論が導かれてしまう問題のことをいう。「自己言及のパラドックス」の例として最も有名なのは「私は嘘つきである」という発言である。
なんの変哲もない言い回しに思えるが、よく考えるとこの発言は矛盾している。もし、この発言が本当だとすると、
私は嘘つき→「私は嘘つきである」という発言も嘘 → 私は正直者
となるが、「私は嘘つき」という前提で始めたのに、「私は正直者」という結論が得られるのは矛盾である。では、この発言が嘘だとするとどうだろう。今度は
私は正直者 →「私は嘘つきである」という発言も本当 → 私は嘘つき
となり、同様にやはり仮定と結論が矛盾する。
つまり、「私は嘘つきである」という発言に対しては、真(本当)であると言うことも偽(嘘)であると言うこともできない。
一般に「この文は偽である」という構造を持っている文は、真偽の判定ができない。これを「自己言及のパラドックス」という。他にも「例外のない規則はない」という規則や、「この壁に張り紙をしてはならない」という張り紙等の例が知られている。
ところで数学はどうであろうか? 数学において命題(客観的に真偽が判断できる事柄)であるのに、真偽の判定不能なものなどあるだろうか?
数学には「真であることが証明された事柄」と「偽であることが証明された事柄」のどちらかしかないというのは、多くの人に共通する認識だろうと思う。もちろん今現在、真偽が判定できていない命題というのはある。ただそれは人間の能力の問題であり、やがては必ずどちらかに分類されるはずと思っている人は多いのではないか。
しかし「数学には真であることも偽であることも証明できない命題が存在する」ことを明らかにしてしまった人物がいた。それがチェコのクルト・ゲーデル(1906~1978)である。
19世後半から20世紀初頭の数学界は一時期混沌とした状況にあった。
図形への興味から生まれ、土木や航海の技術として発展した幾何学、未知なるものを求める方法としてスタートし、方程式論へと進んだ代数学、図形の求積と物理現象の解明のために必要とされた微分積分学、そして国を治めるために使われ出した統計学、ギャンブルにおける利益追求から生まれた確率論……等々が脈略なく生まれ、大きくなっていた。言わば、数学という名のビルに各々が雑居していたわけである。
そうした中、ゲオルク・カントールが打ち立てた集合の概念を使って、数学界を「再編」しようとする動きが強まっていった。